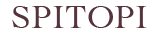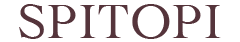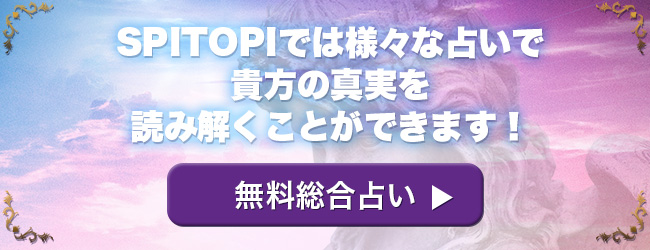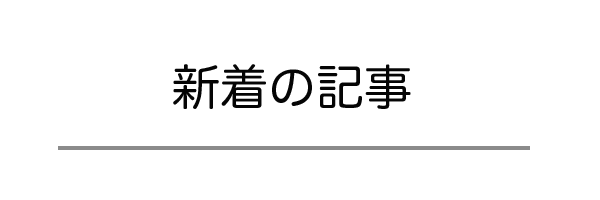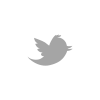何か事件が起こった時に状況が風化するまでや、落ち着くまでの期間を「ほとぼりが冷める」と言ったりします。
出来事後というのは周囲も関心を持っていて少しでも行動に移してしまうと、何かと目立ってしまうため、熱が冷めるまでジッとしていようと思うものですが、人の気持ちや記憶とは徐々に薄れていくものです。
今回はその状態を表す「ほとぼりが冷める」という言葉について詳しく見ていきたいと思います。
- 「ほとぼりが冷める」の意味とは?
- 「ほとぼりが冷める」の似た語や類語・言い換え
- 「ほとぼりが冷める」の使い方
- 「ほとぼりが冷める」を使った例文
- 「ほとぼりが冷める」期間は何時間か
- 「ほとぼりが冷める」を使ったその他の言葉
- 「ほとぼり」の語源とは
- まとめ
1. 「ほとぼりが冷める」の意味とは?

1-1. 「ほとぼりが冷める」の読み方や意味
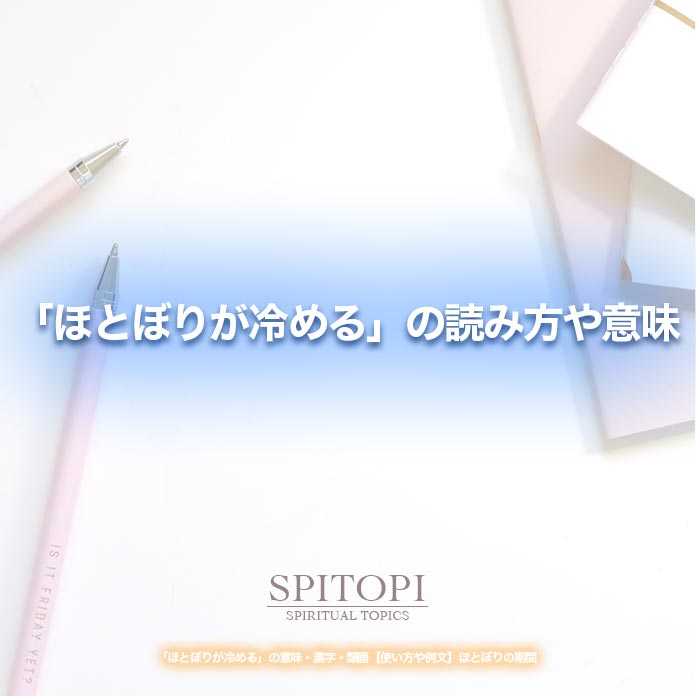
「ほとぼりが冷める」は【ほとぼりがさめる】と読みます。
意味は、
- 余熱が冷めることや、残った熱がなくなること
- 事件や世の中の関心を集めるような出来事が起こった後の興奮が収まったり、関心が薄れたりすること
- 徐々に、ゆっくりと熱した感情が薄れていくこと
などをいいます。
1-2. 「ほとぼりが冷める」の漢字

まず「ほとぼり」は漢字で「熱り」「余熱」と書きます。
「余熱【よねつ】」と書いて「ほとぼり」と読むには、この慣用句を知っていないと難しいでしょう。
ですが強引な当て字ではありますが、「ほとぼりが冷める」の意味を考えればこの漢字はふさわしいかもしれません。
そして「ほとぼり」とは、
- 世の中の関心事の熱が冷めていく途中
- 加熱した感情が薄れていく過程
- 興奮や熱気がまだ少し残る状態
を表し《まだ完全には熱が冷めていない状態、まだ微妙に熱を帯びている状態》を表します。
2. 「ほとぼりが冷める」の似た語や類語・言い換え

2-1. 下火になる【したびになる】

「下火になる」とは、「火勢が衰えていくこと」や「それまで勢いがあり盛んだったものが徐々に衰えていくこと」という意味になります。
- 「一時期、一世風靡したあのゲームも今やかなり下火になっている」
- 加熱した感情が薄れていく過程
- 「下火にはなったが、自分にとってはあれが一番使いやすいシリーズだと思う」
など。
2-2. 熱気が収まる【ねっきがおさまる】
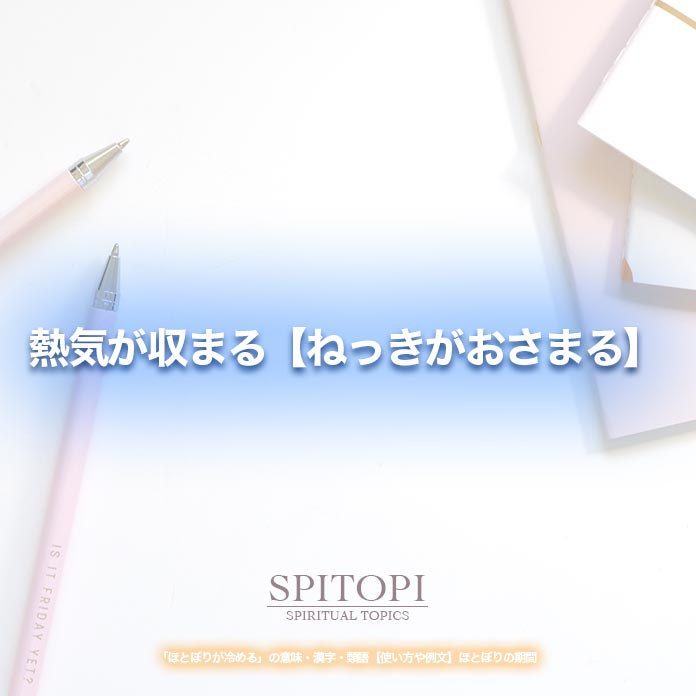
物事への関心や興味などが一旦落ち着く事を言います。
もしくは物理的に熱を帯びるものの熱さが冷えた状態を表します。
- 「大ファンだったみたいだが、興味も落ち着き、熱気が収まったようだ」
- 「蒸暑いとは聞いていたから覚悟していたけれど、少し熱気が収まり過ごしやすくなった」
など。
2-3. 勢いが衰える【いきおいがおとろえる】
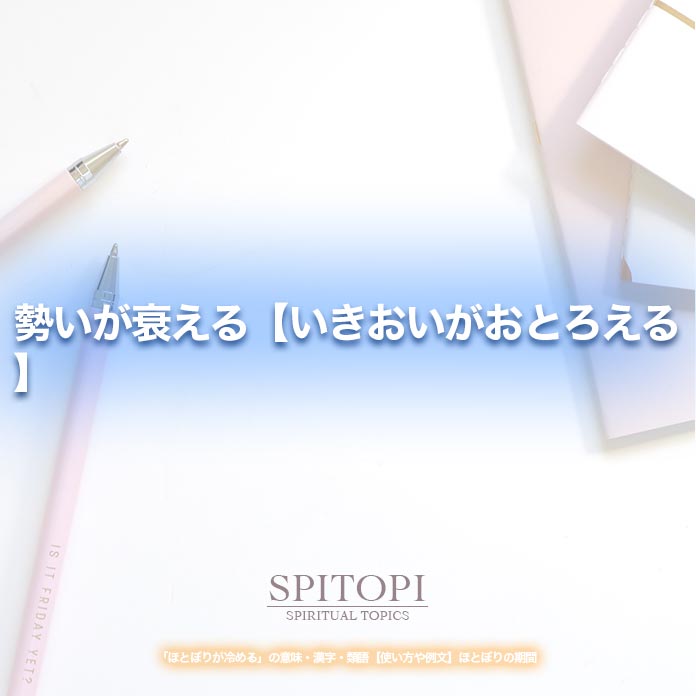
今まで力や活気などを保っていたもののパワーがなくなることや、ペースが落ち弱々しくなる事をいいます。
またこれまでの様な元気がなくなる場合にも使います。
- 「あれ程威勢が良くギラギラしていたのに、突然勢いが衰えてこちらが驚いている」
- 「勢いが衰えると、今までうまくいっていたものがうまくいかなくなるものだ」
など。
3. 「ほとぼりが冷める」の使い方

何かの事件、世の中が関心を持つような出来事、注目を集めるような話題が起き、そこから少し時間が経ったり、ゆっくりと関心や興味が薄れている状態の熱が、本当になくなって冷めてしまった時に使う言葉になります。
ほとぼりは徐々に冷める《余熱》になるので突然なくなるわけではありません。
ですから経過を要する物事が終息する時に使います。
4. 「ほとぼりが冷める」を使った例文

4-1. 例文1

「彼女は決して諦めたわけではなく、ほとぼりが冷めるまで連絡しないと決めているみたいだ」
4-2. 例文2

「人の噂も七十五日というから、ほとぼりが冷めるまでもう少しの辛抱だね」
4-3. 例文3

「暫くはここにいた方がいい。
ほとぼりが冷めたら、すぐにでも荷物をまとめて手続きをした方がいい」
4-4. 例文4

「テレビではまだあの騒動を取り上げているが、誰が興味あるのだろう。
さっさとほとぼりが冷めて、違う話題に移って欲しい」
4-5. 例文5

「やっとほとぼりが冷めてきたので、そろそろ妻と真剣に今後について話し合いたいと思います」
5. 「ほとぼりが冷める」期間は何時間か

まず、一言で「ほとぼりが冷める」期間といっても、その物事によって変わってきます。
世界的にみても大事件であったり、衝撃的な出来事と、人一人単位の出来事では全くほとぼりの熱量が違うでしょう。
その事を踏まえどのような場合があるかをみていきたいと思います。
5-1. テレビのニュースになる様な出来事

凶悪事件や芸能ゴシップなど、テレビやネットなどで幅広く扱われるような内容は、国を超えて話題になったり関心を持たれる事が多々あります。
特にポジティブな物よりも、ネガティブな物の方が関心を持たれやすく、過熱しやすくなるものです。
「人の不幸は蜜の味」という言葉がありますが、まさしく喜ばしくない出来事の方が燃え方は激しくなり、その後のほとぼりにも影響を及ぼす事になるでしょう。
ただその期間は1ヶ月であったり何年も続く事もあるなどバラバラで、次から次へと大きな出来事が勃発する方が、一つずつのほとぼりの期間は短かくなる傾向にあります。
それは人の関心や興味が新しいものに流されやすいという心理からくるものだからです。
また同じようなものが続くと食傷気味になりほとぼりも冷めやすくなります。
ただ、新しい出来事の影響で忘れかけていた出来事に再度火をつけてしまい、冷めかけていたほとぼりが冷めず続いてしまう事もあります。
5-2. 個人的な出来事

例えば浮気や不倫、裏切りに遭ったなどの出来事の場合は、その一人ずつの受け止め方や出来事の重さで、ほとぼりの期間は変わってくると思います。
また、振られてしまったけれど連絡したいなどといった場合も、あまりにもすぐに連絡を取ってしまっては逆効果になってしまう事もあります。
個人レベルで「ほとぼりが冷める」期間は約3ヶ月程度だと言われています。
これは一つの季節が巡り景色が変わるので時間が経った事を感じやすくなるのが理由のようです。
もちろん何度も言いますが、物事の深さや重さ、傷の深さ、関係性などで状況は変わるので、「ほとぼりが冷める」までの期間は様子を見る必要があるでしょう。
6. 「ほとぼりが冷める」を使ったその他の言葉

6-1. 「ほとぼりが冷めるまで待つ」

「ほとぼり」はゆっくり、徐々に冷めていくものであり、最初の熱量が大きいほど冷めるにも時間が掛かります。
つまり、その冷めるまでの期間を何か別の事をしたり、違う場所で待機しながら待つという意味になります。
6-2. 「ほとぼりが冷めやらない」

何かの事件や出来事、世間を騒がせている物事の関心や興味の余熱や熱気がまだ冷めていない事をいいます。
「ほとぼりが冷めやらない」の後には「うちに◯した」や「まま◯しようと思う」などと言った動詞が入り、まだ冷める前に何らかの行動を起こした時に使います。
7. 「ほとぼり」の語源とは

「ほとぼり」は元々「ほとほり」と濁っていなかったと言われています。
そもそも昔はロウソクの火の後やかまどの余熱の事を「火通り【ほとほり】」や「火点り【ほとぼり】」と呼んでいて江戸時代ごろから、「ほとぼり」と変化したと伝えられています。
そしてその徐々に冷めていく熱の様子から人の感情と重ねられ、冷めていくまでの過程を表現した言葉になったようです。
まとめ

「ほとぼりが冷める」ような出来事には遭遇したくないものです。
暫くの間はおとなしく過ごす事になり、場合によっては人前に出る事も憚れるかもしれません。
ですが、自分について見直す期間だと思えば、プラスになりますし、「ほとぼり」になる様な出来事についても今後のために反省したり考えてみるチャンスになるかもしれません。
まとめ

「ほとぼりが冷める」ような出来事には遭遇したくないものです。
暫くの間はおとなしく過ごす事になり、場合によっては人前に出る事も憚れるかもしれません。
ですが、自分について見直す期間だと思えば、プラスになりますし、「ほとぼり」になる様な出来事についても今後のために反省したり考えてみるチャンスになるかもしれません。
スポンサーリンク