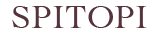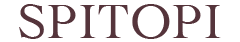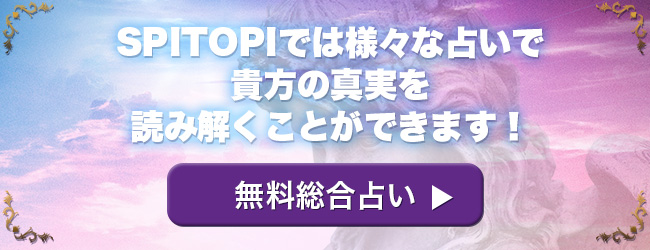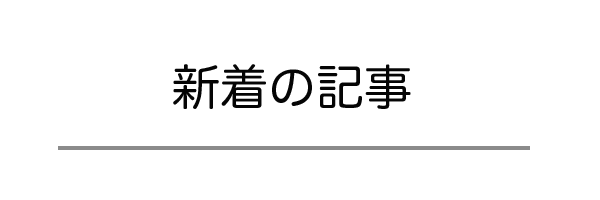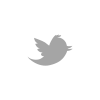色鮮やかなキャベツのような葉牡丹(ハボタン)ですが、街中の花壇などでも見かけることがあります。
よく見かけるのですがどんな植物なのかよくわからないという人もいることでしょう。
ここでは葉牡丹(ハボタン)の花言葉、花についてまとめてみました。
ぜひ参考にしてみてください。
- 葉牡丹(ハボタン)とはどんな花?特徴
- 葉牡丹(ハボタン)の花言葉
- 葉牡丹(ハボタン)の育て方や注意点
- 葉牡丹(ハボタン)の名前の由来
- 葉牡丹(ハボタン)の開花時期
- 種類(園芸品種)
- 葉牡丹(ハボタン)は食べられるのか?
- 葉牡丹(ハボタン)の歴史
- 踊り葉牡丹(ハボタン)とは
- 葉牡丹(ハボタン)の病害虫
- まとめ
1. 葉牡丹(ハボタン)とはどんな花?特徴

葉牡丹(ハボタン)はアブラナ科アブラナ属の多年草です。
鮮やかな葉を鑑賞します。
寒さに強く冬の公園を彩ってくれます。
色は赤、クリーム、白、ピンクとあります。
牡丹のような見た目で、形はキャベツのようです。
葉牡丹(ハボタン)はキャベツから品種改良されて今の形になっているといわれています。
別名「ハナキャベツ」と呼ばれています。
ヨーロッパ原産なのですが、日本で改良が進みました。
江戸時代の頃から栽培されていて「古典園芸植物」のひとつとなっています。
2. 葉牡丹(ハボタン)の花言葉

2-1. 祝福

紅白の色合いがおめでたいということで正月の飾りなどに使われています。
そこから由来しているといわれています。
2-2. 愛を包む

中心の花を葉っぱが包んでいるのですが、中心の花が「赤ちゃん」でありそれを包み込むということで愛を包むという花言葉になったのだといわれています。
2-3. 物事に動じない

物事に動じないという花言葉がありますので、お世話になっている方、尊敬している方に贈ると良いとされています。
2-4. 利益

見た目がキャベツに似ていることから、昔戦場でキャベツを作って兵士に食べさせる食糧とした、役に立ったという話から利益という花言葉になったとされています。
3. 葉牡丹(ハボタン)の育て方や注意点

3-1. 植え方

葉牡丹(ハボタン)の種まきの頃は真夏7~8月の頃になります。
浅い箱に種をまき薄く土をかけます。
土が乾かないように水やりを続けてください。
9月頃に本葉が2~3枚出てきましたら、苗を鉢や花壇などに植え替えてください。
葉牡丹(ハボタン)の苗は10~11月頃に植え替えていきます。
この時期より遅くなりますと根ばりが悪くなるといわれていますので注意をしてください。
鉢植えをする場合は6号鉢より大きいものを準備してください。
水はけのよい清潔な土を用いるようにしましょう。
花壇、庭など地植えする時は日当たりの良い場所にしてください。
大きな株の場合は30~40センチぐらい間隔をとりましょう。
小さな株の場合は20センチほどです。
株同士の葉が重ならないように空けるようにします。
3-2. 育て方

葉牡丹(ハボタン)は日当たりと風通しの良い場所で育てるようにしましょう。
ただし、北風、強い霜などには注意をしてください。
キャベツやブロッコリーと同じくアブラムシ、アオムシといった害虫がつきやすいですので、植える時に殺虫剤を用意しておくといいでしょう。
水やりは植え替えた後は2週間ほど土が乾燥しないように水をやりましょう。
しっかり根づいてからは土の表面が乾いた時に水をたっぷりあげるようにするといいでしょう。
3-3. 肥料について

葉牡丹(ハボタン)の株を植え替える時に窒素、リン酸、カリウムが同量配合された緩効性の化成肥料を土に混ぜましょう。
葉が色づきはじめたら肥料を与える必要はありません。
10月以降に肥料を与えてしまいますと、葉の色が綺麗にならなくなるので注意しましょう。
また小さいサイズの葉牡丹(ハボタン)の時は肥料を薄めて少量にするなど気をつけてください。
4. 葉牡丹(ハボタン)の名前の由来

葉牡丹(ハボタン)の名前の由来は葉を牡丹の花に見立てていることからだといわれています。
5. 葉牡丹(ハボタン)の開花時期

葉牡丹(ハボタン)は夏に種まきをして寒くなると共に色づく葉っぱを鑑賞する植物なのです。
お正月の頃に飾りとして使ったりもします。
順調に育ちますと開花時期は3月か4月です。
黄色い菜の花のような花が咲きます。
開花時期を過ぎましたら、種取り、剪定をしたり、もしくは一年草と割り切って処分するなど、各自で選ぶといいでしょう。
しかし、葉牡丹(ハボタン)は花よりも葉っぱが色づく11~3月の方が見頃となります。
6. 種類(園芸品種)

6-1. ちりめん系(名古屋ちりめん系)

葉っぱのふちが細かくフリル状になっています。
明治時代以降に名古屋で作られました。
根が他のものに比べますと弱いため花壇で育てるのは適していません。
鉢植えで育てるのがおすすめです。
薄紫色の葉が重なり合うように伸びている「紅かもめ」が代表品種となります。
6-2. さんご系

葉っぱに細く深い切れ込みが入っていて、観賞価値が高いとされています。
「紅孔雀」「白さんご」が代表品種です。
6-3. 東京丸葉系

江戸時代から育成が始まった古い系統となります。
葉っぱが丸くてキャベツに似ています。
寒さ、熱さに強いことから栽培がしやすいのが特徴です。
「日の出」が代表品種です。
6-4. 大阪丸葉系

東京丸葉系とちりめん系が交ざったもので、戦後に育てられるようになりました。
葉っぱのふちがゆるやかに波うっています。
葉っぱの発色が良くて育てやすいとされています。
「つぐみ」が代表品種です。
7. 葉牡丹(ハボタン)は食べられるのか?

キャベツのような見た目の葉牡丹(ハボタン)ですが食べられるかどうかといえば、アブラナ科ですので自分で育てて農薬を使用しなければ食べることはできるとされていますが、観賞用に品種改良していますので硬くて美味しくないということなのです。
売られているものに関しては綺麗に育つ為に農薬を使っているものが多いと思われますし、基本的に食用ではないと思っていた方がいいでしょう。
8. 葉牡丹(ハボタン)の歴史

現在の葉牡丹(ハボタン)が品種改良によって作られたのは江戸時代中期以降と見られています。
園芸ブームだったそうです。
縁起の良い紅白2色が好まれたといわれています。
明治時代以降は花が少ない時期、冬の園芸植物として広まりました。
そして海外にも紹介されていき、現在では世界各地で葉牡丹(ハボタン)は栽培されているのです。
9. 踊り葉牡丹(ハボタン)とは

花の少なくなる時期、寒さに耐えて綺麗に色づいた葉っぱを見せてくれる葉牡丹(ハボタン)ですが11~12月に色づいたのを楽しんで終わりと思っている人もいるかもしれません。
しかし葉牡丹(ハボタン)は面白い植物で、2~3月になると茎が伸び始めます。
草姿になり、ツリー風の見た目になります。
そして春になりますと花も咲くのです。
その花の後に切り戻しを行うとくねくねとした茎になり、その上に葉牡丹乗った「踊り葉牡丹(ハボタン)」が楽しめるのです。
4月の中頃、花が終わったら花下で切り戻してください。
そうしますと5月中旬頃にわき芽が伸びてきます。
この新芽の先に再び葉牡丹が出来上がりますのでくねくねと踊っているような見た目になるのです。
10. 葉牡丹(ハボタン)の病害虫

葉を食べてしまう、アオムシ、ヨトウムシ、コナガの幼虫がよくつきます。
2週間に一度殺虫剤を散布しましょう。
また、幼苗の時はナメクジ、アブラムシもつきますので、注意して見ておくことです。
また早目に駆除うようにしましょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
葉牡丹(ハボタン)の花言葉、花についてまとめて紹介しました。
子供の頃は葉牡丹(ハボタン)と知らずに色のついたキャベツだと思う人もいたのではないでしょうか。
色鮮やかな花が少なくなる冬時期に目を楽しませてくれる葉牡丹(ハボタン)ですが、初心者にも育てやすく、種類も豊富ですのでお勧めの植物です。
種類が違うものを寄せ植えにしたりと楽しみ方も色々あります。
お正月の飾りに買う人もいるのですが、自分で育ててみるのはどうでしょうか。
きっと葉牡丹(ハボタン)の魅力に夢中になることでしょう。
8. 葉牡丹(ハボタン)の歴史

現在の葉牡丹(ハボタン)が品種改良によって作られたのは江戸時代中期以降と見られています。
園芸ブームだったそうです。
縁起の良い紅白2色が好まれたといわれています。
明治時代以降は花が少ない時期、冬の園芸植物として広まりました。
そして海外にも紹介されていき、現在では世界各地で葉牡丹(ハボタン)は栽培されているのです。
9. 踊り葉牡丹(ハボタン)とは

花の少なくなる時期、寒さに耐えて綺麗に色づいた葉っぱを見せてくれる葉牡丹(ハボタン)ですが11~12月に色づいたのを楽しんで終わりと思っている人もいるかもしれません。
しかし葉牡丹(ハボタン)は面白い植物で、2~3月になると茎が伸び始めます。
草姿になり、ツリー風の見た目になります。
そして春になりますと花も咲くのです。
その花の後に切り戻しを行うとくねくねとした茎になり、その上に葉牡丹乗った「踊り葉牡丹(ハボタン)」が楽しめるのです。
4月の中頃、花が終わったら花下で切り戻してください。
そうしますと5月中旬頃にわき芽が伸びてきます。
この新芽の先に再び葉牡丹が出来上がりますのでくねくねと踊っているような見た目になるのです。
10. 葉牡丹(ハボタン)の病害虫

葉を食べてしまう、アオムシ、ヨトウムシ、コナガの幼虫がよくつきます。
2週間に一度殺虫剤を散布しましょう。
また、幼苗の時はナメクジ、アブラムシもつきますので、注意して見ておくことです。
また早目に駆除うようにしましょう。
スポンサーリンク