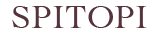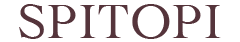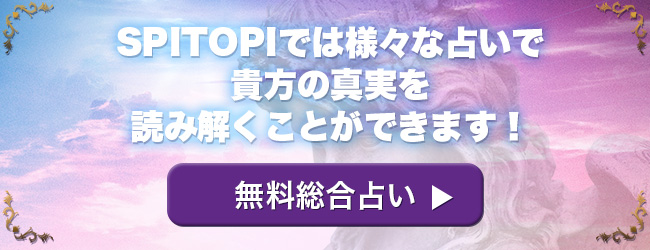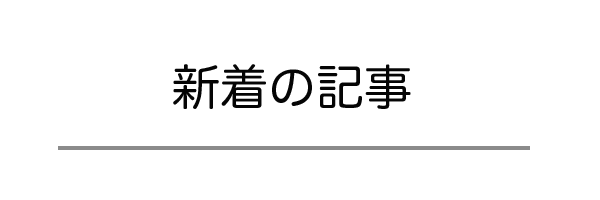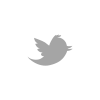有終の美は、多くの事柄において、目指すべき結果だと言えるでしょう。
しかし、それだけでいいという訳でもないのです。
- 「有終の美」の意味とは?
- 「有終の美」の読み方
- 「有終の美」の英語(解釈)
- 「有終の美」の言葉の使い方
- 「有終の美」を使った言葉と意味を解釈
- 「有終の美」を使った例文や短文(解釈)
- 「有終の美」の類義語や言い換え
- まとめ
1. 「有終の美」の意味とは?

有終の美とは、「(物事が)いい形で終わった」、「終わり方がよかった」という意味で使う言葉です。
これを「飾る」、「飾った」と使っている表現はよく見聞きするでしょう。
「有終の美だった」、「有終の美を飾った」という使い方がメインになる言葉で、それができてよかったというニュアンスが多分に含まれています。
何かをうまく終わらせた人に対して、それについて褒める意味や、賞賛する為に使うことが多いです。
2. 「有終の美」の読み方

「有終の美」は、「ゆうしゅうのび」と表現します。
読み方は特に問題ないと思いますが、この読み方だけ知っていて、漢字を当てはめる時には注意が必要です。
よく間違えられる例として、「優秀の美」としてしまうケースが見られます。
「終わり方が優秀だった」と解釈すると、この漢字表記だと思ってしまうかも知れませんが、これは完全な間違いなので気を付けてください。
意外とこの漢字で覚えてしまっている人が多いようなので、この機会にきちんと「有終の美」だと覚えておきましょう。
3. 「有終の美」の英語(解釈)

有終の美は、英語では“successful conclusion”と表記するのがいいでしょう。
これで、「結果は成功に終わった」と表現でき、「有終の美」の意味として使うことができます。
“done to perfection”でも、「完璧な形で終わった(終わらせた)」という意味になり、「有終の美」と言えなくもありませんが、この表記だと終わりだけでなく、内容まで完璧だったという意味になってしまうので、多少「有終の美」とは違う解釈となってしまいます。
「有終の美」は、あくまで終わり方だけについて語っている言葉であって、そこに辿り着くまでの内容については触れていません。
その為、「途中経過はともかく、有終の美を飾れてよかった」などという使い方もされる言葉です。
4. 「有終の美」の言葉の使い方

有終の美とは、そこまでの流れなどはともかく、「終わり方がよかった」と言いたい時に使う言葉です。
綺麗に終わったという意味なので、その後に(そこまでの流れの)何かを引きずるようなことはないという意味も込められています。
物事の終わり(終わらせ)方としては理想だと言うことができますが、冒頭にも書いたように、これだけを目指せばいいという訳でもないのは言うまでもありません。
5. 「有終の美」を使った言葉と意味を解釈

有終の美を使ったよく見る形の表現について解説していきます。
このように使われることが多い言葉なので、しっかりと覚えておきましょう。
5-1. 「有終の美を見届ける」

きちんとした終わり方ができるかどうかを見届けると言っています。
「見届けた」とすると、それができたのを確認したという意味になりますが、この「見届ける」いう形では、まだ終わってはおらず、これからそうできるかどうかというシチュエーションです。
その物事の責任者や監督する立場にある人、または傍から見ている人が使う表現です。
何かを終わらせる立場にある人(当事者)はこのようには使いません。
5-2. 「有終の美を飾る」

この表現は、何かが綺麗に終わった様子そのものです。
そう表現したい時、もしくは「飾る」を「飾ろう」(そのように終わらせよう)という意味で使うことがあります。
「このまま有終の美を飾る!」とすると、その後者の意味になると考えてください。
6. 「有終の美」を使った例文や短文(解釈)

有終の美を使った例文や短文です。
意味が1つだけしかない言葉なので、特に難しいものはないでしょう。
6-1. 「有終の美」の例文1

「最後くらいは有終の美で終わりたいものだ」
「最後くらいは」と言っていることから、途中経過はあまりよくないと推測されます。
しかし、最後くらいは綺麗に終わらせたいと言っており、その為に「有終の美」と使っています。
有終の美という形で終わったとしても、そこまでの経過に何か問題があったかも知れません。
それについてはこの言葉だけでは分からないので、別途確認が必要になります。
6-2. 「有終の美」の例文2

「有終の美とまではいかなくても、ある程度の形で締めたいと考えている」
完全に綺麗な形とまではいかなくても、恥ずかしくない程度の終わり方はさせたいと言っています。
有終の美は、物事の最後の形として理想的ですが、いつもそのようにいくとは限りません。
そこまでは難しい場合でも、変な尾を引いたり、恥ずかしくないくらいの終わり方はさせたいものです。
7. 「有終の美」の類義語や言い換え

有終の美と似た意味で使える言葉や言い変え表現です。
日本には、途中経過がどうであろうと、この「有終の美」という形で終わらせれば、そこまでの内容を問われることは少ないという文化があります。
以下に挙げていく言葉が、正にそれを表現しています。
7-1. 「終わりよければ全てよし」(おわりよければすべてよし)

すぐ上で挙げた、日本独自とも言える文化を象徴的に表しています。
終わり方さえよければ、そこまでの経過は問題ではないという意味の言葉で、そこまでに紆余曲折あったとしても、無事に(綺麗な形で)終わってよかったという時に使います。
もちろん、実際にはそれだけでいいということもないのですが、とりあえず、終わりだけでも無事だったというニュアンスで用いると考えていいでしょう。
また、途中経過については不問にする(今更問わない)という意味も含まれています。
7-2. 「大団円」(だいだんえん)

「最後を綺麗に締め括る(括った)」という意味の言葉です。
主に物語の最後に対して使われる表現で、実際の物事に対しても使えます。
「色々あったが、最後は大団円だった」と言えば、少なくとも最後は「有終の美」だったと解釈していいでしょう。
まとめ
有終の美は、理想的な終わり(終わらせ)方ですが、そこまでの経過もよかったに越したことはありません。
よって、最初からこれだけを目指すのではなく、何かの途中で後はこれくらいしか望めなくなった時に、せめて最後くらいはこのように終わらせたいと考えるものです。
有終の美は、多くの事柄において、目指すべき結果だと言えるでしょう。
しかし、それだけでいいという訳でもないのです。
1. 「有終の美」の意味とは?

有終の美とは、「(物事が)いい形で終わった」、「終わり方がよかった」という意味で使う言葉です。
これを「飾る」、「飾った」と使っている表現はよく見聞きするでしょう。
「有終の美だった」、「有終の美を飾った」という使い方がメインになる言葉で、それができてよかったというニュアンスが多分に含まれています。
何かをうまく終わらせた人に対して、それについて褒める意味や、賞賛する為に使うことが多いです。
2. 「有終の美」の読み方

「有終の美」は、「ゆうしゅうのび」と表現します。
読み方は特に問題ないと思いますが、この読み方だけ知っていて、漢字を当てはめる時には注意が必要です。
よく間違えられる例として、「優秀の美」としてしまうケースが見られます。
「終わり方が優秀だった」と解釈すると、この漢字表記だと思ってしまうかも知れませんが、これは完全な間違いなので気を付けてください。
意外とこの漢字で覚えてしまっている人が多いようなので、この機会にきちんと「有終の美」だと覚えておきましょう。
スポンサーリンク