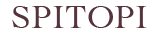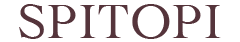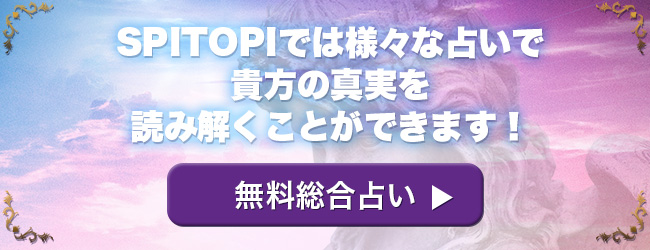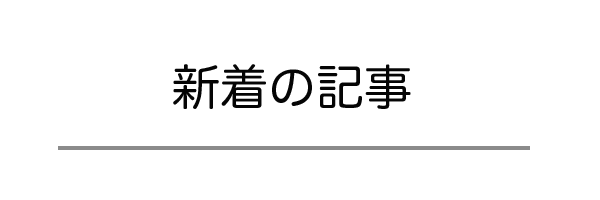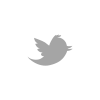日本語の中には、謙遜しながらも人を勇気づける言葉があります。
「一助」という言葉を聞くと、そのようなことをイメージしてしまいます。
- 「一助」の意味とは?
- 「一助」の類語や言い換え
- 「一助」の使い方
- 「一助」を使った例文
- 「一助」を使った言葉を解釈
- 「一助」の反対語や似た対義語
- まとめ
1. 「一助」の意味とは?

「一助」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
日常生活の中では、あまり使うことはありませんが、「一助になる」や「一助とする」と言ったように使います。
この「一助」は、最近、普通に暮らしている中では、使うシーンはそんなに多くはないのですが、ビジネスのシーンではよく使うことが多い言葉です。
使われている漢字を見れば、「何かにたいして助けること」という意味を表していそうな言葉であることが、推測できることでしょう。
何となく大まかな意味は理解できるような感じがするのですが、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか?
「一助」の「一」は音読みで「イチ・イツ」、訓読みで「ひと・ひとつ」と読みますが、ここでの「一」は、「ほんの僅か」や、「ちょっとだけ、少し」を意味します。
「助」は音読みで「ジョ」、訓読みで「たすける・たすかる・すけ」と読みます。
意味は、そのまま「たすける。援助する」ことを意味します。
この「一」と「助」の組み合わせから、「一助」の意味は「少しの助けとなる」ことや、「援助・支援の付け足し」ということになります。
言い換えると、「何かの埋め合わせ的な位置付けとして役に立つわずかな行いや足し、多少の助け、僅かな助力」を表しています。
1-1. 「一助?」の読み方

「一助」はいちじょと読みます。
「いちすけ」と読むことはありません。
特にビジネスのやり取りにおいては、注意が必要です。
2. 「一助」の類語や言い換え

「一助」と似たような意味を持つ言葉としては、次のような言葉があります。
2-1. 「力添え」

「力添え」は、「力を添えて助けること」という意味があります。
「どうか先生のお力添えをお願いいたします。」
「あなたのお力添えがなかったならここまで来ることはできなかったでしょう。」
自分1人ではできなかったことでも、力のある人の助力を受けることで、何とか乗り切れたことを言っていますね。
よく代議士に物事や頼む時に、このような言葉を使うことがないでしょうか?
2-2. 「補佐」

「人に側に付いて、その人が行っている仕事や働きを助けること」を意味しています。
「リーダーを補佐する。」
「困難なプロジェクトも、リーダーを補佐してやり遂げる。」
このような時に使う「補佐」です。
仕事をする中でも、「サブリーダー」や「課長補佐」、「部長補佐」という肩書きを持っている人がいます。
その名の通り、上職を「補佐」する役目を持っていますが、とても有能な人が「補佐」役を担うことが多いです。
2-3. 「補助」

「補助」も「一助」に似たような意味があり、「足りない力や考えを補いながら、助けること」を指しています。
「この方法は、あくまで補助的な手段と理解してください。」
「彼の困っている仕事を円滑に進めるために、補助してやって欲しい。」
このようなケースで使うことになるでしょう。
「足りない力を補い助けること」と言っても、決して微力な位置付けではないことが少なくありません。
補助とは言いながらも、かなり重要なウエートを占めていることも珍しくありません。
3. 「一助」の使い方

「一助」は、直接的や根本的な問題解決の要因として、最終着地に結びつくような助けではなく、不足している点を埋め合わせる僅かばかりの助けを表しています。
もし、自分が何か、そんなに大きな力を必用とせずに、事象やサクセス程度が大きくないヘルプをした時だけでなく、大きな助けを施した時でも、「一助」と言うことがあります。
この時の「一助」は、少し謙遜しながらの言い方になるでしょう。
日本人らしいことであって、自分から「私の助けが、大きな成果につながった。」
と言うことは、日本のビジネスシーンでは、敬遠されそうな言動です。
そのために、「一助」という言葉を使うことになります。
例えば、大きなプランニング策定や、プロジェクトを支援する立場になった時に、あまり意識せずに、"支援しに来た"、"ヘルプしに来ました"と言っても、相手の人の受け止め方は、
「偉そうに、サポートって何様?」と思われてしまうことがあるかもしれません。
せっかく支援する気持ちで、このような言動したのですが、逆に変な反感を買ってしまうことさえありえるのです。
そのようなことにならないために、謙虚な姿勢を示す言葉の「一助」を用いるのとで、周囲からのあつれきをかわすことができるでしょう。
4. 「一助」を使った例文

では、「一助」を使う例文では、どのような文を見ることができるでしょう?
「新しく作成したデータとサンプリングが、今回の計画を進める上で、多くの人達のご理解の得られる一助となれば幸いです。」
このようなケースでの、「一助」は、とても大きいヘルプとなっているはずです。
この「一助」が、壮大な計画を推し進める大きな起爆剤ともなっていることがあります。
「廃墟と化した町の地域活性化の一助となるために、新しい観点で特産品に関連したイベントを開催するのはいかがでしょうか?」
地方の小さな町になると、高齢化や若い人が都会に移り住むなどの人口流出が問題となっています。
町の活性化という意味で、このようなイベントが催されることもありますね。
この他にも、「一助」は、色々なケースで使われます。
「このプロジェクト成功の一助となるべく、スキルの高い経験豊富なメンバーを集めました。」
「提案するシステムは、御社の業務効率化の一助となりえます。」
このような使われ方もあります。
5. 「一助」を使った言葉を解釈

「一助」は、他の言葉と組み合わせて使うことがあります。
5-1. 「大きな一助」

「この技術は、新製品誕生の大きな一助となることは間違いない。
これによって、わが社も新たな市場に展開することができます。」
「一助」とは、あくまで補完的的な力を意味しているのですが、このように流れを大きく変えていく結果に結び付くこともあります。
前述のように「一助」を謙遜して使うことがありますが、かなり大きな影響力を及ぼすこともあります。
5-2. 「一助を担う」

「一助を担う」も、ある動きや目的を達成するために、力の一部の役目を果たすことを意味にしています。
「一助となる」や「一端を担う」というような表現もできます。
「彼は、私達クラブチームの連勝の一助を担っている」というような使われ方になるでしょう。
6. 「一助」の反対語や似た対義語

「一助」の反対語とは、「自立」という言葉が挙げられるでしょう。
自立の意味は、「自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと」となります。
まさに「一助」と対局的な言葉になります。
「彼は、とても自立しているので、何でもそつなくこなせる。」
このようなな例え方になります。
まとめ

「一助」には、「ヘルプ」(助け。援助)や「応援」(助け救うこと)という意味もあります。
ビジネスの世界に身を置く人は、特に「一助」という言葉を実際に体験した人がおおいのではないでしょうか?
1つの仕事でも、自分1人ではやり遂げることや、達成することはできません。
自分1人でやっていることでも、必ず協力者や支援者がいるものです。
このようなことから、ビジネスで仕事を進めていく中では、周りの人をヘルプするくらいの気持ちをもって、オフィスにいることが必要なのです。
日本語の中には、謙遜しながらも人を勇気づける言葉があります。
「一助」という言葉を聞くと、そのようなことをイメージしてしまいます。
1. 「一助」の意味とは?

「一助」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
日常生活の中では、あまり使うことはありませんが、「一助になる」や「一助とする」と言ったように使います。
この「一助」は、最近、普通に暮らしている中では、使うシーンはそんなに多くはないのですが、ビジネスのシーンではよく使うことが多い言葉です。
使われている漢字を見れば、「何かにたいして助けること」という意味を表していそうな言葉であることが、推測できることでしょう。
何となく大まかな意味は理解できるような感じがするのですが、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか?
「一助」の「一」は音読みで「イチ・イツ」、訓読みで「ひと・ひとつ」と読みますが、ここでの「一」は、「ほんの僅か」や、「ちょっとだけ、少し」を意味します。
「助」は音読みで「ジョ」、訓読みで「たすける・たすかる・すけ」と読みます。
意味は、そのまま「たすける。援助する」ことを意味します。
この「一」と「助」の組み合わせから、「一助」の意味は「少しの助けとなる」ことや、「援助・支援の付け足し」ということになります。
言い換えると、「何かの埋め合わせ的な位置付けとして役に立つわずかな行いや足し、多少の助け、僅かな助力」を表しています。
1-1. 「一助?」の読み方

「一助」はいちじょと読みます。
「いちすけ」と読むことはありません。
特にビジネスのやり取りにおいては、注意が必要です。
2. 「一助」の類語や言い換え

「一助」と似たような意味を持つ言葉としては、次のような言葉があります。
2-1. 「力添え」

「力添え」は、「力を添えて助けること」という意味があります。
「どうか先生のお力添えをお願いいたします。」
「あなたのお力添えがなかったならここまで来ることはできなかったでしょう。」
自分1人ではできなかったことでも、力のある人の助力を受けることで、何とか乗り切れたことを言っていますね。
よく代議士に物事や頼む時に、このような言葉を使うことがないでしょうか?
2-2. 「補佐」

「人に側に付いて、その人が行っている仕事や働きを助けること」を意味しています。
「リーダーを補佐する。」
「困難なプロジェクトも、リーダーを補佐してやり遂げる。」
このような時に使う「補佐」です。
仕事をする中でも、「サブリーダー」や「課長補佐」、「部長補佐」という肩書きを持っている人がいます。
その名の通り、上職を「補佐」する役目を持っていますが、とても有能な人が「補佐」役を担うことが多いです。
2-3. 「補助」

「補助」も「一助」に似たような意味があり、「足りない力や考えを補いながら、助けること」を指しています。
「この方法は、あくまで補助的な手段と理解してください。」
「彼の困っている仕事を円滑に進めるために、補助してやって欲しい。」
このようなケースで使うことになるでしょう。
「足りない力を補い助けること」と言っても、決して微力な位置付けではないことが少なくありません。
補助とは言いながらも、かなり重要なウエートを占めていることも珍しくありません。
スポンサーリンク