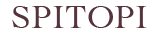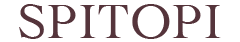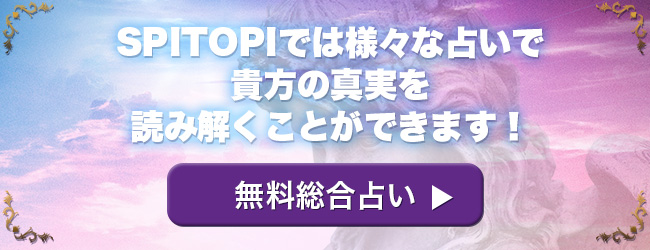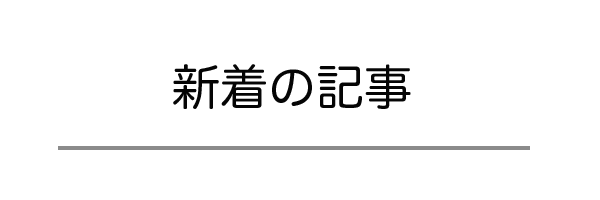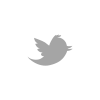物事に対し、いつまでも食らいついて諦めなかったり、しがみつく人に出会った事はないでしょうか。
状況によってはそうする事が大切な場合もありますし、ないと駄目な場合もありますが、タイミング次第では迷惑になる場合も多々あります。
そのような人の事や行為を「食い下がる」と言いますが、この「食い下がる」の意味や、心理にはどのような意味があるのでしょうか。
- 「食い下がる」の意味とは?
- 「食い下がる」の類語
- 「食い下がる」心理
- 「食い下がる」の使い方
- 「食い下がる」を使った例文
- 「食い下がる」の語源
- 「食い下がる」の英語
- 「食い下がる」の対義語
- まとめ
1. 「食い下がる」の意味とは?

目的や欲しいもの、意思や行動など全てにおいて自分が納得したり自分のものになるまでは断固として喰いついて離れず、いつまでもしがみついて離れない事をいいます。
粘り強くどんな相手であっても立ち向かい、執念深く追求し途中で妥協する事がない事を表します。
また、ライバルなどに差をつけられないように、引けを取らないようにする時にも「食い下がる」という表現をする事があります。
よく食い下がるの"下がる"を、引き下がるの"下がる"と同じ意味だと勘違いして、真逆の意味を記憶している方がいますが、食い下がるの"下がる"は、人の行動としての"下がる"ではなく、「物がぶら下がる」「状況として何かがぶら下がっている」といった客観的な状況を表す状態から生まれた言葉なので、引き下がるとの意味は全く違うものになります。
食い下がるの"下がる"は「控える」や「諦める」といった人の動作に対する意味ではありません。
2. 「食い下がる」の類語

2-1. しつこい

しつこいとは、状況や行動だけに限らず五感に対しても使う表現になります。
特に味覚はしつこさやくどさなどを感じやすく、あまり好ましくない場合に使います。
また物事に必要以上に拘ったり、何度も自分の都合だけしか考えず、空気を読む事もなく行動する人にも使います。
つきまとって執念深い人物や行為、発言などをする事をしつこいというので、しつこいと言われるという事は嫌がられている可能性が高いでしょう。
2-2. 執拗

簡単には引き下がらず、いつまでも自分の意見に拘ったり粘ることをいいますが、あまりいいイメージはなく、度を超えた拘りや、態度、行動の時に使う事が多い言葉だと言えるでしょう。
「執拗な」「執拗に」といった使い方をし、状況によっては周りにはその執拗さが異様な光景に映っていることも少なくありません。
2-3. しぶとい

簡単には引き下がらず、どんな困難があってもなかなかその場から離れず、立ち去らず渋る事をいいます。
しぶといという言葉自体は良くも悪くも使われ、最後まで諦めずに全力を尽くして未来を切り開いていく人の表現に使われます。
ですが一方では、自己都合や欲だけの為に空気を読まず、立場や状況を譲る事なくしがみつく人を表す際にも使われます。
早く退散して欲しい物や人にも使うので、どちらかというとあまりいいイメージを持たれる言葉ではないかもしれまん。
3. 「食い下がる」心理

3-1. 我が強い

食い下がらなければいけない状態とは、相手が受け入れ態勢ではないからする行為になるので、気が小さかったり、相手の気持ちを考え行動する人には無理かもしれません。
やはり我が強く、自分本位で自己中心ではないと食い下がろうと思わないと思いますし、できないでしょう。
目的を達成する為には手段を選ばない傾向があり、相手がどう思うが嫌がろうが、場合によっては荒い手法を使ってまでも自分の望む結果に事を運ぼうとします。
他人の迷惑も考えない上に自分の事しか考えていないので、食い下がる事ができるわけです。
もちろん食い下がられた相手からすれば、鬱陶しく迷惑で不愉快この上ないと思いますが、食い下がる人は、自分の考えが中心なので物事を決めつけて行動しますし、周りの意見など聞かず思い込みで突進していきます。
つまり一度決めつけたことを見直したり、撤回するような柔軟な思考を持ち合わせておらず、考え直すような余裕や能力を持ち合わせていないといえるでしょう。
何かを貫く為には我を強く持つ事も必要ではありますが、他人に迷惑を掛けてまで貫いてもいい「我」などありませんし、迷惑にも種類があります。
そもそも迷惑を掛けずに自分を通す事が大切であり、値打ちがある事なのだと学ばなければいけません。
3-2. 自信がない

根本的に食い下がる人は、それがなくなったら困るという強い思いを持っているから食い下がる訳です。
何がなんでも手に入れて自分の欲を満たしたいと思っています。
つまり逆に考えると、それがないとメンタルバランスが保てず余裕がなくなる事を表しています。
表面的に見れば気が強くしつこいとしか見えませんが、心理的には自信がなく不安を打ち消す為にしがみ付いたり、食い下がっているとも言えるのです。
例えば何度もしつこくメールや電話をしてきたり、執拗に会おうとしてきたり、何回断っても誘ってきたりと、そんな事をされた経験がある方も沢山いると思いますが、このような行動をする人は、実は相手の事を考えなければいけないという思考の余裕がないという事であり、とにかく自分が不安になりたくないだけなので、異常なまでに固執してくるのです。
太陽と北風の北風ように、無理に何かをさせようとすると人は心を閉ざしてしまいます。
不審に思いますし、不信が募ります。
結局不安や自信のなさから他人を不安にさせる事になるのです。
3-3. 元々粘着質

食い下がっているものの内容にもよりますが、相手の気持ちなど考えずに食い下がる程、その事に対して執着するのですから、相当粘着質な性格だと言えるのではないでしょうか。
またこのようなタイプは過去に傷付いた事や、自分がされた嫌な事などを忘れることはありません。
ずっと根に持ち常にその事を考えています。
ですから周りからすると、どうでもいいような事やすぐに忘れてしまうような事にも時間を掛けてネチネチ文句を言ったり、クドクド説教をしたりします。
その割に自分がやった事や不愉快にさせている事に対しては無頓着で気付く事すらありません。
食い下がるのは殆どの場合が自分のプライドを保つ為なので、ネガティブな内容でもポジティブな内容でも異常な執着心を燃やしてはしつこく追いかけるでしょう。
3-4. 独占欲が強い

自分の思うようにしたい、手に入れて離したくないのは独占欲が強いからであり、常に監視や管理をし支配下に置いておきたいと思っているから無理矢理食い下がるのです。
自信がなく余裕がない事にも繋がりますが、独占したいのは、他に取られてしまう事が怖いから縛り付けたいと思うので、気持ちに余裕があり、自分に自信があれば例え取られても仕方ないで済ませられますし、また取り返せばいいと考えるはずです。
もっといえば、取られるくらい自分に力がなかったんだと思うものです。
執着したところで他人を変える事は出来ないと分かっているので自分の事を磨き高めようとするでしょう。
ですが独占欲が強いと、他人をどうにかしよう、他人に動いて貰おうとします。
「食い下がっているのだから折れろ」と言わんばかりに自分のやり方や感情に従うようにさせます。
要は他力本願なのにも関わらず、それには気付かず自力だと思っているので相手の気持ちなど御構いなしになるのです。
この独占欲が強い程、自分の周りから人が離れたり、願望が達成されない事に対しての恐怖心が強くなるのですが、それを克服する手段やノウハウは持っていない事が多いでしょう。
3-5. 失敗や手に入らなかった事を「悪」だと思っている
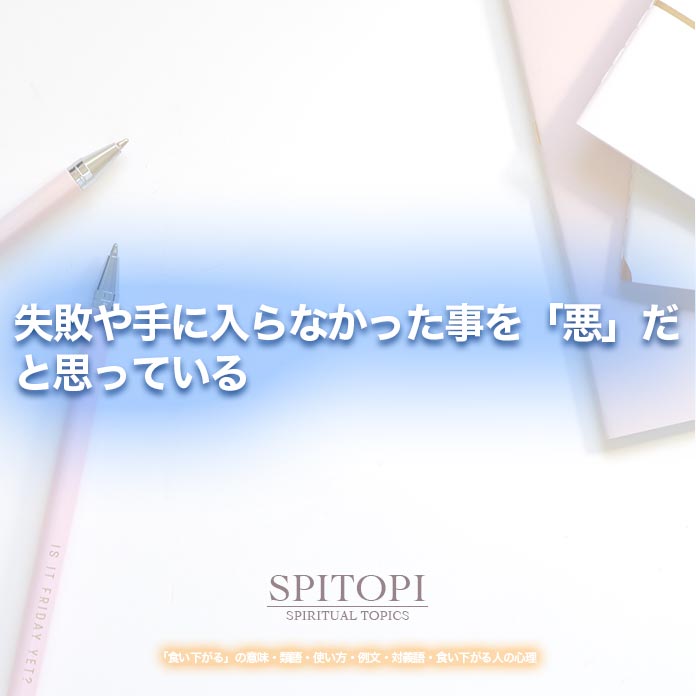
人間は完璧ではありません。
失敗したりうまくいかなかったり、挫折して悔しい思いをする事もあるものです。
だからこそ変化して前進したり、新しい気付きをし、そこから学んだりバネにして飛躍していくのです。
ですから躓く事は決して悪い事ではないのですが、食い下がり、執拗に粘る人は失敗や思い通りにならない事を「悪」だと思っているところがあります。
考え方がネガティブで一方通行のため、常に手に入れなければならないと思っていて、目的を達成しなければいけないと思っています。
おまけにあれ程食い下がり粘ったのだから絶対に支配したいと思っていますし、他に譲りたくないと思っています。
つまりその目的というよりは、食い下がり粘った自分の"労力"に対して粘着したり、執着をしているのだといえるでしょう。
その労力に対する対価を貰うことが出来ないなんて何の意味もなく、行動全てが無駄になってしまうと考えるのです。
ですから毎回食い下がる事には執念を燃やしますが、だからといって何かを学習したり、方法や手段を工夫する事はありません。
なのでいつまでも北風方式で無理矢理ぶら下がり力づくで他人を自分の方に向かせようとするのです。
失敗が嫌な割に自分の方法が『失敗法』という事に気付いていないのが一番の欠点なのですが、その事に気付く事はないかもしれません。
3-6. 孤独が怖い

食い下がる人は独占欲が強く自信がないと述べましたが、心理的な要素として全てに言えることは、とにかく一人置いてけぼりになったり、独りぼっちになる事が嫌で仕方なく、怖くてたまらない人が多いという事です。
さみしい思いや孤独を異常に嫌がり、何とかして繋ぎ止めようとして必死になり束縛したりしがみついて食い下がります。
ですが物理的に一人にならないようにしているだけであり、本質的な部分での繋がりを求めているわけではありません。
正確に言うとそうしたくてもやり方が分からず出来ないのかもしれません。
冷静に現状をみたりタイミングを計ったり、他人の感情を考慮したり、空気を読み引き際を見極めるという事ができないので、どうしてもうわべの付き合いになってしまうのです。
最も嫌な事を自ら引き寄せてしまっているわけですが、食い下がる人というのは、何につけても潔く諦めることができません。
いつまでもひきずりこだわり続けます。
感情を優先させ理性的な動きができない人は結局自分を満たす事ができない場合が多いのです。
3-7. 自分を否定したくない

自分が思っている事が正しく、自分の考えが中心なので物事を決めつけて行動するので、周りの意見など聞くことがありません。
ですから持っている知識や情報は全て自分が集めたものになりバリエーションがありません。
アウトプットする事がないので、視野が狭く、発想が偏っている事が多いといえるでしょう。
他の人がやり方を変え、手を替え品を替え上手くいくように努力しているのにも関わらず、いつまでもただ食い下がるといった手段しかない為、なかなか前進せず挙げ句の果てに嫌がられてしまうのです。
学習をしない、できない理由にも色々あり、中には障害が原因の場合もありますが、多くの場合は他人の意見を取り入れたり引き下がる事が、自分を否定する事だと思いこんでいるからではないでしょうか。
柔軟性がなく余裕がないという事は、世間を知らないという事です。
客観視して自分をみる事もないですし、見えている世界は本当に目の前の狭い範囲なのですが、自分の目に映るものが全てな為変えようとはしません。
何かに食い下がっている自分を想像するとあまりかっこ良くなく恥ずかしいものですが、このようなタイプの人はそんな発想もないですし、他に手段もないのでずっと食い下がる方法を取っていくでしょう。
4. 「食い下がる」の使い方

何かを頑張りたい時や譲りたくない時、負けたくない時などに使います。
また一筋の望みをかけてチャレンジをする時や、どうしても手に入れたいものがある時に相手に対して粘る際にも使います。
5. 「食い下がる」を使った例文

努力や頑張りが認められて、いい方向に結果が向かう場合と、しつこいと思われて悪く転がる場合があるので、食い下がるという言葉は、状況や空気で本当に印象を変えてしまう繊細な言葉だと言えるでしょう。
いくつかパターンを挙げるので比べてみましょう。
- 「何度も却下されたにも関わらず、負けじと食い下がった結果、話だけは聞いてもらえる事になった」
- 「門前払いをされたのに、それでも彼は食い下がって門の前にい続けた」
- 「食い下がりすぎて印象が悪くなってしまったので、名誉挽回したい」
- 「下手に食い下がってもうまくいかないと分かっているので一度引きさがろうと思う」
6. 「食い下がる」の語源

肉食動物は獲物を見つけ仕留めたあと、口で獲物を咥えて絶対に離しません。
その見た目は口から獲物が垂れ下がっている状態に見える事から、執拗に離さない事を「噛んで離さないもの」「食べるまで離さない」から「食い下がる」というようになったと言われています。
7. 「食い下がる」の英語

「食い下がる」と一言で言っても非常に繊細なので、英語で表すと幾つものパターンになります。
どういった食い下がり方かでも表現が変わります。
7-1. I persist in a resisting really persistentl

本当にしつこく食い下がるので大嫌いだ。
7-2. Since persisting in an attack many time

何度も食い下がっては同じ事を言う
7-3. I kept declinin
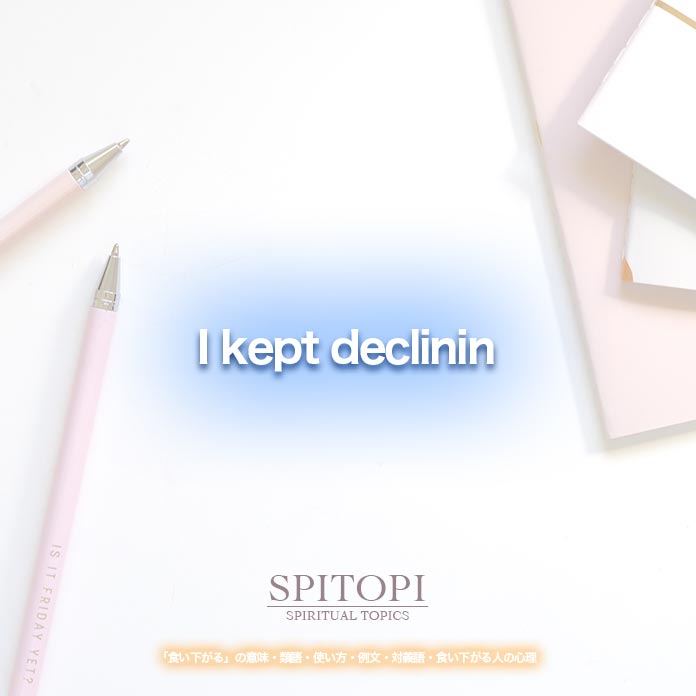
断り続けたけど諦めなくてよかった
8. 「食い下がる」の対義語

8-1. 引き下がる

狙っていたものや目的、目標から静かに手を引く事をいいます。
またその場から退いたり、自分の主張を引っ込めたり、自分の実力や立場、状況を理解して身を引く事をいいます。
先程も説明をしましたが、引き下がるの"下がる"と食い下がるの"下がる"は意味が違います。
引き下がるの"下がる"は身を引いたり、ある意味『立場をわきまえる』という意味でもあります。
ドラマなどで人に向かって「下がれ」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、そのように人の行動を表現する言葉になります。
8-2. 諦める

思っていた事や望んでいた事を綺麗さっぱり断念する事をいいます。
諦めるの対義語に粘るがありますが、食い下がるの意味の中には粘るという意味もあるので、反対を表す際の表現としては適切ではないでしょうか。
8-3. 身を引く

自らの意思でその場から立ち去ったり、その状態から抜け出す事を言います。
先の事を考えている場合に使われる事が多く、ポジティブで前向きなイメージが強い表現だと言えるでしょう。
まとめ

人は熱意や情熱がある程、なかなか諦めきれないものです。
「継続は力なり」、「夢を諦めるな」、「やめるのも勇気」などの言葉がありますが、では一体どうすればいいのかと思ってしまいますが結論から言えば、全て正解ですし全てできればいう事ないでしょう。
ですがなかなか難しく、強い精神力がいる事なので簡単ではありません。
継続をしないと夢は叶いませんが、無鉄砲に続けていても意味がありません。
食い下がるだけであれば誰でもできる事であり単純にしつこいだけで終わってしまう事も多いでしょう。
状況判断やタイミングを上手に考えながら引き際もまでしっかり計算しておく事が、食い下がる事に意味を持たせますし、メリハリが出てその物事自体にも価値が出てくるのではないでしょうか。
物事に対し、いつまでも食らいついて諦めなかったり、しがみつく人に出会った事はないでしょうか。
状況によってはそうする事が大切な場合もありますし、ないと駄目な場合もありますが、タイミング次第では迷惑になる場合も多々あります。
そのような人の事や行為を「食い下がる」と言いますが、この「食い下がる」の意味や、心理にはどのような意味があるのでしょうか。
1. 「食い下がる」の意味とは?

目的や欲しいもの、意思や行動など全てにおいて自分が納得したり自分のものになるまでは断固として喰いついて離れず、いつまでもしがみついて離れない事をいいます。
粘り強くどんな相手であっても立ち向かい、執念深く追求し途中で妥協する事がない事を表します。
また、ライバルなどに差をつけられないように、引けを取らないようにする時にも「食い下がる」という表現をする事があります。
よく食い下がるの"下がる"を、引き下がるの"下がる"と同じ意味だと勘違いして、真逆の意味を記憶している方がいますが、食い下がるの"下がる"は、人の行動としての"下がる"ではなく、「物がぶら下がる」「状況として何かがぶら下がっている」といった客観的な状況を表す状態から生まれた言葉なので、引き下がるとの意味は全く違うものになります。
食い下がるの"下がる"は「控える」や「諦める」といった人の動作に対する意味ではありません。
2. 「食い下がる」の類語

2-1. しつこい

しつこいとは、状況や行動だけに限らず五感に対しても使う表現になります。
特に味覚はしつこさやくどさなどを感じやすく、あまり好ましくない場合に使います。
また物事に必要以上に拘ったり、何度も自分の都合だけしか考えず、空気を読む事もなく行動する人にも使います。
つきまとって執念深い人物や行為、発言などをする事をしつこいというので、しつこいと言われるという事は嫌がられている可能性が高いでしょう。
2-2. 執拗

簡単には引き下がらず、いつまでも自分の意見に拘ったり粘ることをいいますが、あまりいいイメージはなく、度を超えた拘りや、態度、行動の時に使う事が多い言葉だと言えるでしょう。
「執拗な」「執拗に」といった使い方をし、状況によっては周りにはその執拗さが異様な光景に映っていることも少なくありません。
2-3. しぶとい

簡単には引き下がらず、どんな困難があってもなかなかその場から離れず、立ち去らず渋る事をいいます。
しぶといという言葉自体は良くも悪くも使われ、最後まで諦めずに全力を尽くして未来を切り開いていく人の表現に使われます。
ですが一方では、自己都合や欲だけの為に空気を読まず、立場や状況を譲る事なくしがみつく人を表す際にも使われます。
早く退散して欲しい物や人にも使うので、どちらかというとあまりいいイメージを持たれる言葉ではないかもしれまん。
スポンサーリンク