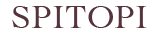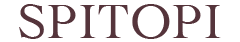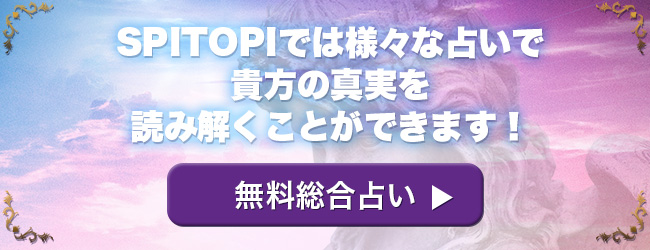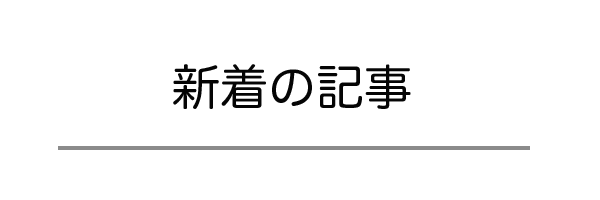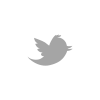「インスパイア」はよく耳にする言葉です。
今さら聞けないメジャーな言葉になりつつあるので、知らない人は正しい意味を覚えておきましょう。
- 「インスパイア」の意味とは?
- 「インスパイア」の類語
- 「インスパイア」の対義語
- 「インスパイア」の使い方
- 「インスパイア」を使った例文
- 「インスパイア」を使った言葉
- 「インスパイア」の英語
- 「インスパイア」と「パクリ」の違い
- まとめ
1. 「インスパイア」の意味とは?

「インスパイア」は正しくは「inspire」と英語で表記します。
もともとの意味は、吸収するという意味の「in」と息という意味の「spire」から出来ている言葉です。
そして、この2つの言葉が組み合わさると、「インスパイア」には「刺激を受ける」「考え方や思想などを吹き込まれる」といった意味になります。
単なる言葉のイメージですが、「インスパイア」は英語の意味を直訳すると、「息が吹き込まれた」という意味になります。
今まで生気のなかったものが、まるで生き生きと動き出すかのように生まれ変わるようなイメージを持たせてくれる言葉です。
非常にポジティブで格好良い言葉です。
この「インスパイア」の持つ言葉のポジティブさ、そして格好良さから、日本では、コマーシャルやアーティストの楽曲名、車の名前などにも起用されています。
非常に心が前向きになる良い言葉です。
日常生活においていえば、「インスパイア」される瞬間とはどのようなときなのでしょう。
例えば、誰かの生き方を見て格好良いと思い、自分もこうなりたいと思った瞬間などでしょうか。
あるいは何を見て、良いアイディアを閃いた瞬間でしょうか。
日常生活の中でも、周りの人や物事を見て、良い刺激を受けることがあります。
その自分の心に受けた刺激こそが、その人にとっての「インスパイア」です。
2. 「インスパイア」の類語

「インスパイア」の類語についてみていきましょう。
2-1. 影響力(えいきょうりょく)

「インスパイア」の類語として、「影響力」が挙げられます。
「影響力」とは「他に働きかけ、考えや動きを変えさせるような力」のことです。
「インスパイア」にも、他から受けた刺激に反応して、考えや動きに変化が生じるという意味があるので、この2つの言葉は類語として考えられます。
しかし、完全なる類語ではありません。
「インスパイア」の場合は、今まで生気のなかったものが息づいて、イキイキしだす意味を持ちます。
それは、非常にポジティブなもので、インスパイアを受けた人は希望と夢を胸に抱くような、明るいイメージを持つ言葉です。
それに比べると、「影響力」はポジティブなイメージだけでなく、マイナスなイメージも含んでいます。
「悪い友達の影響力が強すぎて、とうとう彼も不良になってしまった」
などのように、悪い意味でも使われています。
ここに、「影響力」と「インスパイア」の違いがあります。
いくつか例文を挙げていきましょう。
まずは良い意味での影響力から。
「クラスにおける彼女の影響力はとてもすごい。彼女が着れば、可愛いとはやし立て、みんな真似をしようとする」
(クラスにおける彼女の周りにもたらす変化はすごい。彼女が着れば、可愛いとはやし立て、みんな真似をしようとする。)
次いで悪い意味での影響力の例文。
「この影響力は計り知れないぞ。このままだと、この町全体が死滅してしまう」
(この周りにもたらす変化は計り知れないぞ。このままだと、この町全体が死滅してしまう。)
このように、「影響力」は悪い意味でも良い意味でも使われています。
2-2. 生気が宿る(せいきがやどる)
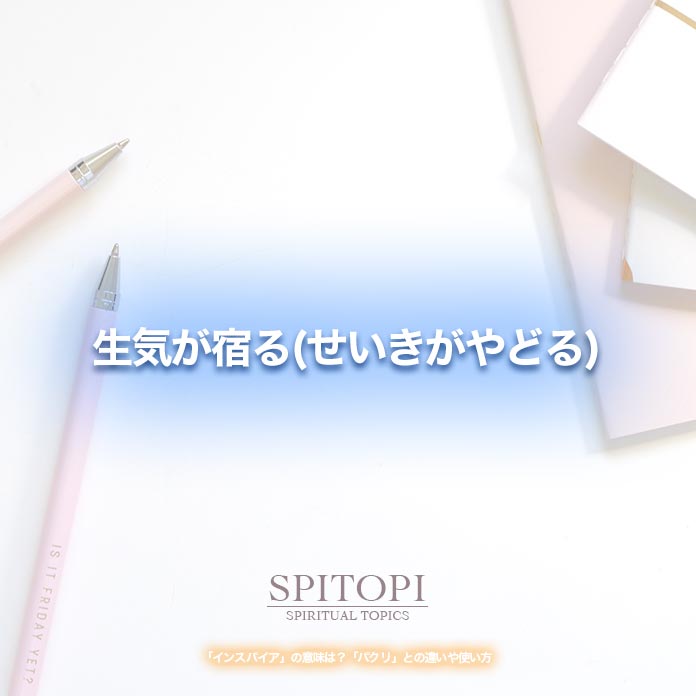
生気が宿るとは、「活気が自分にとどまる」という意味です。
「生気が宿る」は「生気」と「宿る」の2つの言葉に分けることができます。
ぞれぞれの意味としては、「生気」が「いきいきとした感じ」「活気」を表し、「宿る」が「その場所にとどまること」を表しています。
「生気」という言葉も「宿る」という言葉も、非常に前向きで良いイメージを持つ言葉です。
「生気」には文字通り「生きる気力」を、「宿る」には妊娠することを「子が宿る」と表現するように良い縁起の良さを感じる日本語です。
この点から、「インスパイア」が持つイメージと非常に類似しているといえます。
また、「生気が宿る」には、「元気になる」「生気が戻る」「顔色がよくなる」「血の気がさす」などの意味があります。
これらの意味も、非常に前向きで良い状態に変化することを表す意味です。
この意味からも「生気が宿る」の言葉は、良い影響を表す「インスパイア」と非常に似ていると言えます。
例文としては、「彼の表情は暗かったが、その吉報を聞いた途端、生気が宿ったように目をランランと輝かせた」
(彼の表情は暗かったが、その吉報を聞いた途端、希望が宿り、目をランランと輝かせた。)
「まるで人形のように心のこもった言葉をかけられない人だったけど、今となっては嘘のようだ。まるで生気が宿ったかのように感情表現が豊かになった」
(まるで人形のように心のこもった言葉をかけられない人だったけど、今となっては嘘のようだ。元気に明るくなり、感情表現が豊かになった。)
などが挙げられます。
何かの影響を受けて、良い方向へと変わっていく姿を伺うことができる表現です。
3. 「インスパイア」の対義語

「インスパイア」の対義語についてみていきましょう。
3-1. 「影を落とす」(かげをおとす)
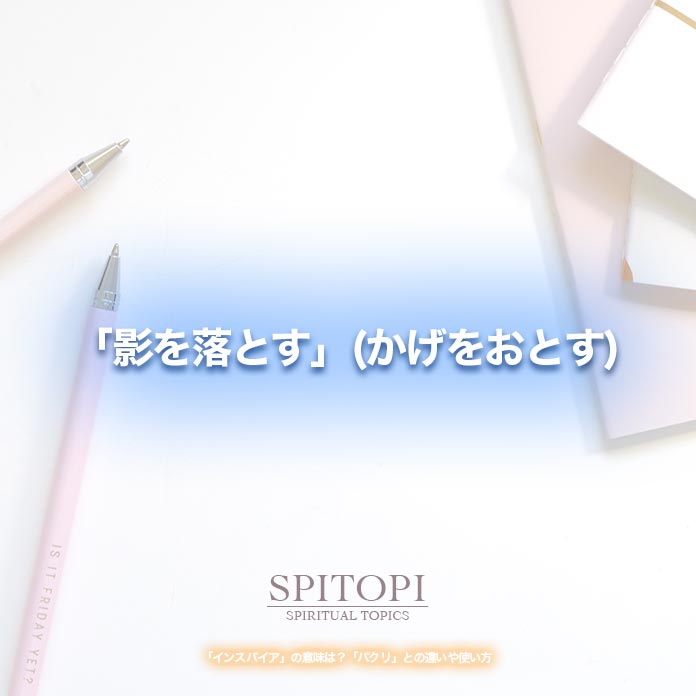
「インスパイア」の対義語として、「影を落とす」という言葉が挙げられます。
「影を落とす」には、そのままの直訳で「自らの影を他の物の上に現す」という意味もありますが、「不幸・不吉・不安などをもたらす」という意味もあります。
そして、「インスパイア」の対義語として考えられる意味は、後者の「不幸・不吉・不安などをもたらす」という意味です。
「インスパイア」が良い意味での刺激を表す言葉であり、非常に前向きな感情を捉えることができる表現であるため、その点においても非常にネガティブさを表す「影を落とす」は、対義語として適切だといえるでしょう。
「影を落とす」を言い換えるとすれば、「悪い連鎖を引き起こした」「悪い影響をもたらした」「不幸を呼び込んだ」「不吉なことのはじまりだった」「悪い方向へと転じることになった」などです。
あまり良い意味で使われていない言葉であることが分かります。
例文としては、「今回の事件は、子供たちに暗い影を落とした」
(今回の事件は、子供たちを落ち込ませ、悪い影響をもたらした。)
「彼は良かれと思ってしたことだったが、この行動は後に大きな影を落とすことになっていった」
(彼は良かれと思ってしたことだったが、この行動は後に大きな不幸を呼ぶことになっていった。)
4. 「インスパイア」の使い方

「インスパイア」の使い方についてみていきましょう。
「インスパイア」を使うときは以下の3つの点に気を付けましょう。
まず一つ目は、「インスパイア」は良い影響をもたらすときに使うものであるということ。
そのため、「悪い影響を受けた」「それをきっかけに不幸になった」「希望を失った」「評判を落とした」などという悪い意味が込められていません。
「希望をもたらした」「良い刺激を受けた」「良いアイディアが閃いた」などのポジティブな意味をもつ言葉となっています。
「インスパイア」は英語の直訳だと「息が吹き込まれる」という、元気になる意味合いがあるので、このような意味になるのも納得です。
「インスパイア」された人は、良い影響を受けたことで、さぞ、心が充実し、満足していることでしょう。
二つ目ですが、使うときに気を付けてほしいことは「特定の物事を指す」言葉であることです。
誰かの考えや思想、特定のドラマや芸術、音楽などに影響を受けたことを「インスパイアされた」などと表現します。
そのため、「世界中の想いが届き、これからの歴史に影響を及ぼすだろう」
などの表現を「世界中の想いが届き、これからの歴史にインスパイアされるだろう」などとは使いません。
あくまで、「インスパイア」するのは特定のものであり、世界中の想いなどといった範囲の広いものではありません。
「インスパイア」する特定のものとして挙げられるのは、「彼や彼女といった特定の人」「特定の小説」「特定の映画やドラマ」「特定のアーティストの音楽作品」などです。
三つ目は、英語で使うときと日本語で使うときの使い方に違いがあるという点です。
英語においても日本語においても意味は同じですが、使い方が少し異なります。
使い方にどのような違いがあるのか、詳しくみていきましょう。
日本語において「インスパイア」という言葉を使うときは、一般的に主語は「インスパイア」される側です。
例えば、日本語においてはこのような使い方をされています。
「彼の文学はシェイクスピアにインスパイアを受けている」
(彼の文学はシェイクスピアに影響を受けている。)
「私はあなたの舞台をみてインスパイアを受けました」
(私はあなたの舞台を見て良い刺激を受けました。)
主語となる「彼の文学」も「私」も、すべて「インスパイアされる側」を主語においています。
しかし、これが英語になると、「インスパイア」する側が主語となります。
英語では「インスパイア」する側、日本語では「インスパイア」される側が主語にしやすい傾向があることを覚えておきましょう。
5. 「インスパイア」を使った例文

「インスパイア」を使った例文をみていきましょう。
5-1. 例文1

「彼の伝記を読んでインスパイアを受け、同じような志で勉学に励むことを誓った」
(彼の伝記を読んで影響を受け、同じような志で勉学に励むことを誓った。)
彼の伝記を読んだ人が、彼のようになりたいと、彼のような志を持って勉学に励む姿を表しています。
勉学に励むという行為は、いやいや励むといったマイナスな感情ではなく、自ら進んで勉学に励むというプラスの感情でしかありません。
彼に良い影響を受けて、彼をお手本にして勉学に励む姿を表しています。
5-2. 例文2

「彼女がこれまでインスパイアを受けてきた作品は数知れない。
だからこそ、あの生き生きとした作品を世に出すことができるのであろう」
(彼女がこれまで刺激を受けてきた作品は数知れない。
だからこそ、あの生き生きとした作品を世に出すことができるのであろう。)
彼女が様々な作品に刺激を受け、良い作品づくりをしている様子がみてとれます。
「インスパイア」を受けた、様々な作品を通して、それが彼女に良い結果を導いているのが分かります。
6. 「インスパイア」を使った言葉

「インスパイア」を使った言葉についてみていきましょう。
6-1. 「インスパイアされる」

「インスパイア」の言葉を使うとき、一番日本で使われている使い方は「インスパイアされる」です。
「インスパイアされる」は「触発される」「刺激を受ける」「影響を受ける」という意味になります。
ある特定の思想や人物、芸術などから「触発される」「刺激を受ける」「影響を受ける」といった状況に陥ったときに「インスパイアされた」と表現します。
例文としていくつか挙げてみます。
「彼は彼女の生き方にインスパイアされる」
「この小説にインスパイアされ、作り上げた作品がこれです」
それでは、逆にインスパイアする側として表現する場合はどのような表現になるのでしょう。
インスパイアを与える側に立つときは、「インスパイアする」と表現します。
例文をいくつか挙げてみます。
「彼の生き方は、彼の弟子たちにインスパイアした」
「私のこの作品は多くのファンをインスパイアするだろう」
「インスパイアする」という表現も使えないことはないですが、日本において一番主流の使い方は「インスパイアされる」方です。
「インスパイアする」という表現はあまり耳にすることはないでしょう。
6-2. 「インスパイアを受ける」

「インスパイア」という言葉を使うとき、「インスパイアを受ける」という表現も、よく使われている表現です。
意味としては、「インスパイアされる」と同等の意味を持ち、こちらも「触発される」「刺激を受ける」「影響を受ける」という意味があります。
つまり、「インスパイアを受ける」も「インスパイアされる」も同じ意味です。
使い方としては次のような文章になります。
いくつか例文を挙げてみます。
「彼の考えにインスパイアを受け、この職業を選んだ」
「彼女が力強い意思で行動する姿にインスパイアを受け、私も今まで以上に活発に行動するようになった」
それでは、逆にインスパイアを受けさせる側に立つ時は、どのような表現になるのでしょう。
表現としては「与える」という言葉が適切かもしれません。
例文をいくつか挙げてみます。
「彼は多くの子供たちにインスパイアを与えた」
「彼女のデザインは多くのデザイナーにインスパイアを与えた」
しかし、「インスパイアされる」という表現と同じで、こちらも「インスパイアを与える」という表現よりは「インスパイアを受ける」という表現の方が主流です。
「インスパイアを与える」も使えないことはないですが、あまり耳にする機会はないでしょう。
7. 「インスパイア」の英語

「インスパイア」の英語は、1. でも説明しましたが、吸収するという意味の「in」と息という意味の「spire」から出来ている言葉です。
また、英文として使うときは、日本語では主語が「インスパイアされる側」であるのに対し、英文では「インスパイアする側」が主語にきます。
いくつか英文の例文をあげてみます。
「We inspire our an audience.」
(私たちは多くの観客を観劇させる。)
「You inspire my creative activities.」
(あなたは私の創作活動に刺激を与えてくれている。)
このように英語で話すときは「インスパイアする側」が主語にくるので、気を付けて使いましょう。
8. 「インスパイア」と「パクリ」の違い

ここで「インスパイア」と「パクリ」の違いについてみていきます。
「パクリ」とは、現代用語において「盗む」という意味があります。
「この作品をパクった」といえば、「この作品を盗作した」という意味になりますし、「パクられた財布」というと「盗まれた財布」という意味になります。
そして、ここで問題になるのは、「インスパイア」を受けた作品が、しばしば盗作だと主張されかねない事態を招く場合があるということです。
芸術の世界は非常に曖昧な部分があり、どこまで人の影響を受けて作った作品が盗作で、どこまでがインスパイアされた作品なのかの線引きが難しいです。
例えば、「これはピカソの盗作だ」と指摘を受けた芸術家が、「これは盗作ではない。単にピカソのインスパイアを受けた作品」などと主張する場合もあります。
実際、多くの芸術家は、これまでに様々な作品や思想にインスパイアされ、今の作品造りへと結びついています。
そのため、「インスパイアを受けた作品は盗作だ」
などと主張されたら、多くの芸術家の作品が盗作としてあてはまってしまうでしょう。
「インスパイア」なのか、それとも「パクリ」なのかの見極めは、非常に難しいです。
まとめ

「インスパイア」は歌詞や小説などにもよく使われる言葉なので、意味が分かればさらに作品が楽しめそうです。
また、非常に良い意味を持つ言葉なので使うときがあるかもしれません。
正しい使い方を覚えて、周囲に披露してみましょう。
「インスパイア」はよく耳にする言葉です。
今さら聞けないメジャーな言葉になりつつあるので、知らない人は正しい意味を覚えておきましょう。
1. 「インスパイア」の意味とは?

「インスパイア」は正しくは「inspire」と英語で表記します。
もともとの意味は、吸収するという意味の「in」と息という意味の「spire」から出来ている言葉です。
そして、この2つの言葉が組み合わさると、「インスパイア」には「刺激を受ける」「考え方や思想などを吹き込まれる」といった意味になります。
単なる言葉のイメージですが、「インスパイア」は英語の意味を直訳すると、「息が吹き込まれた」という意味になります。
今まで生気のなかったものが、まるで生き生きと動き出すかのように生まれ変わるようなイメージを持たせてくれる言葉です。
非常にポジティブで格好良い言葉です。
この「インスパイア」の持つ言葉のポジティブさ、そして格好良さから、日本では、コマーシャルやアーティストの楽曲名、車の名前などにも起用されています。
非常に心が前向きになる良い言葉です。
日常生活においていえば、「インスパイア」される瞬間とはどのようなときなのでしょう。
例えば、誰かの生き方を見て格好良いと思い、自分もこうなりたいと思った瞬間などでしょうか。
あるいは何を見て、良いアイディアを閃いた瞬間でしょうか。
日常生活の中でも、周りの人や物事を見て、良い刺激を受けることがあります。
その自分の心に受けた刺激こそが、その人にとっての「インスパイア」です。
2. 「インスパイア」の類語

「インスパイア」の類語についてみていきましょう。
2-1. 影響力(えいきょうりょく)

「インスパイア」の類語として、「影響力」が挙げられます。
「影響力」とは「他に働きかけ、考えや動きを変えさせるような力」のことです。
「インスパイア」にも、他から受けた刺激に反応して、考えや動きに変化が生じるという意味があるので、この2つの言葉は類語として考えられます。
しかし、完全なる類語ではありません。
「インスパイア」の場合は、今まで生気のなかったものが息づいて、イキイキしだす意味を持ちます。
それは、非常にポジティブなもので、インスパイアを受けた人は希望と夢を胸に抱くような、明るいイメージを持つ言葉です。
それに比べると、「影響力」はポジティブなイメージだけでなく、マイナスなイメージも含んでいます。
「悪い友達の影響力が強すぎて、とうとう彼も不良になってしまった」
などのように、悪い意味でも使われています。
ここに、「影響力」と「インスパイア」の違いがあります。
いくつか例文を挙げていきましょう。
まずは良い意味での影響力から。
「クラスにおける彼女の影響力はとてもすごい。彼女が着れば、可愛いとはやし立て、みんな真似をしようとする」
(クラスにおける彼女の周りにもたらす変化はすごい。彼女が着れば、可愛いとはやし立て、みんな真似をしようとする。)
次いで悪い意味での影響力の例文。
「この影響力は計り知れないぞ。このままだと、この町全体が死滅してしまう」
(この周りにもたらす変化は計り知れないぞ。このままだと、この町全体が死滅してしまう。)
このように、「影響力」は悪い意味でも良い意味でも使われています。
2-2. 生気が宿る(せいきがやどる)
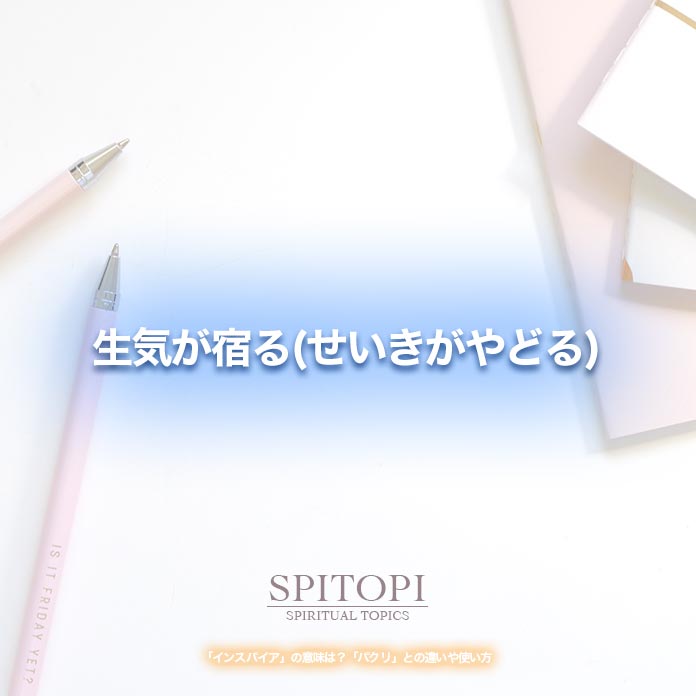
生気が宿るとは、「活気が自分にとどまる」という意味です。
「生気が宿る」は「生気」と「宿る」の2つの言葉に分けることができます。
ぞれぞれの意味としては、「生気」が「いきいきとした感じ」「活気」を表し、「宿る」が「その場所にとどまること」を表しています。
「生気」という言葉も「宿る」という言葉も、非常に前向きで良いイメージを持つ言葉です。
「生気」には文字通り「生きる気力」を、「宿る」には妊娠することを「子が宿る」と表現するように良い縁起の良さを感じる日本語です。
この点から、「インスパイア」が持つイメージと非常に類似しているといえます。
また、「生気が宿る」には、「元気になる」「生気が戻る」「顔色がよくなる」「血の気がさす」などの意味があります。
これらの意味も、非常に前向きで良い状態に変化することを表す意味です。
この意味からも「生気が宿る」の言葉は、良い影響を表す「インスパイア」と非常に似ていると言えます。
例文としては、「彼の表情は暗かったが、その吉報を聞いた途端、生気が宿ったように目をランランと輝かせた」
(彼の表情は暗かったが、その吉報を聞いた途端、希望が宿り、目をランランと輝かせた。)
「まるで人形のように心のこもった言葉をかけられない人だったけど、今となっては嘘のようだ。まるで生気が宿ったかのように感情表現が豊かになった」
(まるで人形のように心のこもった言葉をかけられない人だったけど、今となっては嘘のようだ。元気に明るくなり、感情表現が豊かになった。)
などが挙げられます。
何かの影響を受けて、良い方向へと変わっていく姿を伺うことができる表現です。
スポンサーリンク