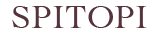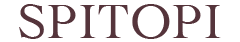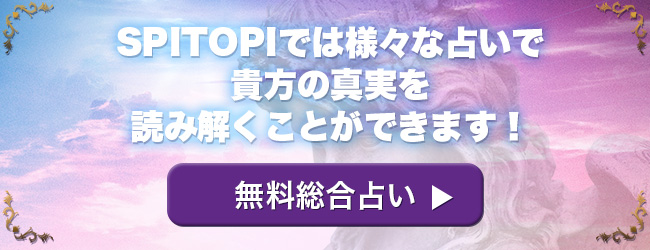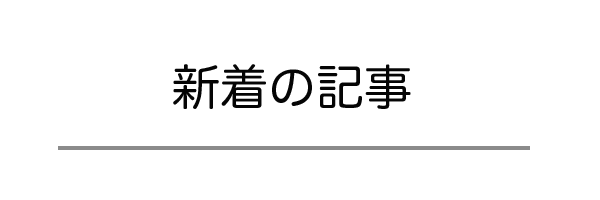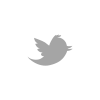「肩を貸す」の意味と類語を紹介します。
また「肩を貸す」時の心理と使い方についても紹介していきます。
- 「肩を貸す」の意味とは?
- 「肩を貸す」の類語
- 「肩を貸す」心理
- 「肩を貸す」の使い方
- まとめ
1. 「肩を貸す」の意味とは?

「肩を貸す」とは、困っている人を助けてあげるという意味を持つ言葉です。
例えば、足を捻挫してしまった人がいた時に、肩に手を捕まらせてあげて歩行の手伝いをしてあげる時が、まさしく「肩を貸す」行為となります。
骨折して松葉つえをついて学校に通っている同級生に肩を貸してあげて、段差などを無事に移動するよう手伝う行為は「肩を貸す」の代表的な行為といえるでしょう。
このように肉体的な「肩」を貸して、相手を助けてあげる行為も「肩を貸す」ですが、それ以外の援助的な行為に対しても「肩を貸す」という言葉を使います。
例えば簡単なお手伝いをする時にも「肩を貸す」という行為を使います。
仕事場の大掃除をしている同僚を見ていて、「このままでは終わらないかもしれない」「大変そうだな」と思った時に、自分の仕事を置いて掃除を手伝ってあげる人がいます。
このような行動も「肩を貸す」という言葉の中に含まれています。
また目上の人が、年下の人に対してサポート行為を行う時も「肩を貸す」という表現をします。
例えば相撲取りで番付が上の力士が、若手のトレーニングに付き合う事も「肩を貸す」といいます。
ビジネスシーンで、後輩のプロジェクトを支援する行為やお手伝いをしてあげる行為も、同様に「肩を貸す」に含まれる行為となります。
このように比較的ライトな感じで誰かを助けてあげる時、「肩を貸す」という言葉を使います。
助けてもらう方も「助けてください」と本気の支援を願い出るのは難しいですが、「ちょっと肩を貸してください」ならお願いがしやすいです。
2. 「肩を貸す」の類語

「肩を貸す」の類語をチェックして、「肩を貸す」の言葉の意味を立体的に理解していきましょう。
そこで「肩を貸す」の類語をいくつか見て行きます。
自分が誰かにしてあげている行為は、どの言葉がもっともイメージが近いでしょうか。
2-1. 「手を貸す」

「肩を貸す」と同じような意味に「手を貸す」という言葉があります。
誰かを助けてあげる時に、「手を貸す」という表現をします。
こちらの言葉も、「肩を貸す」と同様に、ややライトなサポートを行う時に使う言葉です。
例えば大きな荷物を持って横断歩道を渡ろうとしている高齢者がいた時に、荷物を持って一緒に横断歩道を渡ってあげるようなサポート行為を「手を貸す」といいます。
ベビーカーを押しながら駅の階段を上ろうとしているママのために、荷物やベビーカーを代わりに持ってあげるような行為も「手を貸す」となります。
「手を貸す」という言葉を使って誰かを助ける時は、自分の時間や労力、家計を犠牲にせずに行える軽いサポートの場面で使う事が多いです。
「肩を貸す」と同様に、手伝う人にそれほど負担がかからない時に、使用したい言葉です。
2-2. 「助け舟を出す」

「肩を貸す」と似た言葉のひとつに「助け舟を出す」という言葉があります。
そもそも「助け舟」とは、海や池などで溺れかけている人を助けるための「救助船」の事です。
救助船を出して、遭難しそうになっている人を救ってあげる行為となります。
命を救う場合もある事から「肩を貸す」「手を貸す」という言葉よりも、やや重めな救済行為となります。
また「助け舟を出す」という言葉を使う時は、「ヒントを出す」という意味もあります。
あくまで救助船を出すだけで、自分が海や池の中に飛び込み、遭難している人を助けるわけではありません。
そこから間接的に誰かを助ける、ヒントを出したり、策を与えたりして、誰かを救うという意味合いが強くなっています。
例えば仕事上で苦しんでいる後輩を見た時に、情勢が直接問題を解決せずに、状況を打開するようなヒントを授けます。
後輩はヒントを頼りに自分の力で、仕事上の問題を解決する事ができるかもしれません。
このように困っている人にヒントを授ける行為が「助け舟を出す」のイメージにもっとも近いかもしれません。
クイズの答えが出ない人に、ちょっとしたヒントを言う行為も、「助け舟を出す」の言葉が表す行為に含まれます。
2-3. 「片肌脱ぐ」

「片肌脱ぐ」という言葉も、誰かを手助けしてあげる意味の言葉です。
「片肌脱ぐ」とは、着物の片肌をはだけて、肩部分の肌を出すという意味です。
着物を着ている時代の人が、誰かを助ける時に、片肌を出して気合をいれている様子をイメージすると良いでしょう。
例えば重いリアカーを押している女性を、着物の片肌を脱いで気合を入れて後ろから押してあげるようなイメージです。
このように「肩を貸す」よりも「ちょっと気合を入れて」誰かを助けてあげる行為が「片肌を脱ぐ」といえるでしょう。
2-4. 「一肌脱ぐ」

「片肌脱ぐ」よりもより本気度が強い手助けをする行為が「一肌脱ぐ」です。
「片肌脱ぐ」の場合は、着物の片方だけを脱いで気合をいれていましたが、「一肌脱ぐ」の場合は着物の両方の袖を脱いで、上半身が露出した状態になっています。
見た目をイメージしただけでも「一肌脱ぐ」の方が、助ける気が強い事が分かると思います。
「肩を貸す」のサポートが、足をくじいている人に肩を貸して歩行の手助けをしてあげる程度のサポートなのに対して、「一肌脱ぐ」の場合は、自分の車を出して送り迎えを担当してあげるような、全面的な支援を感じさせます。
場合によっては、足が治るまでの医療費も肩代わりをしてあげるような全面的なサポートを行うかもしれません。
このように「一肌脱ぐ」行為は、誰に対してもできる事ではなく、大切な人に対してや、手助けをする事で後に大きな利益が得られそうだと思う時に限られます。
「一肌脱ぐ」時は、相手を選んで行うようにしましょう。
2-5. 「助太刀」

「助太刀」という言葉があります。
「助太刀」とは、武士の時代の果し合いの時などに、味方になって加勢してもらう時に使った言葉です。
そのため「助太刀」には、命をかけるような大変な場面でもサポートをするという「真剣度」が高いサポートの場面で使います。
また果し合いを、現代のスポーツに例えて、本来のチームメイト以外の人にチームに加わってもらう時も「助太刀」と呼びます。
「助太刀」をする人そのものの事を「助太刀」と呼び、サポートをする行為は「助太刀をする」などと言います。
「助太刀」という言葉を日常的なシーンで使う事もあります。
会社で行っている自分の業務が終わりそうもない時に、手の空いている同僚に「助太刀を頼む」とお願いする事もあります。
草野球の試合で人数が足りない時に、近所に住んでいる野球好きな人に声を掛けて「助太刀をお願いする」事もあります。
このように「助太刀」は便利に使う事ができますが、もともとの、「武士の仲間に果し合いのサポートをお願いする」というイメージを持っておいた方が良いでしょう。
そして他の似たような言葉と使い分けて、ここぞという時に「助太刀」という言葉を使った方が効果的かもしれません。
また年配の方には「サポートしてください」と言うよりも、「助太刀してください」と言ったほうが、意味が伝わりやすく、意気に感じてくれる可能性が高いかもしれません。
2-6. 「サポートする」

「肩を貸す」という言葉を、もっとも現代風に言えば「サポートする」になるでしょう。
「サポートする」には、ちょっとしたお手伝いから、「助太刀」のように全面的にプロジェクトに関わるような深いお手伝いをする行為も含まれます。
横文字でライトなイメージがあるからか、言う方も「サポートをお願い!」と頼みやすく、言われる方もあまり抵抗なくお手伝いをする事ができます。
締め切りを目の前にした前日の夜から、徹夜で仕事を手伝ってもらうような時は「肩を貸して」「手を貸して」とお願いするには、作業が辛すぎます。
とはいえ「助太刀して」は堅苦しいかもしれません。
こんな時でも「サポートしてくれる?」は適当な言葉です。
どんな時でも「サポートして」は言いやすく、言われても抵抗が少ないので、使いやすい言葉になるでしょう。
3. 「肩を貸す」心理

誰かに「肩を貸す」という行為は、簡単なようでなかなかできるものではありません。
それほど重い負担ではありませんが、それなりに労力を使いますし、自分の時間を少しではありますが、犠牲にするからです。
それでも「肩を貸す」人の心の中はどのようなものでしょうか。
そこで「肩を貸す」の心理について紹介します。
3-1. 「ほおっておけない」

例えば高齢者の方が重い荷物を持って道を歩いているのを見た時に、あなたはどう思うでしょうか。
「ほおっておけない」と思う人も少なくないはずです。
移動中や仕事中で忙しく、手を貸せない場合は仕方ありませんが、できれば「肩を貸したい」と思うのではないでしょうか。
高齢者の方の荷物を代わりに持ってあげて、しばらく歩く程度の行為は、健康な人にとってどうという事はないからです。
それよりも、高齢者の方が辛そうに見ている方が辛いとかじる人の方が多いはずです。
このように「ほおっておけない」場面に遭遇すると、人は「肩を貸す」事になります。
徹夜が続いている同僚を見たら、「ほおっておけない」という気持ちになるかもしれません。
完全にコミットして手伝うわけではありませんが、一つのタスク程度なら「肩を貸して」手助けしてあげたいと思うでしょう。
このように人が本来持っている優しさの感情が、「肩を貸す」行為を生みます。
優しい性格の人ほど、「肩を貸す」機会が多くなるはずです。
3-2. 「弱い立場の人を助けるのは当然」
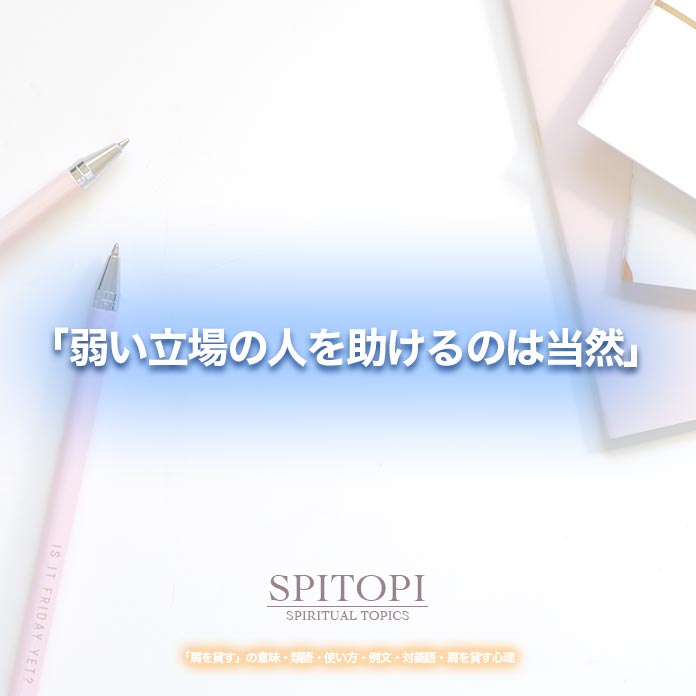
「弱い立場の人を助けるのは当然」と考えている人がいます。
このような人は、大きな荷物を持って道を歩いている人がいれば手助けをしますし、仕事が終わらない同僚を見たら、できる範囲で手助けをするでしょう。
生まれつき正義感が強いヒーロータイプの性格の持ち主かもしれませんし、両親の育てられ方によって「弱い立場の人を助けるのは当たり前」と思っているのかもしれません。
当たり前だと思っていれば、行動を起こす時に「面倒だ」とか「恥ずかしい」など、心が揺れ動かないのでスムーズに「肩を貸す」事ができます。
助けるのは当然と思っている人は、余計な事を考えない分、助けられた人にとっても気が楽です。
とてもスマートに行動ができるため、周囲の人から好感を持たれる事が多いでしょう。
3-3. 「好意を持っている」

「肩を貸す」時に、相手に「好意を持っている」ケースがあります。
例えば好きな人が職場にいる場合、その好きな人の事を手助けしたいと思うのは当然でしょう。
むしろ「肩を貸す場面はないか」と思いながら、毎日を過ごしているかもしれません。
そして少しでも困った場面に遭遇しているのをみつけたら、走って行って「肩を貸す」のではないでしょうか。
実際に誰からも助けてもらう事ができる人は、そのコミュニティでの評価が高いケースが多いです。
誰からも好かれている人は、誰からも「肩を貸してもらう」機会が多くなります。
職場の紅一点の若い女性などは、毎日のように誰かにサポートをしてもらっているはずです。
動機が「好意」の場合は、している方が楽しいので、全く苦になりません。
3-4. 「マナーとして肩を貸す」

社会人としてのマナーなどを大切にしたいと思う人も「肩を貸す」行為を頻繁に行います。
例えば格闘技の試合が終わった後、負けて傷ついた人に勝者が貸して花道を引き揚げる事があります。
このような行為は、格闘家としてのマナーのようなものです。
職場でも大量の荷物を持っている人がいたら、代わりにエレベーターのボタンを押す、廊下ですれ違う時は道を譲る、ドアを開けてあげるなどのマナーを守るために「肩を貸す」行為を行う人も少なくないでしょう。
そこには特別な感情は無く「マナーを守りたい」という社会人としての常識だけが存在します。
マナーがしっかりしている職場では、このような「肩の貸し借り」は日常的に行われています。
働きやすい理想的な職場といえるかもしれません。
3-5. 「育成する」

「肩を貸す」という言葉には「ちょっとしたサポートをする」という意味がありますが、「育成する」という意味もあります。
職場の後輩の仕事をサポートする時に「肩を貸す」と言いますが、ただ手伝うというよりも、「肩を貸す事で後輩の実力を引き上げる」という意味が強いです。
格闘技の世界や、スポーツの世界では、強い人と弱い人、強いチームと弱いチームが戦う時に、強い方が「肩を貸す」と言います。
強い人は弱い人と戦っても、「勝利」という事実が残るだけですが、弱い人はその戦いから様々な事を学ぶ事ができます。
強者に「肩を借りて」試合をする事で、強くなるための貴重な経験を積む事ができます。
このように「肩を貸す」という言葉には、単純にサポートをするだけでなく、壁になって貴重な経験を積ませるような育成する意味も含まれています。
4. 「肩を貸す」の使い方

「肩を貸す」という言葉には、「サポートをする」「育成をする」という意味が含まれている事が分かりました。
それでは「肩を貸す」をどのように文章に組み入れて、日常生活に活かせばよいでしょうか。
そこで「肩を貸す」の使い方を例文とともに紹介います。
4-1. 日常生活で使いたい「肩を貸す」の例文
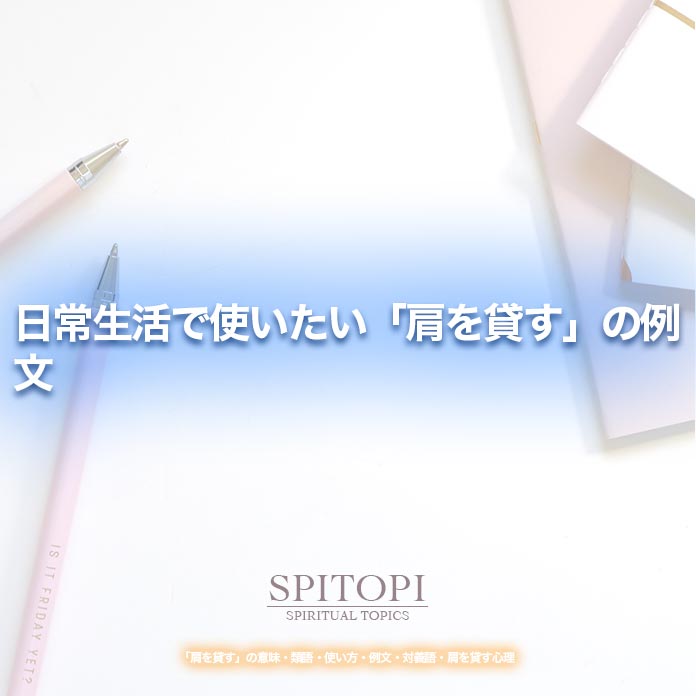
「肩を貸す」を日常生活で使う時は、本当に肩を貸してサポートをしてあげる時が、いちばん分かりやすいです。
そこでまず肉体的な意味での「肩を貸す」の使い方を見て行きましょう。
例えば友達とライブ会場で待ち合わせした時に、足をひきずって歩いている友達を発見したとします。
友達に理由を聞くと「階段を下りる時に足首をひねってねん挫した」と言います。
そして「だから悪いけど、今日のライブはキャンセルするよ、一人で行ってきて」と言うかもしれません。
そんな時に、「肩を貸す」つもりがあるなら、手助けをする提案をしてみましょう。
「俺が肩を貸すから、一緒にライブ見ようぜ!」という感じです。
「スタンディングの必要がある時は、俺が肩を貸すから気にするなよ」などと言いましょう。
「肩を貸す」を文字通り、自分の方を貸す時に使うと、とてもスムーズで相手にも意味が伝わりやすいのでおすすめです。
4-2. 仕事の場面で使いたい「肩を貸す」の例文
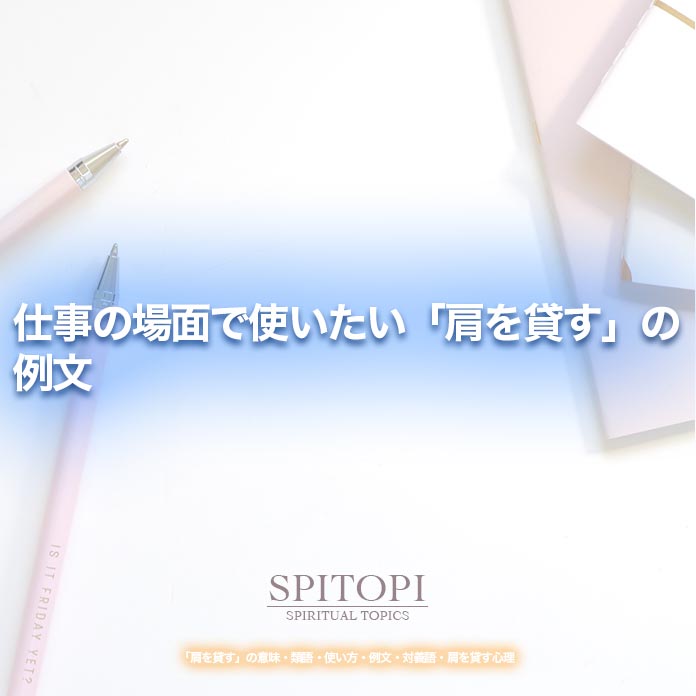
仕事中にも「肩を貸す」場面が多いです。
特にあなたに後輩がいる場合は、ぜひ「肩を貸して」あげましょう。
例えば後輩がプレゼンの練習をしている時に、あなたは後輩をサポートしたいと思います。
そんな時に、プレゼンの資料作りを手伝ったり、プレゼンの仕方を手取り足取り教えてあげても、仮にプレゼンは成功しても後輩の成長は見込めないと感じるかもしれません。
そこで後輩に「俺をクライアントだと思ってプレゼンしてみろ」と提案してみましょう。
これはまさに「後輩に肩を貸す行為」です。
「お前に肩を貸してやる。俺を厳しいクライアントだと思って、全力でプレゼンしろ」などと言いましょう。
後輩は意気に感じて思い切りプレゼンをし、その実力を伸ばす事ができるはずです。
後輩に「肩を貸す」行為は、とても格好いい行為です。
ぜひ余裕がある時は「肩を貸す」行為をしてみましょう。
まとめ

「肩を貸す」には様々な意味があり、日常的なちょっとした場面から、仕事の大切な場面でも使用できる言葉です。
類語もたくさんありますので、サポート度や場面によって使い分けると意味が通じやすくなるでしょう。
「肩を貸す」の意味と類語を紹介します。
また「肩を貸す」時の心理と使い方についても紹介していきます。
1. 「肩を貸す」の意味とは?

「肩を貸す」とは、困っている人を助けてあげるという意味を持つ言葉です。
例えば、足を捻挫してしまった人がいた時に、肩に手を捕まらせてあげて歩行の手伝いをしてあげる時が、まさしく「肩を貸す」行為となります。
骨折して松葉つえをついて学校に通っている同級生に肩を貸してあげて、段差などを無事に移動するよう手伝う行為は「肩を貸す」の代表的な行為といえるでしょう。
このように肉体的な「肩」を貸して、相手を助けてあげる行為も「肩を貸す」ですが、それ以外の援助的な行為に対しても「肩を貸す」という言葉を使います。
例えば簡単なお手伝いをする時にも「肩を貸す」という行為を使います。
仕事場の大掃除をしている同僚を見ていて、「このままでは終わらないかもしれない」「大変そうだな」と思った時に、自分の仕事を置いて掃除を手伝ってあげる人がいます。
このような行動も「肩を貸す」という言葉の中に含まれています。
また目上の人が、年下の人に対してサポート行為を行う時も「肩を貸す」という表現をします。
例えば相撲取りで番付が上の力士が、若手のトレーニングに付き合う事も「肩を貸す」といいます。
ビジネスシーンで、後輩のプロジェクトを支援する行為やお手伝いをしてあげる行為も、同様に「肩を貸す」に含まれる行為となります。
このように比較的ライトな感じで誰かを助けてあげる時、「肩を貸す」という言葉を使います。
助けてもらう方も「助けてください」と本気の支援を願い出るのは難しいですが、「ちょっと肩を貸してください」ならお願いがしやすいです。
2. 「肩を貸す」の類語

「肩を貸す」の類語をチェックして、「肩を貸す」の言葉の意味を立体的に理解していきましょう。
そこで「肩を貸す」の類語をいくつか見て行きます。
自分が誰かにしてあげている行為は、どの言葉がもっともイメージが近いでしょうか。
2-1. 「手を貸す」

「肩を貸す」と同じような意味に「手を貸す」という言葉があります。
誰かを助けてあげる時に、「手を貸す」という表現をします。
こちらの言葉も、「肩を貸す」と同様に、ややライトなサポートを行う時に使う言葉です。
例えば大きな荷物を持って横断歩道を渡ろうとしている高齢者がいた時に、荷物を持って一緒に横断歩道を渡ってあげるようなサポート行為を「手を貸す」といいます。
ベビーカーを押しながら駅の階段を上ろうとしているママのために、荷物やベビーカーを代わりに持ってあげるような行為も「手を貸す」となります。
「手を貸す」という言葉を使って誰かを助ける時は、自分の時間や労力、家計を犠牲にせずに行える軽いサポートの場面で使う事が多いです。
「肩を貸す」と同様に、手伝う人にそれほど負担がかからない時に、使用したい言葉です。
2-2. 「助け舟を出す」

「肩を貸す」と似た言葉のひとつに「助け舟を出す」という言葉があります。
そもそも「助け舟」とは、海や池などで溺れかけている人を助けるための「救助船」の事です。
救助船を出して、遭難しそうになっている人を救ってあげる行為となります。
命を救う場合もある事から「肩を貸す」「手を貸す」という言葉よりも、やや重めな救済行為となります。
また「助け舟を出す」という言葉を使う時は、「ヒントを出す」という意味もあります。
あくまで救助船を出すだけで、自分が海や池の中に飛び込み、遭難している人を助けるわけではありません。
そこから間接的に誰かを助ける、ヒントを出したり、策を与えたりして、誰かを救うという意味合いが強くなっています。
例えば仕事上で苦しんでいる後輩を見た時に、情勢が直接問題を解決せずに、状況を打開するようなヒントを授けます。
後輩はヒントを頼りに自分の力で、仕事上の問題を解決する事ができるかもしれません。
このように困っている人にヒントを授ける行為が「助け舟を出す」のイメージにもっとも近いかもしれません。
クイズの答えが出ない人に、ちょっとしたヒントを言う行為も、「助け舟を出す」の言葉が表す行為に含まれます。
2-3. 「片肌脱ぐ」

「片肌脱ぐ」という言葉も、誰かを手助けしてあげる意味の言葉です。
「片肌脱ぐ」とは、着物の片肌をはだけて、肩部分の肌を出すという意味です。
着物を着ている時代の人が、誰かを助ける時に、片肌を出して気合をいれている様子をイメージすると良いでしょう。
例えば重いリアカーを押している女性を、着物の片肌を脱いで気合を入れて後ろから押してあげるようなイメージです。
このように「肩を貸す」よりも「ちょっと気合を入れて」誰かを助けてあげる行為が「片肌を脱ぐ」といえるでしょう。
2-4. 「一肌脱ぐ」

「片肌脱ぐ」よりもより本気度が強い手助けをする行為が「一肌脱ぐ」です。
「片肌脱ぐ」の場合は、着物の片方だけを脱いで気合をいれていましたが、「一肌脱ぐ」の場合は着物の両方の袖を脱いで、上半身が露出した状態になっています。
見た目をイメージしただけでも「一肌脱ぐ」の方が、助ける気が強い事が分かると思います。
「肩を貸す」のサポートが、足をくじいている人に肩を貸して歩行の手助けをしてあげる程度のサポートなのに対して、「一肌脱ぐ」の場合は、自分の車を出して送り迎えを担当してあげるような、全面的な支援を感じさせます。
場合によっては、足が治るまでの医療費も肩代わりをしてあげるような全面的なサポートを行うかもしれません。
このように「一肌脱ぐ」行為は、誰に対してもできる事ではなく、大切な人に対してや、手助けをする事で後に大きな利益が得られそうだと思う時に限られます。
「一肌脱ぐ」時は、相手を選んで行うようにしましょう。
2-5. 「助太刀」

「助太刀」という言葉があります。
「助太刀」とは、武士の時代の果し合いの時などに、味方になって加勢してもらう時に使った言葉です。
そのため「助太刀」には、命をかけるような大変な場面でもサポートをするという「真剣度」が高いサポートの場面で使います。
また果し合いを、現代のスポーツに例えて、本来のチームメイト以外の人にチームに加わってもらう時も「助太刀」と呼びます。
「助太刀」をする人そのものの事を「助太刀」と呼び、サポートをする行為は「助太刀をする」などと言います。
「助太刀」という言葉を日常的なシーンで使う事もあります。
会社で行っている自分の業務が終わりそうもない時に、手の空いている同僚に「助太刀を頼む」とお願いする事もあります。
草野球の試合で人数が足りない時に、近所に住んでいる野球好きな人に声を掛けて「助太刀をお願いする」事もあります。
このように「助太刀」は便利に使う事ができますが、もともとの、「武士の仲間に果し合いのサポートをお願いする」というイメージを持っておいた方が良いでしょう。
そして他の似たような言葉と使い分けて、ここぞという時に「助太刀」という言葉を使った方が効果的かもしれません。
また年配の方には「サポートしてください」と言うよりも、「助太刀してください」と言ったほうが、意味が伝わりやすく、意気に感じてくれる可能性が高いかもしれません。
2-6. 「サポートする」

「肩を貸す」という言葉を、もっとも現代風に言えば「サポートする」になるでしょう。
「サポートする」には、ちょっとしたお手伝いから、「助太刀」のように全面的にプロジェクトに関わるような深いお手伝いをする行為も含まれます。
横文字でライトなイメージがあるからか、言う方も「サポートをお願い!」と頼みやすく、言われる方もあまり抵抗なくお手伝いをする事ができます。
締め切りを目の前にした前日の夜から、徹夜で仕事を手伝ってもらうような時は「肩を貸して」「手を貸して」とお願いするには、作業が辛すぎます。
とはいえ「助太刀して」は堅苦しいかもしれません。
こんな時でも「サポートしてくれる?」は適当な言葉です。
どんな時でも「サポートして」は言いやすく、言われても抵抗が少ないので、使いやすい言葉になるでしょう。
スポンサーリンク