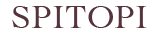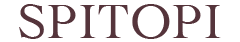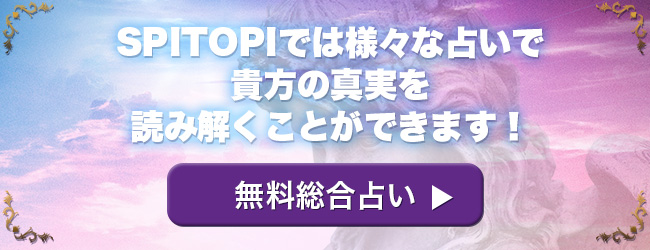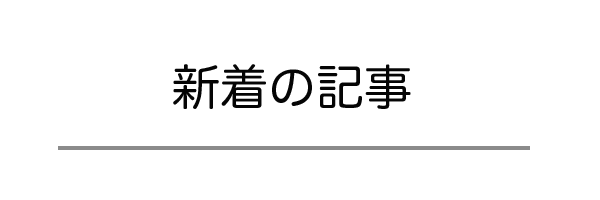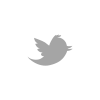「エゴが強い」というと、あまり良い意味にはなりません。
しかし「エゴ」とは人が自分を内面を知る上で大切なものでもあります。
「エゴ」とはどの様なものなのか、言葉の意味だけではなく感情面やスピリチュアルな面からも紹介します。
- 「エゴ」とは?
- 「エゴ」の類語
- 「エゴ」の対義語
- 「エゴ」の使い方
- 「エゴ」で生まれる感情
- スピリチュアルの観点から見るエゴ
- 「エゴ」の塊みたいな人の特徴
- まとめ
1. 「エゴ」とは?

「エゴ」には哲学的な意味と心理学的な意味での解釈があります。
1-1. 哲学としての「エゴ」の意味とは
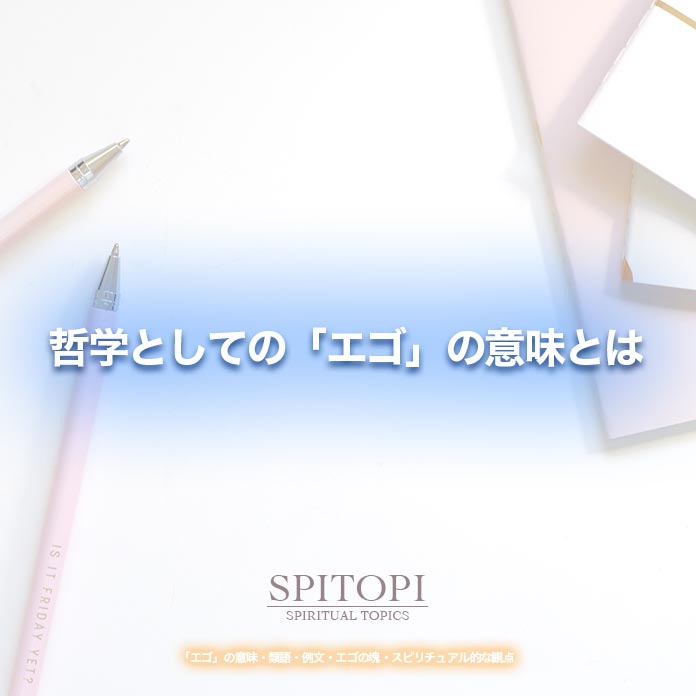
哲学でのエゴ」の意味は一般的に良く知られている「自我」として使われます。
但し哲学は非常に奥深いものですので、単なる「自分」というものではなく、自分以外の存在との差別化という概念があるのです。
「エゴ」があることで自分を知り、自己認識をすることをが「自我」であり「エゴ」なのです。
1-2. 心理学としての「エゴ」の意味とは
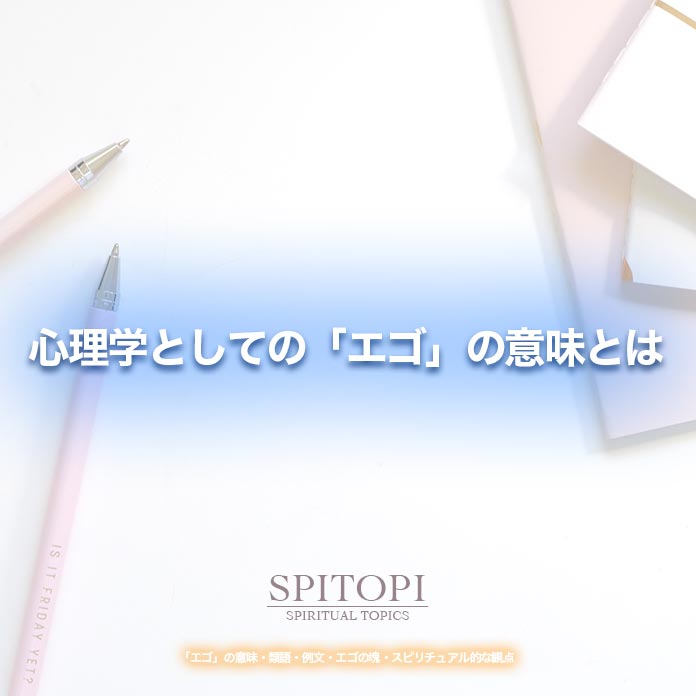
心理学での「エゴ」の意味は、人格を形成する上での3つの要素のうちの一つを意味します。
人格には「イド: 快楽を求める心」「エゴ: イドをコントロールする自我」「スーパーエゴ: 自我の中の向上心」の3つがあります。
「エゴ」は、人が楽しさや楽を求める気持ちを上手にコントロールして、最も安全で確実に行動できる様にする心です。
1-3. 仏教としての「エゴ」の意味

仏教での「エゴ」の意味は、哲学・心理学のどちらの意味も含んでいます。
仏教においては、世界のものは常に変化を続けていて、ほんの一瞬たりとも全く同じ状態はありえないとしています。
この思想は「諸行無常」と呼ばれ「平家物語」でも有名です。
変化し続ける状態の中では「エゴ」は存在できないという考え方をしています。
1-4. 現代的な「エゴ」の意味

上記の「哲学・心理学・仏教的」な意味が混ざって変化して、現代では「エゴ」の意味は「自我」「利己主義」の2つとなっています。
ラテン語では「エゴ=私」という意味ですので、自我と解釈するのは自然です。
そして英語では「エゴイスト」「エゴイズム」という言葉があり、「自分が一番大事」という考え方や、その様に行動する人を意味していることから、「利己主義」に結びつきました。
2. 「エゴ」の類語

「エゴ」自体が非常に難しい言葉ですので、類語と言っても全く同じ意味の言葉はなく、似た様なものと解釈される言葉になります。
2-1. 「一人よがり」

ものごとに対して自分だけで満足したり、良いと思い込んでしまう状態を表しています。
2-2. 「自己中心的」

「エゴ」の基本である「自分が一番」という性質を言い表したものです。
2-3. 「ワガママ」

一般的に「エゴ」の類語として最も多くの人がイメージするのがこの言葉でしょう。
2-4. 「身勝手」

他人のことは考えず、自分の都合や有利になる点だけを考えて行動をすることです。
2-5. 「利己主義」

身勝手が実際の行動を表すのに対し、こちらは考え方や思想を表す言葉です。
3. 「エゴ」の対義語

「エゴ」の対義語は辞書を見れば載っていますが、普段の会話で使うことは殆どありません。
3-1. 「利他主義」

人が得をしたり、人の為に尽くすことで生きがいや喜びを感じたいという考え方です。
人に積極的に親切にしたり、毎回ボランティア活動に参加したりする人の思想を表します。
4. 「エゴ」の使い方

「エゴ」は、悪い意味で使われることが多いのですが、「芯が通った人間」を言い表す時に使うこともあります。
哲学的な意味を含んだ言葉ですので、その時の状況で意味合いが大きく変わってきます。
4-1. 「チームワークにエゴは必要ない」

こちらはワガママという意味で使われています。
チームで行動する時には自分の意見を押し通そうとするのではなく、協調性が必要になります。
4-2. 「仕事を自分のエゴで進めている」
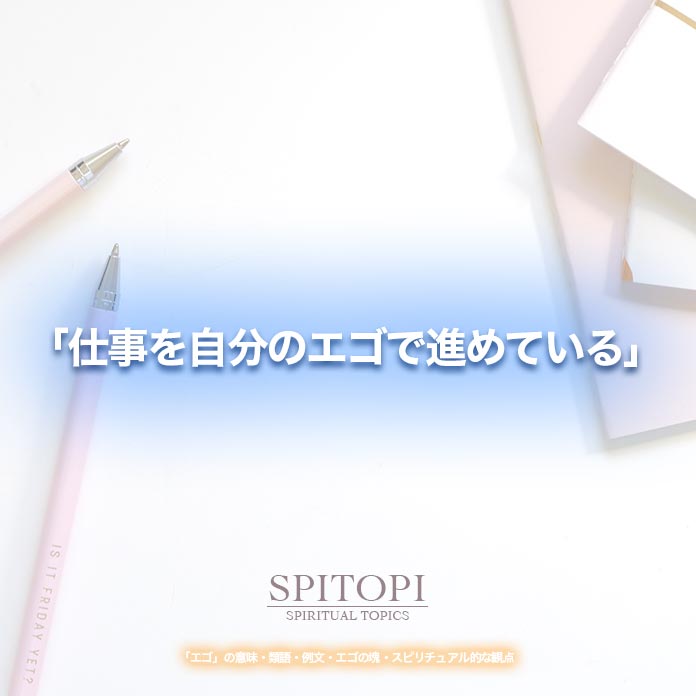
こちらもワガママという意味ですが、自分が思っているのと同じように相手も思っている、と考えてしまっている状態です。
4-3. 「子供の為と言ってもそれは親のエゴだ」
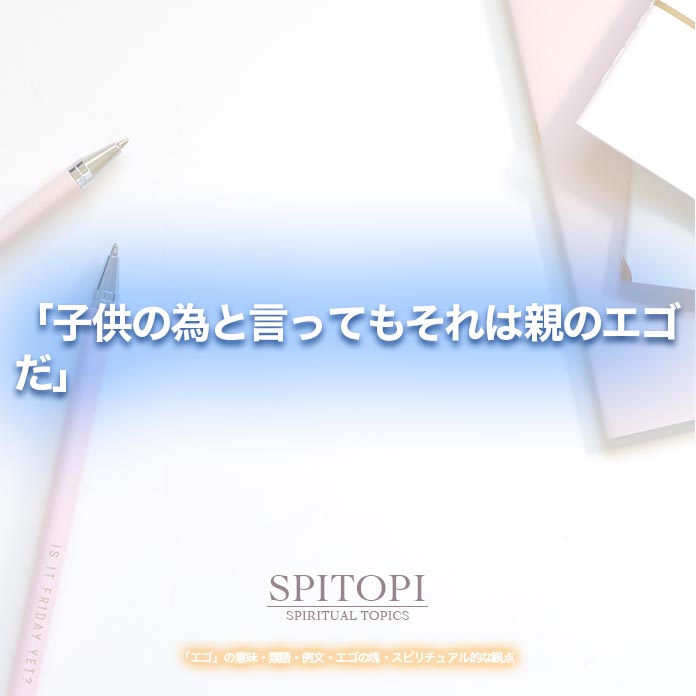
親が「子供の為」と思って塾に通わせたり、高級な洋服を着せたりするのですが、それは子供の為ではなく単に親が自己満足をしたいだけである状態です。
4-4. 「彼はエゴが強いがリーダーとしてこれから伸びるだろう」
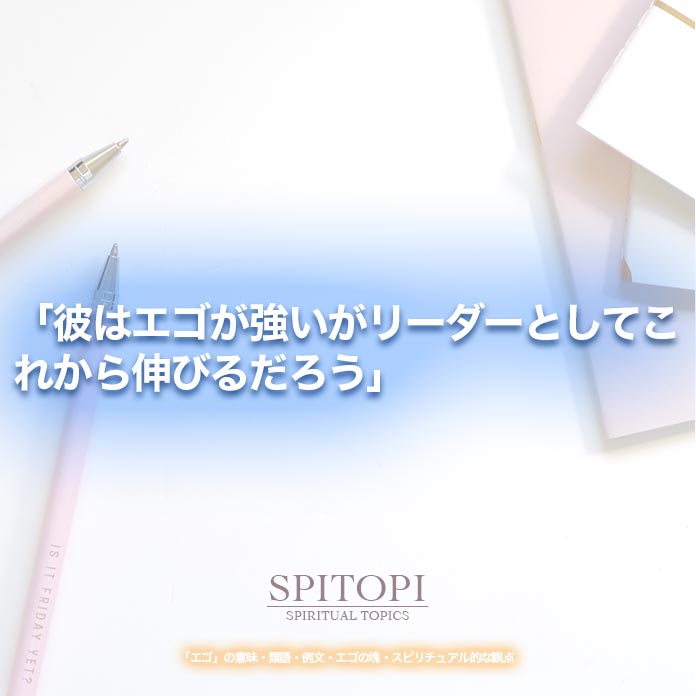
こちらの「エゴ」の場合、単なる「自我」や「自意識」という意味で使います。
独善的な面もあるのですが、リーダーシップを発揮する上では行動力や判断力が必要です。
多少自意識が強い方がアイデアに優れていて、周囲も付いてきてくれることもあるのです。
5. 「エゴ」で生まれる感情

「エゴ」が強いと、内面で様々な感情が芽生えてきます。
その感情に気付くのが遅れると、段々と内面で負のエネルギーが強くなってしまい、それが運気に影響を与えてしまうこともあるのです。
「エゴ」で生まれる感情には以下のものがあります。
5-1. 罪悪感

「エゴ」が強い人は、過去の経験や失敗から「これで本当に良かったのだろうか」と迷いが生じがちです。
他の人よりも、自分とそれ以外の人という意識を強く持つことから「自分はこうでなけれないけない」といイメージを強く持っているからです。
新しく何かにチャレンジしたい、試してみたいと思った時に「そんなことをしていいのか」と罪悪感に働きかけて、折角の行動のチャンスを奪ってしまうことがあるのです。
5-2. 不安感

「エゴ」は自分を強く意識させます。
普段から人と自分を比べて優劣を競い、その結果相手の方が優れているとなると強い不安感を生じるです。
「このままでは明らかに不利になってしまう」「周囲の人にバカにされるのでは」等と、余計な不安ばかり感じる様になります。
自分は自分、人は人という考え方が中々できないので「エゴ」による不安感に支配されて人を貶めようとする人もいるのです。
5-3. 自虐性

不安な気持や自信のなさを隠そうとすると、自虐性を求める人もいます。
「もっと痩せなきゃダメだな」「うっかりミスで残業ばっかり」など、自虐的な言葉は「エゴ」がもっと自分の存在に気付かせる為に仕向けているのです。
もっともっと自分の内面に目を向けて「エゴ」に目覚める様にコントロールされている可能性があります。
5-4. 怒り

「エゴ」が強い人は、自分を攻撃されるのを嫌います。
自分が不利になったり、貶められた時にはそのエネルギーを怒りの感情として表現するのです。
その内容は自分に向けられたものだけではなく、自分が興味を持っているものや好きなものけなされた時も当てはまります。
「エゴ」による怒りの感情で友情や自分の居場所を失った人も大勢います。
5-5. 優越感

人と自分をすぐに比較してしまうのは自然なことです。
しかし「エゴ」が強い人は、その比較の結果が相手の全てと捉えてしまい、付き合い方や人間関係をその基準で考えてしまいます。
カードゲームの様に、常に「相手のポイント・自分のポイント」を測っているので、精神的にも疲れます。
優越感を持てる人としか付き合わない様にするので、視野が狭くなってしまうでしょう。
6. スピリチュアルの観点から見るエゴ

「エゴ」はスピリチュアルにも影響を与えることがあります。
「エゴ」が強い人が陥り易い考え方には以下のものがあります。
6-1. スピリチュアルは特別なことだと思っている
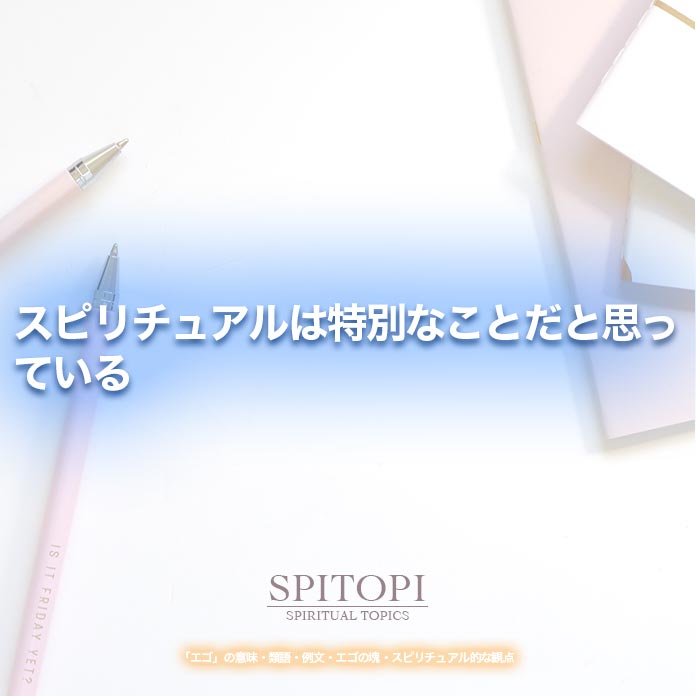
スピリチュアルは、宇宙や自然の中にある「気」を感じる能力を持つことです。
スピリチュアルこそが全てだと思い込んでしまい、そこから「エゴ」が発生してしまいます。
しかし「真実」は一人一人の心に宿るものであり、スピリチュアルでコントロールできるものではありません。
他人の大切にしているものを否定しない様にしましょう。
6-2. 自分が一番スピリチュアル的に優れていると思っている
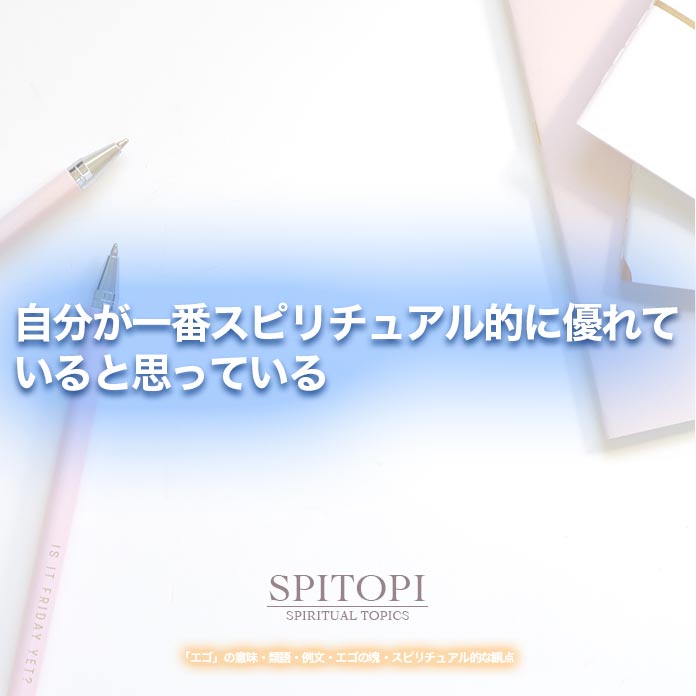
スピリチュアルで前世を透視できる能力があると、前世ではどの様に優れた人物だったのか、歴史的有名人との付き合いがあった等と自慢したくなります。
それが「エゴ」に繋がってしまうのですが、スピリチュアルの考え方ではその様な人は意外と多く、自慢のタネにはなりません。
いずれにせよ前世で業がある人が現世に生まれ変わって来ていますので、人の価値には関係ないのです。
6-3. スピリチュアルな能力を自慢する
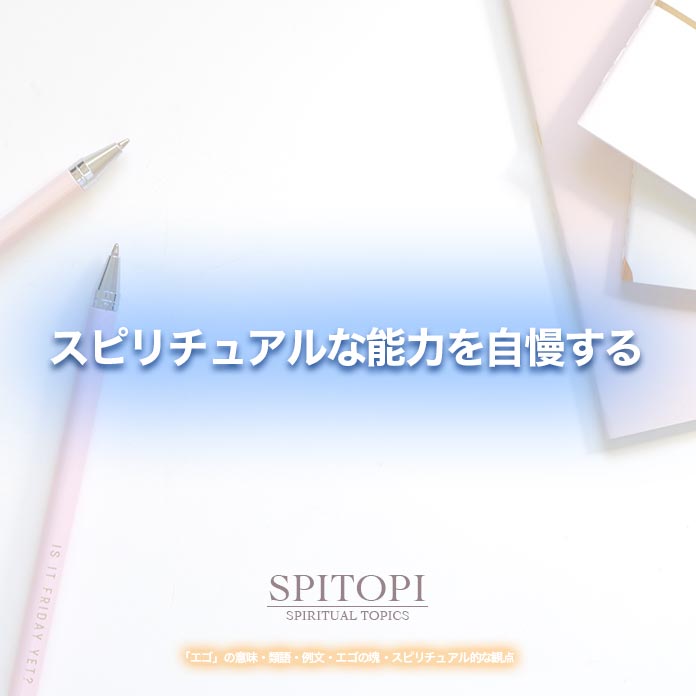
スピリチュアルな能力や知識があると、つい他人に自慢したくなります。
しかしスピリチュアルは、宇宙や自然の「気」を感じる能力であり、自然界の存在としてごく当たり前の能力です。
知識や能力があっても人の為に使わず、「エゴ」のネタにしかならない様ならば意味がありません。
6-4. 自分の体験談ばかりを話す

自分がスピリチュアルな体験をすると、不思議なことばかり起きるので、つい人に話したくなり、そこから「エゴ」が目覚めてしまいます。
しかし誰もが少なからずスピリチュアルな経験をしたことがあり、それに気付いていないだけです。
自分の体験談に興味を持って貰えるとは限らないので、程々にしましょう。
6-5. 他人とスピリチュアル面を比較する
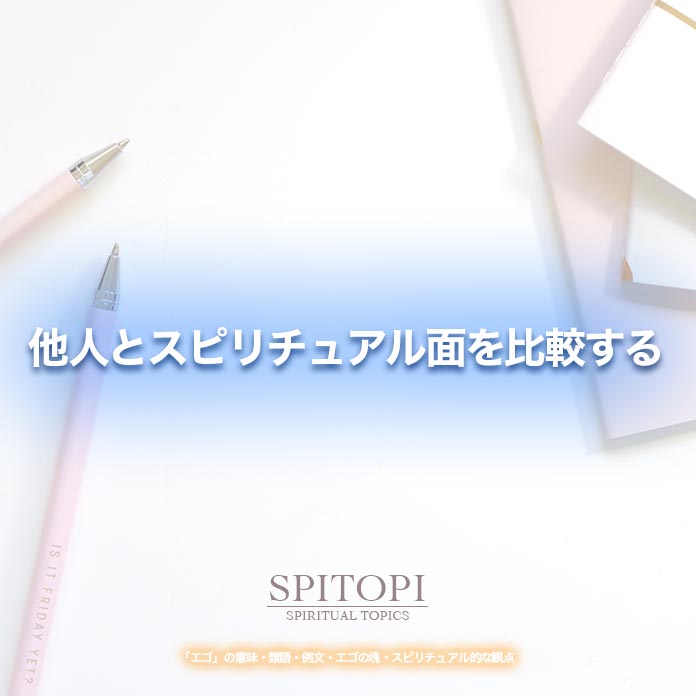
この行為は正に「エゴ」のなす仕業と言えます。
人は元々自然界に存在するもので、スピリチュアル面を比較するのは魂を比較する様なもので愚かな行為です。
魂や「気」のエネルギーに優劣はありません。
6-6. スピリチュアルな正義にこだわる

自分で正しいと思っていることでも、人にとってそうであるとは限りません。
自分でスピリチュアルで導かれた正義を信じることは大切ですが、人にその正義を押し付けるのは明らかに「エゴ」な行為です。
6-7. スピリチュアルを過信する

スピリチュアルな能力があるから、世界を救うべきだと考えてしまう人もいます。
しかし実際には何もできなくて悩んでしまうことでしょう。
スピリチュアルな能力は、自分の内面を高める為に使うのがまず最初です。
世界を救おうというのは目的違いであり、明らかに「エゴ」によるものです。
7. 「エゴ」の塊みたいな人の特徴

世の中には「エゴ」が強くて付き合いにくいと思う人もいます。
「エゴ」の塊みたいな人に共通する特徴について紹介します。
7-1. 自分が悪くても謝らない

社会生活をする上で、自分の非を素直に認めて謝るというのは大切なことであり、決して恥ずべきことではありません。
しかし「エゴ」の塊になってしまうと、「謝る=自己否定」になってしまうので、中々できないのです。
但し自分が悪い、或いは何故か周囲が皆好意的ではないと気付くと、態度を軟化させるのですが、それでも絶対に謝ることはなく、何とかして言い逃れたり、話題を変えようとします。
或いはふてくされた態度で嫌々謝るなど、子供っぽい言動をするのです。
7-2. 自分に対する人の態度が気になる

自分と人との間に一線を引いて完全に差別化していますから、当然優先順位も自分が一番です。
マウンティングとしても、他の人が自分に対してどの様な態度を取るのか気になって仕方ありません。
自分よりも立場が下だと思っている人に比べてどの様に扱われているかをしっかりとチェックしています。
そして相手の態度に納得がいかないと、立場が下だと思っている人に対して不機嫌な態度を取ることもあります。
不満があれば口で言えば良いのですが、怒りのエネルギーに支配されているのでそれができないのです。
7-3. すぐに感情的になる

何が何でも自分の意見を押し通そうとして、感情的になってしまう人も多くいます。
これは「エゴ」の塊の人にとっては、自己主張をすることが素直な自己表現となるので、自覚が無いのです。
周囲の人がどう思うか、自分がどう見えるかなどは全く考えず「自分の意見に耳を傾けて欲しい」という気持ちが先走ってしまっているのです。
7-4. 言い訳ば多い

謝らない、感情的になると同時についてくるのが言い訳の多さです。
何とか謝らない様にしたい、自分を正当化したいという気持ちから饒舌になり、言い訳三昧になってしまいます。
しかし言えばいう程段々と矛盾が出てきてしまい、周囲も段々と興味を失ってしまうのです。
「エゴ」の塊であるので、自分を擁護しないとプライドが傷ついてしまうと思っているのです。
7-5. 仕切り屋が多い

自分の意見を優先したいので、人の前に出ることは大好きです。
会議でも進行役を買って出たり、飲み会では幹事もしたがります。
仕切り役になれば、殆ど自分の思い通りにものごとを運べますので、「エゴ」を満足させることができます。
但し反対意見が多くて自分の思い通りにいかない時にはやる気をなくしたり感情的になることもあります。
7-6. 人に弱みを見せたがらない

仕事やプライベートで悩み事があっても、人に知られるのを好みません。
自分なりの「こうでありたい」という理想像があって、それに反したイメージを持たれるのを嫌うからです。
また、自分を優位に見せたくて幾つか大袈裟に話していることもあり、あまり細かくプライベートなことを話すとそれらのこととの矛盾点がバレ易くなります。
その為に人に対して弱みを見せることは滅多にありません。
7-7. 好きなものに対するこだわりが強い
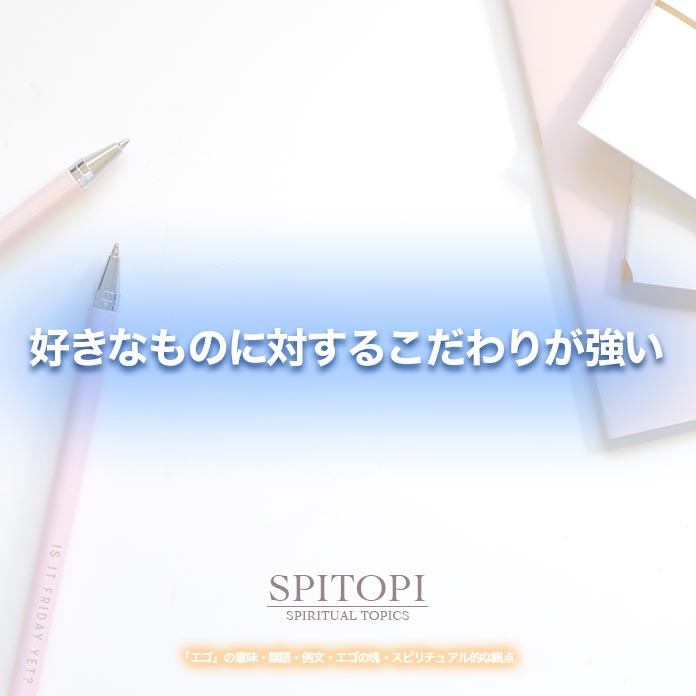
「エゴ」の塊の様な人ですから、当然趣味や興味のあることに対しては非常に強いこだわりがあります。
そのことに関しては常に自分が第一人者でいないと気が済まず、たまにダークホースで経験者や知識が豊富な人がいると負けじと努力をします。
自分の好きなことで他人と差を付けるのが「エゴ」の美学であり、優越感に浸ることができます。
中には他人に知られると自分の価値が下がると思い、趣味があることを隠している人もいるのです。
7-8. SNSを活用している

自分をアピールする方法として、不特定多数の人を対象にしたSNSを有効活用しています。
SNSの良いところは、実際よりも自分を良く表現できるところにあります。
自分のお気に入りの画像を使用すれば、なりたい自分を演出できます。
SNSにより「エゴ」を達成できる人もいて、「いいね!」の数を獲得しようと必死です。
まとめ

社会生活の中では、活発に意見を出したり行動できる「エゴ」の強い人も必要です。
そして誰もが少なからず「自分が一番」という気持ちはあるものです。
それをコントロールできるには、相手の気持ちに気付くことが大切です。
自分の「エゴ」と向き合い、出る部分と引っ込める部分を上手にコントロールできる様になりましょう。
「エゴが強い」というと、あまり良い意味にはなりません。
しかし「エゴ」とは人が自分を内面を知る上で大切なものでもあります。
「エゴ」とはどの様なものなのか、言葉の意味だけではなく感情面やスピリチュアルな面からも紹介します。
1. 「エゴ」とは?

「エゴ」には哲学的な意味と心理学的な意味での解釈があります。
1-1. 哲学としての「エゴ」の意味とは
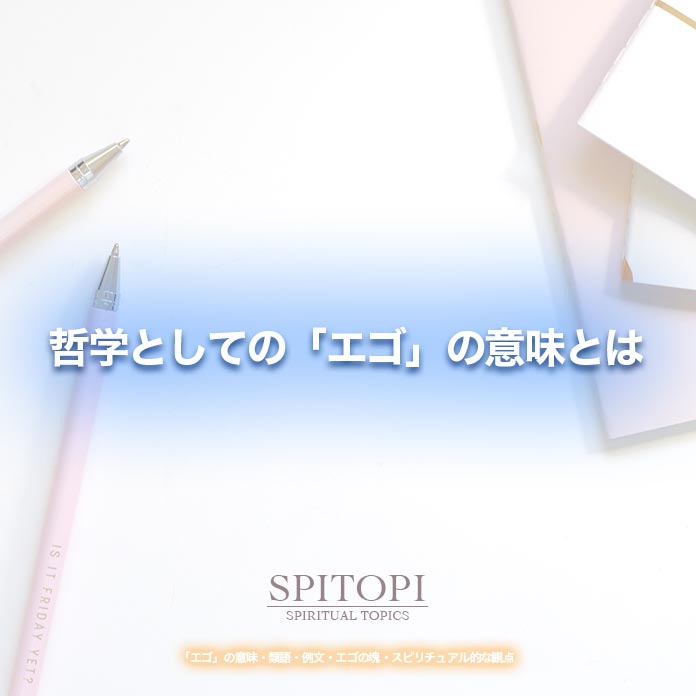
哲学でのエゴ」の意味は一般的に良く知られている「自我」として使われます。
但し哲学は非常に奥深いものですので、単なる「自分」というものではなく、自分以外の存在との差別化という概念があるのです。
「エゴ」があることで自分を知り、自己認識をすることをが「自我」であり「エゴ」なのです。
1-2. 心理学としての「エゴ」の意味とは
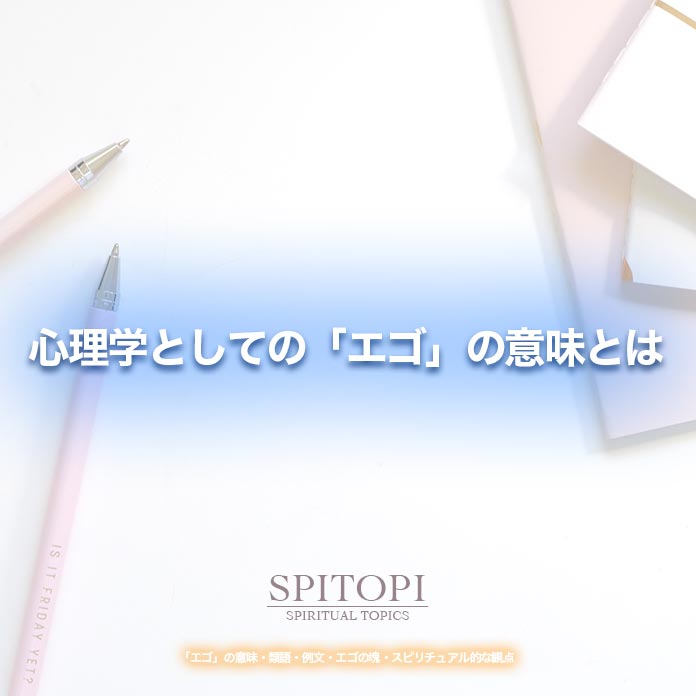
心理学での「エゴ」の意味は、人格を形成する上での3つの要素のうちの一つを意味します。
人格には「イド: 快楽を求める心」「エゴ: イドをコントロールする自我」「スーパーエゴ: 自我の中の向上心」の3つがあります。
「エゴ」は、人が楽しさや楽を求める気持ちを上手にコントロールして、最も安全で確実に行動できる様にする心です。
1-3. 仏教としての「エゴ」の意味

仏教での「エゴ」の意味は、哲学・心理学のどちらの意味も含んでいます。
仏教においては、世界のものは常に変化を続けていて、ほんの一瞬たりとも全く同じ状態はありえないとしています。
この思想は「諸行無常」と呼ばれ「平家物語」でも有名です。
変化し続ける状態の中では「エゴ」は存在できないという考え方をしています。
1-4. 現代的な「エゴ」の意味

上記の「哲学・心理学・仏教的」な意味が混ざって変化して、現代では「エゴ」の意味は「自我」「利己主義」の2つとなっています。
ラテン語では「エゴ=私」という意味ですので、自我と解釈するのは自然です。
そして英語では「エゴイスト」「エゴイズム」という言葉があり、「自分が一番大事」という考え方や、その様に行動する人を意味していることから、「利己主義」に結びつきました。
2. 「エゴ」の類語

「エゴ」自体が非常に難しい言葉ですので、類語と言っても全く同じ意味の言葉はなく、似た様なものと解釈される言葉になります。
2-1. 「一人よがり」

ものごとに対して自分だけで満足したり、良いと思い込んでしまう状態を表しています。
2-2. 「自己中心的」

「エゴ」の基本である「自分が一番」という性質を言い表したものです。
2-3. 「ワガママ」

一般的に「エゴ」の類語として最も多くの人がイメージするのがこの言葉でしょう。
2-4. 「身勝手」

他人のことは考えず、自分の都合や有利になる点だけを考えて行動をすることです。
2-5. 「利己主義」

身勝手が実際の行動を表すのに対し、こちらは考え方や思想を表す言葉です。
スポンサーリンク