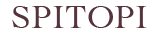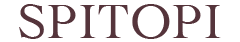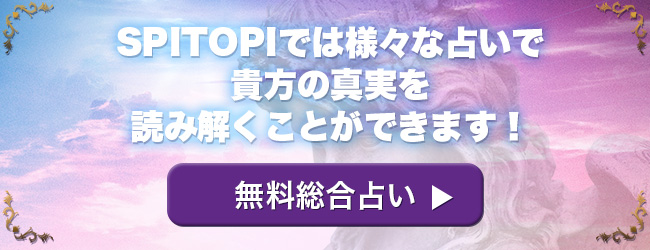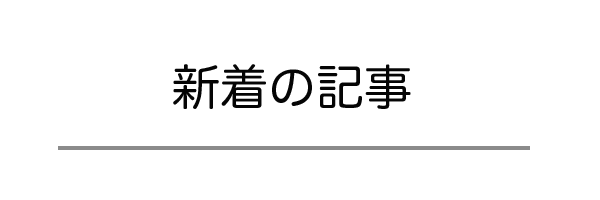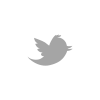社会人になると、自分の思い通りにならないことも多くなります。
「理不尽な相手」に振り回されてしまい、ストレスを感じることもあるでしょう。
ところで「理不尽」とはどういう意味なのか、使い方や人の特徴などについて紹介します。
- 「理不尽」の意味とは?
- 「理不尽」の類語
- 「理不尽」の対義語
- 「理不尽」の使い方
- 「理不尽」を使った例文
- 「理不尽」な人の特徴
- 「理不尽」の英語
- まとめ
1. 「理不尽」の意味とは?

「理不尽(りふじん)」とは、「筋が通らないこと」という意味です。
言葉の成り立ちから考えると「理=ものごとの法則やあるべき姿」、「不=否定語」「尽=きわめる、果たす」という意味を持っています。
「理不尽」は、元々は何かの名前や状態を表す言葉ではなく、それぞれの漢字の意味を組み合わせた言葉です。
全てを組み合わせて「ものごとのあるべき姿を果たしていない」、つまり「ものごとの筋道が通っていないこと」という意味になるのです。
筋道が通っていない状態は様々ありますが、「理不尽」と言われる時はまず対象となる相手を嫌な気持にしたり、不利な役割を押し付ける様な状態を表しています。
2. 「理不尽」の類語

「理不尽」には以下の様な類語があります。
2-1. 「不合理(ふごうり)」

この言葉も元々合った言葉ではなく、漢字の意味を組み合わせて作った言葉と思われます。
「不=否定」「合=合致する、見合う」「理=ものごとの法則やあるべき姿」で、シンプルに「ものごとのあるべき姿に見合っていない」という意味になります。
既存の制度が現状に合っていない時に使われることが多く、ビジネスシーンで役立つ言葉です。
2-2. 「不条理(ふじょうり)」

こちらは大きな意味で「道理に合わない」状態を表す言葉です。
人が決めたことではなく、天災や厄災など、人の力ではどうしようもない時に使われます。
ほぼ「理不尽」と同じ意味で、それぞれを言い換えても意味が通じます。
2-3. 「無理無体(むりむたい)」

相手の意思に関係なく強引に物事を行うことや、社会常識や法律に背いても強制することを意味します。
2-4. 「筋違い」

道理に外れていることで、理不尽の「理」の部分を強調した言葉です。
2-5. 「無茶」

道理に合わないこと、乱暴で無理やりなことを表します。
元々は仏教用語で「自然で全く手が加わっていなもの・不格好なもの」を表す「無作(むさ)」から変化した言葉です。
これを更に強調した言葉が「無茶苦茶」です。
2-6. 「滅茶苦茶」

上記の「無茶」を強調した「無茶苦茶」と全く同じ意味です。
ものごとの後先を考えずに行動する様や、筋道が全く立ってない状態を表します。
3. 「理不尽」の対義語

「理不尽」は漢字を組み合わて作られたものですので、全く反対の意味を持つ言葉は存在していません。
以下に対義語に最も近い意味の言葉を紹介します。
3-1. 「妥当(だとう)」

道理に合っているというよりも、最も無難で反対の余地はない、という時に使います。
他に特に優れた方法がなく、それしかない時に使います。
3-2. 「正当」

道理にかなっていて、当然のことを意味します。
良し悪しに関わらず、正しい論理により導き出される結果です。
3-3. 「適正」

ものごとが適切で正しく取り扱われている状態を表します。
3-4. 「道理」

ものごとのあるべき状態や、筋道が立っている状態を表します。
3-5. 「合理」

しっかりとした論理的根拠があり、道理にかなっていることを言います。
4. 「理不尽」の使い方

理不尽は、道理にかなっていないことならばほぼ使えます。
運命や天災に遭った時など人の力ではどうにもならないことだけではなく、人の言動や組織の対応等に対しても使えます。
自然にそうなってしまうのではなく、誰かが故意的に筋道の立たない言動をした時にも「理不尽」と言えます。
ビジネスシーンで不満を持った時に使う人が多くなります。
但し、「理不尽」は使う相手により「理」が違ってくるものです。
自分では道理に合っていないと思っていても、相手にとっては「当然のこと」と思っている場合もあるのです。
「理不尽」という言葉を使う時には「何がどの様に理にかなっていないのか」という根拠をはっきりとさせる必要があります。
何となく自分が不利になったり気に入らない時に「理不尽」を使ってしまいがちですが、相手を否定したことになるので注意しましょう。
5. 「理不尽」を使った例文

「理不尽」はどの様な時に使う言葉なのか、例文を幾つか紹介します。
5-1. 「取引先から理不尽な要求をされて仕方なく受け入れた」
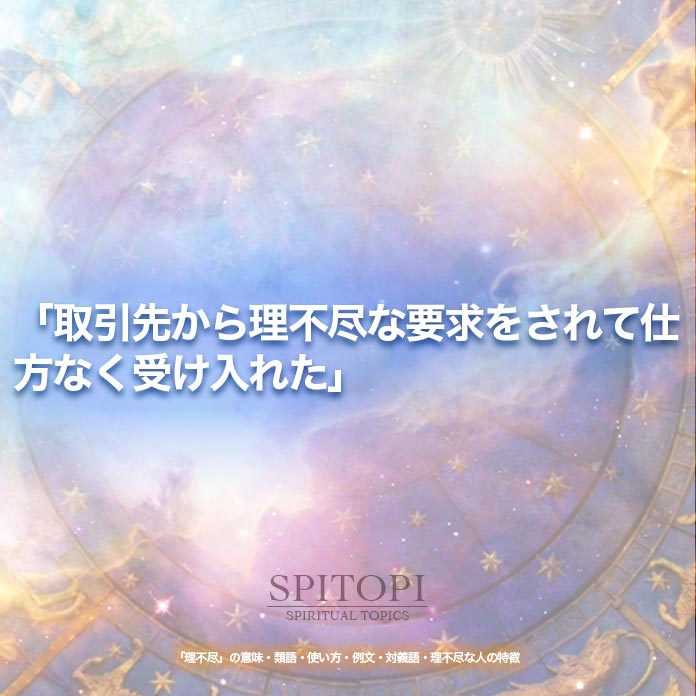
上下の立場があることから、自分の会社にとって不利になる様な要求をされても、断ることができません。
泣く泣く要求をのんだ時に使われます。
5-2. 「上司から理不尽な扱いを受けて退職した」
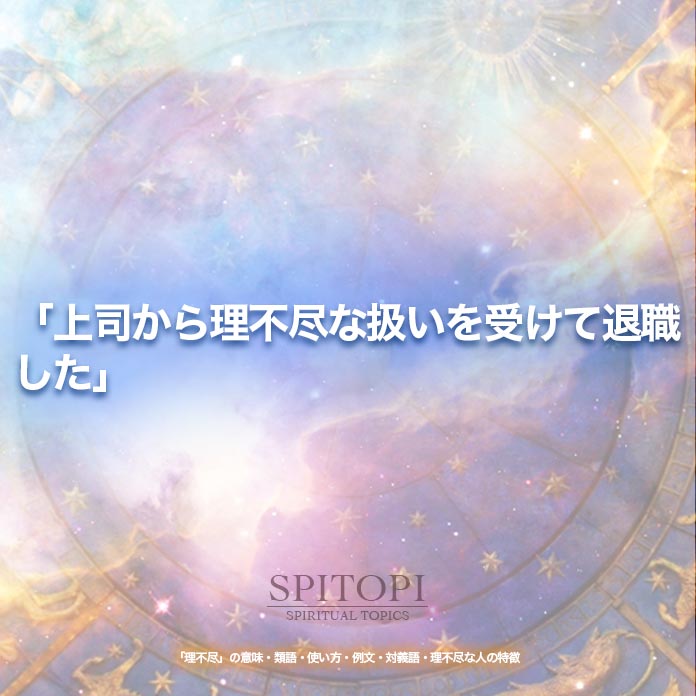
残業を強いられる、責任をなすりつけられるなど、上司が明らかにパワハラと思われる様な態度を取った時に使われます。
この場合、会社の上層部も組織ぐるみでパワハラに加担している状態です。
5-3. 「100円の品物に手数料が500円かかるなんて理不尽だ」

他人の定めたルールに対して不満を感じる時に使えます。
5-4. 「彼がミスをしたのに私が怒られるのは理不尽だ」

自分で思っていたことと違う結果になった時に、道理に合っていないと感じることもあり、その様な時に使います。
5-5. 「前回火事でもらい火したばかりなのに、今回は水害なんて理不尽だ」

自分ばかりが不幸な出来事が続くと、運命に対して文句を言いたくなります。
本来ならば運命や自然には道理やや筋道はないものですが、どこにも怒りのやり場がないのでこの様に使うことがあります。
6. 「理不尽」な人の特徴

「理不尽」という言葉について紹介しましたが、「理不尽な人」というのがいるものです。
なるべく関わり合いたくないものですが、その特徴については以下の通りです。
6-1. 感情の起伏が激しい

穏やかに話をしていたのに、急に怒り出す人がいます。
この様な人に理由を聞いてみると、普通の人ならば気にもしない様なことが原因であることが多いのです。
自分がその時のことを思い出して「相手の顔が気に入らなかった」、たまたま自分が嫌いな食べ物の話題になった、自分だけ知らないことだったなど、他人にとっては計り知れないことが多くあります。
何が逆鱗に触れるか分からず、一度怒るとしばらく機嫌が悪いので、周囲もその人の理不尽さに我慢して付き合うしかありません。
6-2. 公私混同をする

プライベートで嫌なことがあると、仕事でも不機嫌になります。
他の人が笑顔で話し掛けてもつっけんどんな態度を取ったり、わざと情報を教えてくれなかったりします。
理不尽な感情を押し付けられて迷惑するのは周囲の人です。
特に女性は恋愛でトラブルがあると大切な仕事があるのに欠勤することもあります。
上司が公私混同するタイプだと、理不尽な態度を取られて部下が振り回されることになります。
6-3. プライベートに口出しする

会社の人との関係はあくまで仕事だけにしておきたいものですが、中にはプライベートなことに口出しをしてくる人もいます。
特に女性の上司で理不尽な人は「その色、似合わないから替えてきなさい」と言って指図します。
また「ウチは残業が多いんだから、金曜日にデートの約束は入れない様に」とまで言ったりするのです。
身だしなみや社会常識についてならば上司から指導されても仕方ありませんが、全く関係のないプライベートに口出しをされて、しかも理不尽なことを言われると対応に困るものです。
6-3. コロコロ考えを変える

最初に言っていたことと、最終的な結論が全く変わる人がいます。
また、数日前までは反対していたのに、或る日急に「いいね、是非やろうよ」と言う人もいます。
理不尽な人は、ものごとの筋道に一貫性がなく、その時の気分次第で考え方がコロコロ変わってしまうのです。
しかし本人はその時に一生懸命考えてこれがベストだと思っているので、人に迷惑をかけているとは全く感じていません。
明らかに反対意見が多い時には「あ、そう、じゃあいいよ」等と言ってすぐに意見を引っ込めることもあります。
その時の思いつきで軽率かつ理不尽なことを言うので周囲が迷惑します。
6-4. 体育会系のノリである

上下関係に厳しく、先輩に対しては絶対服従です。
社会人になってからもそのノリが変わらずに、上下関係を第一に考えます。
自分が体育会系で育ったので、人も当然そうだと思い、部下や後輩に対して「挨拶の声が小さい」「この仕事を至急やれ」等と厳しくします。
きちんと部下を指導して育てられれば良いのですが、「返事ができないから残業代ナシ」「ミスをしたから昼休み返上で仕事をしろ」等と、理不尽な要求を突き付けることが多いのです。
6-5. 仕事の能力が低い

分り易く言えば「仕事の出来ない人」です。
理不尽な人は、人に対して無理な要求をしたり、やり方をコロコロと変えることが多くあります。
自分だけではなく周囲も混乱して、部署として目標を達成するのが困難いになります。
自分が間違っていたら大袈裟に驚いて「そうだったんですか、すみませんね」で済ませようとします。
筋道を立てて段取り良く仕事をしない為に、正しい知識やスキルがいつまで経っても身に着きません。
口ばかり「簡単です、やります」と言っているけれども誰にも評価されない人材です。
6-6. 自分に自信がない

心理的な特徴ですが、自分に自信がない人は、人に対してすぐにマウンティングをしたがります。
自分の方が優れていると思わせたいが為に、何でもいいから一歩有利な立場になろうと思うのです。
その結果理不尽なことを言って自分を正当化させようとします。
作業の手順に一貫性がなく「自分は常に色々考えて作業の効率化を図っている」と言いながらやたらとミスが多い人もいます。
自分に自信がない分相手を低く見せようとつまらない努力をしますが、全くムダな努力です。
6-7. リーダーシップがあるフリをする

理不尽な人は、筋道が立っていなくても思い切って決断をしてしまうので、リーダーシップがある様に思われがちです。
しかしその人に仕事の采配を任せた時点で誰もが「しまった」と思うのです。
思いつきで人に指示を出すし、仕事の優先順位や難易度も全く考えていません。
とにかく締切に間に合わせることしか考えていないので、仕事の分担にムラが生じることもあります。
適材適所を考えずに振り分けることで「何で自分がこれをやらなければならないのか」と理不尽に思う人もいるのです。
やる気だけが先行して中身のない人は、すぐにバレてしまうでしょう。
6-8. 言行不一致

言うこととやることが矛盾しているのがこのタイプです。
会議で「集まる時間を厳守しよう」と言っておきながら、飲み会やプライベートでは平気で遅刻をしてきます。
読書家で様々な人の名言を知っていたり、人に説教をするのですが、自分に関してはことごとく相反する言動をしています。
親が子供に「つまみ食いをするな」と言っておきながら、実は自分がやっている様なもので、他人から見れば理不尽な行為です。
6-9. 言い訳上手

理不尽な人は非常に弁が立ち、何かの時に周囲が関心する程すらすらと言い訳が出てきます。
仕事でミスをしたり、締切が遅れた時には「余計な電話が5本も入ってきて、その対応に追われてしまって」「途中でパソコン調子が悪くなって、他の人のを借りようとしたんだけど、パスワードが分からなくて」等と、あらゆる言い訳を上手に説明します。
本当は計画性がなく、ギリギリのタイミングで仕事をしてきた自分の責任で、理由の対象となった人にとってはまことに理不尽な言い訳になります。
6-10. 人の言うことを聞かない

人がきちんと説明をしている時に「もう何度もやっているから」としっかりと最後まで説明を聞こうとしません。
目が合ってうなづいたりメモを取ったりしていますが、実は全く頭の中に入っていないのです。
いざトラブルがあった時に「はあ?」と初めて聞く様な態度を取ります。
相手が「メモを取ってたじゃないか」と問い詰めると改めて確認して「本当だ、ゴメンゴメン」と軽く言います。
人の意見をきちんと聞いていないので自分の中で理解し切れずに、とんちんかんな行動を取ってしまうのです。
6-11. 人の好き嫌いが激しい

人により「好きな人・嫌いな人」がハッキリしていて、接する態度ですぐに分かります。
自分が好意を持っている人がミスをすると「いいよいいよ」で済ませて、相性が悪い人だと「いい加減にしてよ」と厳しくします。
同じ様なミスでも人により態度が変わるので、酷い扱いを受けた方は理不尽だと思うでしょう。
仕事の内容ではなく、人の好き嫌いにより態度を変えるのは、理不尽でしかも人間関係を悪化させる可能性があります。
6-12. 普段は優しい

「理不尽な人」は、いつでも理不尽で周囲から嫌われている様なイメージがありますが、実は普段は気さくで面白い人が多いのです。
理不尽だから悪い人と言う訳ではなく、雑談をしていても盛り上げ役となってくれることも多く、部署のムードメーカーだったりします。
軽度の理不尽な人の場合は、問題行動が出た時に周囲が「まただよ」という雰囲気になります。
本人も後から反省して、対象となった人に「昨日は悪かったね」と謝ってくることも多いのです。
6-13. 文系が多い

理系の人は常に論理的に物事を考えるので、理不尽なことを言うのが自分で恥ずかしくなるものです。
これに対して文系の人で、特に感受性が豊かな人は、その時の感情で気分が変わってしまいます。
非常識なことを言っている、理不尽なことを言っていると自分で分かっていてもどうしようもなく、自分で自分をコントロールできなくなってしまうのです。
7. 「理不尽」の英語

英語では同じ「理不尽」でも、その時のシチュエーションにより言い方が変わってきます。
7-1. " It's unreasonable. "

「reason=理由」で、リーゾナブルは「合理的」という意味です。
買い物をする時に「リーゾナブルな値段」というと、「お手頃価格」を意味します。
その「reasonable」に打消しの「un」が付くことで、「理にかなっていない」という意味になります。
7-2. "It's not fair. "

「フェアじゃない=理不尽」という意味で、友人同士などカジュアルな場でよく使われる表現です。
会社でも上司に対して不服がある時に使うことがあり、覚えておくと非常に便利です。
7-3. "That doesn't make sense. "
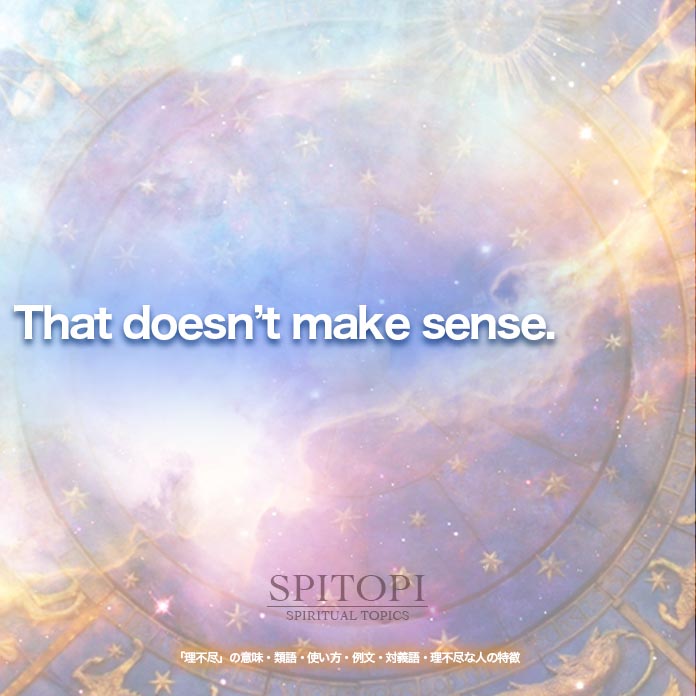
「理にかなってない=理不尽」という意味ですが、ビジネスの場では「understand」と同様に「理解できる、理解できない」という意味で使われることもあります。
7-4. "It's outrageous. "
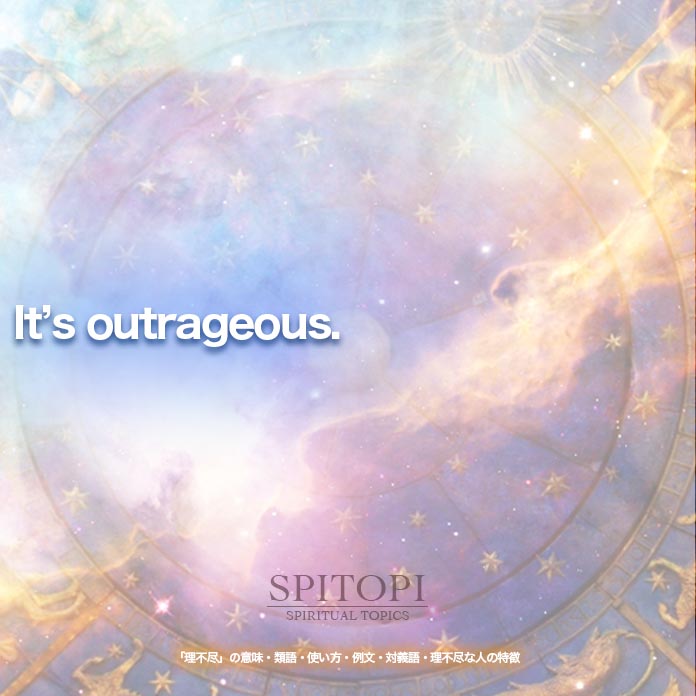
「常識外れだ=理不尽」という意味で、相手に対して非難の意味が強くなります。
まとめ

「理不尽」とは、その行動を取る人にとっては自分を守るための手段の一つです。
自分にとっては十分筋道が立っていても、相手から見れば想定外のことに見える場合もあるのです。
気が付かないうちに理不尽な言動をしてしまう人も多くいますので、普段から相手がどの様な気持ちなのかを良く考えて行動することが大切です。
社会人になると、自分の思い通りにならないことも多くなります。
「理不尽な相手」に振り回されてしまい、ストレスを感じることもあるでしょう。
ところで「理不尽」とはどういう意味なのか、使い方や人の特徴などについて紹介します。
1. 「理不尽」の意味とは?

「理不尽(りふじん)」とは、「筋が通らないこと」という意味です。
言葉の成り立ちから考えると「理=ものごとの法則やあるべき姿」、「不=否定語」「尽=きわめる、果たす」という意味を持っています。
「理不尽」は、元々は何かの名前や状態を表す言葉ではなく、それぞれの漢字の意味を組み合わせた言葉です。
全てを組み合わせて「ものごとのあるべき姿を果たしていない」、つまり「ものごとの筋道が通っていないこと」という意味になるのです。
筋道が通っていない状態は様々ありますが、「理不尽」と言われる時はまず対象となる相手を嫌な気持にしたり、不利な役割を押し付ける様な状態を表しています。
2. 「理不尽」の類語

「理不尽」には以下の様な類語があります。
2-1. 「不合理(ふごうり)」

この言葉も元々合った言葉ではなく、漢字の意味を組み合わせて作った言葉と思われます。
「不=否定」「合=合致する、見合う」「理=ものごとの法則やあるべき姿」で、シンプルに「ものごとのあるべき姿に見合っていない」という意味になります。
既存の制度が現状に合っていない時に使われることが多く、ビジネスシーンで役立つ言葉です。
2-2. 「不条理(ふじょうり)」

こちらは大きな意味で「道理に合わない」状態を表す言葉です。
人が決めたことではなく、天災や厄災など、人の力ではどうしようもない時に使われます。
ほぼ「理不尽」と同じ意味で、それぞれを言い換えても意味が通じます。
2-3. 「無理無体(むりむたい)」

相手の意思に関係なく強引に物事を行うことや、社会常識や法律に背いても強制することを意味します。
2-4. 「筋違い」

道理に外れていることで、理不尽の「理」の部分を強調した言葉です。
2-5. 「無茶」

道理に合わないこと、乱暴で無理やりなことを表します。
元々は仏教用語で「自然で全く手が加わっていなもの・不格好なもの」を表す「無作(むさ)」から変化した言葉です。
これを更に強調した言葉が「無茶苦茶」です。
2-6. 「滅茶苦茶」

上記の「無茶」を強調した「無茶苦茶」と全く同じ意味です。
ものごとの後先を考えずに行動する様や、筋道が全く立ってない状態を表します。
スポンサーリンク