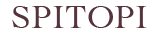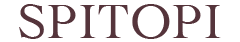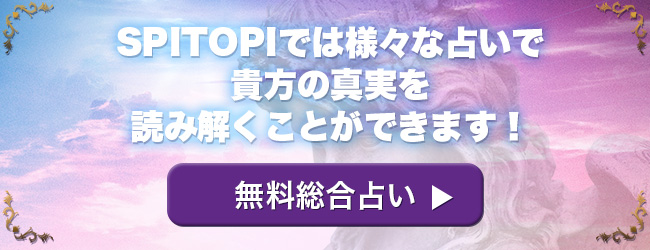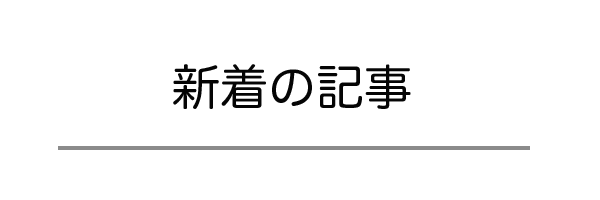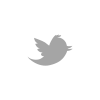「どうしよう」という言葉は、自分を不安にさせてしまうだけではなく、周囲にもネガティブな影響を与えてしまう言葉です。
「どうしよう」が口癖になっている人は、周囲を動揺させてしまうために信頼や信用を獲得することができません。
ですから、そうしたネガティブな口癖を直していくことが重要なのです。
ここでは、「どうしよう」が口癖の人の心理や、特徴、「どうしよう」などのネガティブな口癖を直す方法などについて紹介します。
この記事を参考にして、ポジティブに行動や発言できる人になりましょう。
- 「どうしよう」の意味
- 「どうしよう」が口癖の人の心理
- 「どうしよう」が口癖の人の特徴
- 「どうしよう」を口癖にするデメリット
- 「どうしよう」という口癖を改善するコツ
- まとめ
1. 「どうしよう」の意味

「どうしよう」とは、手段や対応に困ったり、途方に暮れたりした時の心境を表現する言葉です。
「どうしよう」と思ったり、口にしてしまうことは誰でもあります。
しかし、いつもそうした発言をすると、自分の不安や恐れをコントロールできず、より不安感を抱くようになってしまいます。
また、周りの人の不安を煽り、よりネガティブな雰囲気を作ってしまう危険性も高くなるのです。
それゆえに、「どうしよう」という言葉を口癖にしないことが重要なのです。
2. 「どうしよう」が口癖の人の心理

2-1. 不安や恐れをコントロールできない

いつも「どうしよう」と言ってしまう人は、自身のネガティブな感情をコントロールできていない場合が多いです。
何か問題が起きた時、不安や恐れが先行してしまい冷静な判断ができなくなってしまうのです。
また、起きてもいないトラブルを杞憂して、「どうしよう」という言葉が出てきてしまう場合もあります。
いずれにせよ、不安にとり憑かれ、正常な行動ができなくなる危険性が高まっているのです。
場合によっては、強迫神経症やうつ病などの精神疾患である可能性もあるので、必要な時は医療機関に相談するのも一つの手段です。
「どうしよう」という言葉はより自身を追い詰めてしまうことがあるので気をつけましょう。
2-2. 自分に自信がなく周りの意見を聞いてから行動したい

自分の考えや行動に自信がなく、周囲の感情や行動を気にしてばかりいる人も「どうしよう」という言葉が口癖になっていることが多いです。
相手の意見を伺うことに神経をすり減らしてしまい、正常な判断ができていないことも多いです。
運悪く、支配的な人にマインドコントロールされてしまう危険性もあるので注意が必要です。
また、過去に、対人的な問題でトラウマを抱いている人ほど、自身を失いやすい傾向が強いので注意しなければなりません。
根本的な心の問題に向き合い、解決していくことも大切です。
そして、自分で考え、選択できることに、恐れではなく喜びを感じられる人になりましょう。
2-3. 自分の弱さに甘えて周りに頼りたい

「どうしよう」が口癖になっている人には、甘えがちで依存的な人も多いです。
自分の弱さに甘えたり、自分の至らなさを言いわけにして、周りに頼ってしまう人ほどネガティブな発言をしがちです。
あえて弱い所を見せることによって味方を増やそうとする、狡猾な手口を用いる人もいるでしょう。
あざとさやこずるい行動というのは、場合によって周囲から反感を買ってしまうこともあるので気をつけなければなりません。
自分の弱点に対して開き直るだけではなく、弱さを見つめ改善していくことも大切です。
人としての成長機会を失わないように気をつけましょう。
2-4. 自分の責任から逃れたい

「どうしよう」が口癖になっている人ほど、責任逃れをしようとしている人が多いです。
「自分ではもうどうしようもない」と諦めてしまい、最善を尽くすことを怠ってしまいます。
時には、問題を投げて、周りに押し付けてしまうこともあるでしょう。
そうした無責任な対応によって、信頼が失墜してしまう場合もあるので注意が必要です。
関わったことは、最後まで責任をもってやり遂げる誠実さを見せることが大切です。
3. 「どうしよう」が口癖の人の特徴

3-1. 臆病

「どうしよう」が口癖の人は、臆病な場合が多いです。
物事や未来に対しての不安が強く、ネガティブな感情にとらわれてしまいがちです。
勝手な憶測によって否定的になり、自分の可能性をも閉ざしてしまうことがあるので気をつけましょう。
慎重になることが重要な場合もありますが、過度な臆病さによってチャンスを逃さないように注意しましょう。
自身の不安に負けずに行動していくことが大切です。
3-2. 自分に自信がない

「どうしよう」が口癖の人は、自分に自信がない場合が多いです。
自分の考えや行動に自信が持てず、いつもびくびくしています。
時には、周囲に選択を委ねてしまうこともあるでしょう。
選択を放棄することは、一時の安息をもたらすこともありますが、後になって後悔をもたらすものでもあるます。
自分の意思決定を信じて行動することが、未来を切り開いていくのです。
3-3. 無責任

「どうしよう」が口癖の人は、不安や恐怖に負けてしまい、自分の責任を放棄してしまいがちです。
周囲に問題や課題を丸投げして、逃げてしまうことがあるので気をつけましょう。
関わったことに対して責任を持てない人は、すぐに信頼を失ってしまうので注意が必要です。
良識ある大人になるためには、最低限の責任を果たすように心がけていかなければならないのです。
3-4. リーダーとしての素質が低い

「どうしよう」という言葉は頼りなさを印象付ける場合が多いです。
それゆえに、「どうしよう」という言葉が口癖の人は、リーダーとしての素質が低いと言えるのです。
ですから、リーダーとして信頼されたいのであれば、自分の不安や恐怖を簡単に吐露しないように気を付けることも重要なのです。
毅然とした態度で問題に立ち向かっていきましょう。
3-5. 周りを気にし過ぎている

「どうしよう」が口癖の人は、周りの感情や動きを気にし過ぎている場合が多いです。
余計な敵を作りたくない、仲間外れになりたくないといった恐れが、ネガティブな発言を生んでしまうのです。
人間関係においてトラウマを抱いている人も少なくないと言えるでしょう。
しかし、そのネガティブさがかえって敵を作ることにも繋がってしまうので気をつけましょう。
また、支配的な人な人に都合よく利用されてしまう危険性もあるので注意しなければなりません。
3-6. 繊細

「どうしよう」が口癖の人は繊細な人が多いです。
優しさや気配りに繋がることもありますが、神経質すぎてストレスを抱えやすい性格とも言えます。
余計に問題を抱え込みがちなので、些細なことを気にしないメンタルを鍛えることも大切です。
また、細やかすぎるこだわりを周囲の人たちに押し付けないように気をつけましょう。
3-7. 依存的

「どうしよう」が口癖の人は、他人に甘えがちで依存的です。
自分の行動やふるまいに責任が持てず、いつまでも他者を頼ってしまいます。
また、経済面や生活面においても不安が多く依存的ば場合もあります。
責任ある大人になれるように、性格的にも金銭的にも自立することが大切です。
3-8. 動揺しやすい

「どうしよう」が口癖の人は、精神的に動揺しやすい側面を持っています。
打たれ弱く、問題やトラブルが起きるとすぐに心が揺れてしまい、不安や恐怖が露わになります。
その動揺は周囲にも伝わってしまい、さらなる不安を煽る結果にもなるので気をつけなければなりません。
また、心の揺れに乗じて漬け込むような人も表れるので気を付けて生活する必要があるでしょう。
3-9. 感情的

「どうしよう」が口癖の人は、理性よりも感情で動いてしまう人です。
感情が大切な場合もありますが、感情に飲まれ、自分を見失ってしまっては元も子もないのです。
自分の感情によって周囲を振り回さないように気をつけましょう。
そして、真の思いやりというのは、身勝手なものではなく、冷静さや客観性を伴うものなのです。
3-10. 自己中心的

「どうしよう」が口癖の人は、自己中心的でわがままな場合が多いです。
自分の思うように物事が進まないと、だだをこねたり、騒いだりしてしまいがちです。
その身勝手さによって周りを巻き込んでしまいがちなので気をつけましょう。
4. 「どうしよう」を口癖にするデメリット

4-1. 自身のネガティブな気持ちを強めてしまう

「どうしよう」が口癖になると、自分をネガティブな方向へと導いてしまいます。
言葉の影響力というのは強く、悪い言葉は自分の感情や行動を抑制したり、縛ることに繋がってしまうのです。
結果として、自分の可能性すら狭めてしまう危険性もあるので気をつけなければなりません。
ですから不安になった時「どうしよう」という言葉を使ってしまうと、より自分を追い詰めてしまうことになるので気をつけましょう。
問題にぶつかった時は、冷静に考えることや、あえてポジティブな言葉を使うことも大切なのです。
前向きな発言によって、明るい方向へと生き方の舵を変えていくことが大切なのです。
4-2. 周りの不安を煽ってしまう

言葉の影響力というのは、自分自身だけではなく周囲にも広く強く及んでしまうものです。
「どうしよう」という言葉が口癖になってしまうと、周りの人たちの不安を煽ってしまうことに繋がるので気をつけましょう。
特に、リーダーたる人は、不安を吐露しすぎず、感情をコントロールすることが、チームや組織の士気を保つのに繋がります。
恐れを感じても、口に出さず、毅然とした態度を見せることも重要なのです。
4-3. 冷静さを欠き失敗してしまう

「どうしよう」という言葉は、感情を先行させてしまう言葉です。
それゆえに、理性的な判断ができなくなり、失敗を招くことに繋がるので気をつけましょう。
「どうしよう」ではなく、「どうすべきか」冷静に考え、選択することでリスク回避することができるようになるでしょう。
4-4. 頼りない印象を作ってしまう

「どうしよう」という言葉は、途方に暮れてしまっている印象を作ってしまいまいます。
それゆえに、頼りなく、か弱い印象を持たれる結果になってしまうのです。
上に立ち信頼を集める人ほど、「どうしよう」という言葉を軽々しく言ってはいけないのです。
また、弱い印象によって、悪い人たちにつけこまれる場合もあるので気をつけましょう。
4-5. 感情的で子供っぽい印象を持たれてしまう

「どうしよう」ということ言葉は、感情的で弱い印象のある言葉です。
それゆえに、責任のない子供のような雰囲気が出てしまう場合もあるので注意しましょう。
子供のような発言ばかりしていると、信頼や信用を失う結果に繋がりやすくなるので、発言や態度には慎重になければなりません。
5. 「どうしよう」という口癖を改善するコツ

5-1. 冷静に考えて行動する

「どうしよう」という言葉は、自分自身を感情的にし、ネガティブな方向へと追い詰めてしまいます。
まずは、その悪い言葉を口にするのではなく、冷静かつ理性的に考え行動するように努めていきましょう。
口先だけの人と言うのは大成しないものです。
不安な言葉にとらわれるのではなく、冷静な行動を示すことによって周囲からの信頼を獲得することができるようになるでしょう。
自分の明るい人生のためにも、考えることや行動することを放棄しないように気を付けていきましょう。
5-2. 不安の原因を解決する

「どうしよう」と口にしてしまう人ほど、根本的な問題に気付けていない場合が多いです。
どうして不安を感じるのか、どうして恐れを抱くのか、その原因を探り解決していくことが大切です。
特に、過去における問題に対するトラウマが自分自身を縛っている可能性が高いです。
ネガティブな感情や記憶から解放されることによって、よりよく生きることができるようになるでしょう。
5-3. ネガティブな気持ちや状態をアピールしようとしない

「どうしよう」が口癖になっている人ほど、自分の弱さやネガティブさをアピールしている傾向が強いです。
ネガティブな自己表現というのは、人間関係をネガティブなものに捻じ曲げてしまいます。
自分の弱さを見せつけ、悲劇のヒロインや主人公を演じる人を、誰も快くは思わないのです。
また、その弱さにつけこもうと悪い考えをもった人も引き寄せてしまうので注意が必要です。
歪んだ自己アピールをするのではなく、正々堂々と自分や相手と向き合うことが良い人間関係を構築することに繋がるでしょう。
そして、自分の短所を改善し、長所を伸ばそうと努力していくことも大切です。
5-4. 素直に助言や手助けを求める

「どうしよう」という言葉は、誰かを頼る言葉ですが、自分から頭を下げる意味が含まれていない場合もあります。
ただ泣きつけば許される、相手から助けてくれるという思いこみが「どうしよう」という言葉を生んでしまうのです。
そうした思いこみを改め、意地を張らずに、頭を下げて依頼したり、願い出るように心がけていきましょう。
素直さと誠実さによって、きっと手を貸してくれる人や助言してくれる人が現れるでしょう。
5-6. 自分の思い通りに物事が進むと思いこまない

「どうしよう」という言葉を使っている人ほど、実は自己中心的な考えにとらわれていることが多いです。
「自分だけは大丈夫」「自分だけは許される」といった身勝手な論理から、問題やトラブルを引き起こしてしまいがちです。
まずは、自分の中にある、高慢で傲慢な考え方や、特権意識を排除することが重要だと言えるでしょう。
そして、いつでもトラブルや問題は起こり得るということを認識した上で、冷静にふるまうことが大切です。
思いこみに陥るのではなく、常に客観的に物事を捉えるように努めていきましょう。
5-7. 問題が起きる前にさまざまな手立てを打つ

「どうしよう」という言葉を使う人ほど、問題やトラブルに対して冷静な対応ができていません。
また、予測する力が弱いために、前もって手立てを打つことができていない場合も多いです。
さまざまなリスクを考え、準備をしたり、備蓄をしたりするように心がけていきましょう。
ポジティブなことは大切ですが、日和見ならないように、計画的に行動することも大切です。
5-8. 思ったことをすぐに口にしない

「どうしよう」と言ってしまう人ほど、思ったことがすぐに言葉や表情に出てしまいがちです。
また、それゆえに問題発言や失言も増えてしまう傾向が強いです。
ですから、感情的にならず、時には想いや言葉を自分の内にとどめたり、飲み込んだり、セーブすることが重要なのです。
TPOを無視して言いたい事ばかりいっていると、責任ある大人として認められないので注意しましょう。
良識と気配りを忘れずに、言葉を選ぶように気を付けていきましょう。
まとめ

「どうしよう」という言葉は、自分をネガティブに追い詰めるだけではなく、周りの人の不安を煽る可能性を持っています。
素直な気持ちを吐露することも大切ですが、時には感情をセーブして冷静に振る舞うことも大切です。
特に、自身がリーダーである場合は、不安な様子を見せるのではなく毅然とした態度をとることで、周りの人たちを動かすことができるでしょう。
動揺せずに、理性的な行動ができるように心がけていきましょう。
「どうしよう」という言葉は、自分を不安にさせてしまうだけではなく、周囲にもネガティブな影響を与えてしまう言葉です。
「どうしよう」が口癖になっている人は、周囲を動揺させてしまうために信頼や信用を獲得することができません。
ですから、そうしたネガティブな口癖を直していくことが重要なのです。
ここでは、「どうしよう」が口癖の人の心理や、特徴、「どうしよう」などのネガティブな口癖を直す方法などについて紹介します。
この記事を参考にして、ポジティブに行動や発言できる人になりましょう。
1. 「どうしよう」の意味

「どうしよう」とは、手段や対応に困ったり、途方に暮れたりした時の心境を表現する言葉です。
「どうしよう」と思ったり、口にしてしまうことは誰でもあります。
しかし、いつもそうした発言をすると、自分の不安や恐れをコントロールできず、より不安感を抱くようになってしまいます。
また、周りの人の不安を煽り、よりネガティブな雰囲気を作ってしまう危険性も高くなるのです。
それゆえに、「どうしよう」という言葉を口癖にしないことが重要なのです。
2. 「どうしよう」が口癖の人の心理

2-1. 不安や恐れをコントロールできない

いつも「どうしよう」と言ってしまう人は、自身のネガティブな感情をコントロールできていない場合が多いです。
何か問題が起きた時、不安や恐れが先行してしまい冷静な判断ができなくなってしまうのです。
また、起きてもいないトラブルを杞憂して、「どうしよう」という言葉が出てきてしまう場合もあります。
いずれにせよ、不安にとり憑かれ、正常な行動ができなくなる危険性が高まっているのです。
場合によっては、強迫神経症やうつ病などの精神疾患である可能性もあるので、必要な時は医療機関に相談するのも一つの手段です。
「どうしよう」という言葉はより自身を追い詰めてしまうことがあるので気をつけましょう。
2-2. 自分に自信がなく周りの意見を聞いてから行動したい

自分の考えや行動に自信がなく、周囲の感情や行動を気にしてばかりいる人も「どうしよう」という言葉が口癖になっていることが多いです。
相手の意見を伺うことに神経をすり減らしてしまい、正常な判断ができていないことも多いです。
運悪く、支配的な人にマインドコントロールされてしまう危険性もあるので注意が必要です。
また、過去に、対人的な問題でトラウマを抱いている人ほど、自身を失いやすい傾向が強いので注意しなければなりません。
根本的な心の問題に向き合い、解決していくことも大切です。
そして、自分で考え、選択できることに、恐れではなく喜びを感じられる人になりましょう。
2-3. 自分の弱さに甘えて周りに頼りたい

「どうしよう」が口癖になっている人には、甘えがちで依存的な人も多いです。
自分の弱さに甘えたり、自分の至らなさを言いわけにして、周りに頼ってしまう人ほどネガティブな発言をしがちです。
あえて弱い所を見せることによって味方を増やそうとする、狡猾な手口を用いる人もいるでしょう。
あざとさやこずるい行動というのは、場合によって周囲から反感を買ってしまうこともあるので気をつけなければなりません。
自分の弱点に対して開き直るだけではなく、弱さを見つめ改善していくことも大切です。
人としての成長機会を失わないように気をつけましょう。
2-4. 自分の責任から逃れたい

「どうしよう」が口癖になっている人ほど、責任逃れをしようとしている人が多いです。
「自分ではもうどうしようもない」と諦めてしまい、最善を尽くすことを怠ってしまいます。
時には、問題を投げて、周りに押し付けてしまうこともあるでしょう。
そうした無責任な対応によって、信頼が失墜してしまう場合もあるので注意が必要です。
関わったことは、最後まで責任をもってやり遂げる誠実さを見せることが大切です。
スポンサーリンク