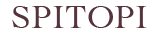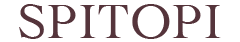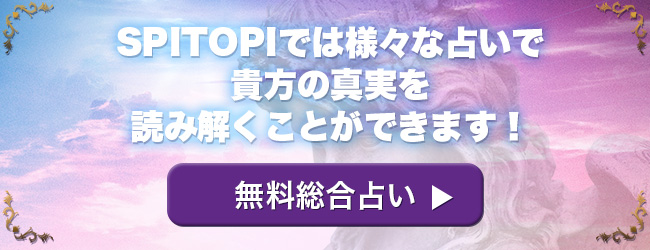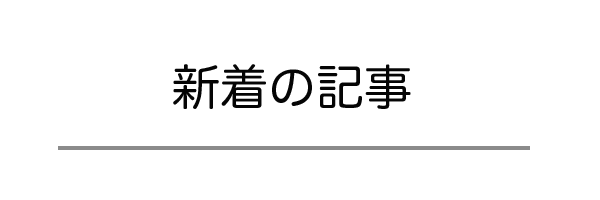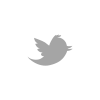ふと気が付けば体を支配している言われなき怒り、それがイライラです。
嫌なものですが、現代日本においてイライラを感じないことはできないと言えるでしょう。
今回は、イライラしてしまう状況やデメリットの解説、解消方法についてご紹介します。
- イライラとは?
- イライラする時に多い状況
- イライラするデメリット
- イライラするメリットはない
- イライラするのは仕方がない
- イライラを解消するコツ
- まとめ
1. イライラとは?

イライラとは、辞書上では「思い通りにならなかったり不快なことがあったりして神経が昂るさま」とあります。
そんなイライラを軽減する解決策について公開は書いていきます。
2. イライラする時に多い状況

イライラする状況は、たいていが自分が一生懸命に行っていることに対して起こります。
それだけまじめに取り組んでいるからなのですが、悲しいかな頑張れば頑張るほどイライラを感じるシーンは増えてきてしまいます。
代表的な状況3つについて解説します。
2-1. 仕事

仕事をしている時は、イライラを感じやすいと言えます。
イライラとは、自分の思うようにならなかったり、自分の考える進行が妨げられそうなときに感じる感情です。
仕事において、そのようなことは日常茶飯事。
むしろ、イライラを感じないで済むことの方が少ないでしょう。
しかし、仕事の中でも比較的、営業、営業アシスタントなどの仕事がイライラを感じやすく、部署で言うなら営業、人事などがそれに相当します。
逆にマイペースでできる事務やシステムエンジニアなど、自分の裁量が最大限活かせる仕事だと、イライラを感じることも少ないと言えます。
2-2. 子育て

子育てはイライラを感じる最たるものです。
それは、こどもが全く思い通りにならないから。
生まれたばかり〜幼年期は、ミルクや睡眠の状況に振り回され、小学校〜青年期は精神的な要因で疲弊します。
子育てとは、一時的とは言え別人格であるこどもの全責任を肩代わりし、また将来的な面からしつけも行わなければいけないという大変ストレスフルなものです。
自分のしたことに責任を負うのは簡単ですが、別人格であるこどもは思ってもみないことをしでかします。
しかし、責任の所在はすべて親にあります。
また、身の安全さえ守っていればいいというわけではなく、適切な指導・しつけをする必要もあります。
ただ、これを甘んじて受けるこどもはいません。
良かれと思って叱ったことに反発をくらうことは日常的に起こります。
子育てとは、自分の思うとおりにならないこと。
それはイライラの最大の原因です。
2-3. 彼氏や彼女

自分の思うとおりにならないことがイライラの発生源です。
彼氏・彼女の関係性においては、相手に期待を持ちすぎることによってイライラを感じてしまうことがあります。
本当であれば大人同士の付き合いですから、相手に過度の期待はするべきではありません。
しかし、恋とはやっかいなもの。
自分の望むような愛情をかけてもらいたいと願うあまり、その度合いが自分の想像するものと違った場合にイライラしてしまうのです。
3. イライラするデメリット

イライラするデメリットは計り知れません。
たわいもない感情の波ですが、その怒りの波動は小さな波から大きなうねりとなって様々なところへ波及します。
大きく見れば社会全体にまで、その影響が及ぶこともあります。
3-1. 信頼関係が損なわれる

イライラしている人は、自分の考えが相手に伝わっていないと感じています。
そのため、相手に対して率直に怒りを感じます。
それは相手にすぐさま伝わり、気まずい状況を生み出すことでしょう。
この場合、相手はイライラを感じ取りはしますが、具体的な内容について正確に察知することは少ないです。
なぜなら、それがわかっていればイライラは発生しないからです。
相手はイライラされていることだけは悟り、しかしそれをリカバリーする方法は分かりません。
困惑し、一緒に何かを行うことに自信を持てなくなってしまうでしょう。
3-2. 効率が下がる

イライラしている時に行う作業は、遅々として進まないものです。
特に、対人間ではなく、例えばパソコン上のシステムであったり、その他ビジネスツールに対してイライラを感じた場合、それを使っての作業は苦痛極まりないものになります。
本来1時間未満でできる作業が数時間かかってしまったり、できたと思っても大量のミスが発生したり。
イライラしている時の作業効率は驚くほど低く、それによりさらにイライラが増幅するという負のスパイラルが発生します。
3-3. 自分の時間が楽しめない

仕事や子育てなどでイライラしていると、例え自分の時間を持ったとしてもその余波で気分が悪いまま…ということもよくあります。
これは、自分の時間を持ったと思っても、頭の中はいまだにそのイライラした事柄から離れられていないために起こります。
そのため、本来の意味では自分の時間とは言えません。
プライベートタイムとは、普段の雑事から完全に切りはなされ、解放感を味わうためのものだからです。
イライラした気持ちを引きずってしまう場合、本当の自分の時間をもつことはできないのです。
3-4. 他者に威圧感を与える

怒りやいら立ちを感じている人のそばで、リラックスできる人はいません。
特に自分の立場が相手より上、例えば職場では上司の立場にあったり、家庭では母であったりする場合、相手に与える威圧感は相当なものです。
立場が下でも、きちんとその不快感を伝えてくれる相手なら改めようもあるのですが、日本の社会は上下関係に比較的厳しい環境です。
どちらかと言えばイライラをぶつけられた方が何か改めなければいけないのでは?という風潮すらあります。
これは大変なとばっちりであり、他人にストレスを与える行為です。
そのイライラが他者に伝染し、さらにイライラを増やしてしまうことになりかねません。
3-5. こどもの性格形成に影響がある

こと、家庭という小さい社会において、親の存在は絶対です。
こどもは小さいうちは親に養育されなければならず、その判断や指示にはほぼ間違いなく従わなければなりません。
そういった状況の中、親がイライラしていると、こどもは委縮し、恐怖を感じます。
精神的にも未熟ですから、なぜ親がイライラしているかを推し量ることはできません。
こどもの考える世界は自分か、親かくらいのものですから、一生懸命小さな頭で考え、親がイライラしているのは自分が悪い子だからだ、という考えに至ります。
親も仕事が忙しいんだろうとか、体調が悪いんだろうとか、そういう複合的な思考をすることは、大人になってからでないとできないのです。
自分が悪い子だと思い込んだこどもは、自分の意見が言えず、嘘をつくことで身を守るこどもになってしまいます。
3-6. 身体にも悪影響

イライラし続けることは、自分の体にも影響があります。
笑顔であったり、笑うことというのは、身体にも良い影響があると言われます。
気のせいでは決してなく、笑うことによりあるホルモンが増加し、免疫力が向上するとの学説もあります。
その意味で言えば、イライラすることが体に悪いのは自明の理です。
不満をため込んでいると便秘になりやすい、怒りばかり感じていると下痢になりやすいとはよく言います。
また、イライラした後に頭痛や胃痛を感じることもよくあります。
感情と体調は切っても切り離せないもの。
イライラした精神を抱えていれば、当然体にも悪影響があるのです。
3-7. 自分に優しくできない

他者に優しくできる瞬間というのは、自分に余裕のある時です。
当然ながら、イライラしながら他人に優しい行為をすることはできません。
そしてその対象は、最も身近な他人、自己に対しても適用されます。
自分に優しくできないことは、自己肯定感の低下、また自尊心の低下につながります。
そうでなくてもイライラしている時は疲れていることが多いはず。
その上、そんな疲弊した自分に優しくできないのであれば、癒される瞬間がありません。
その結果、さらに心的な疲労をため込んでしまうことになります。
3-8. ヘイトや差別など社会にも影響を及ぼす
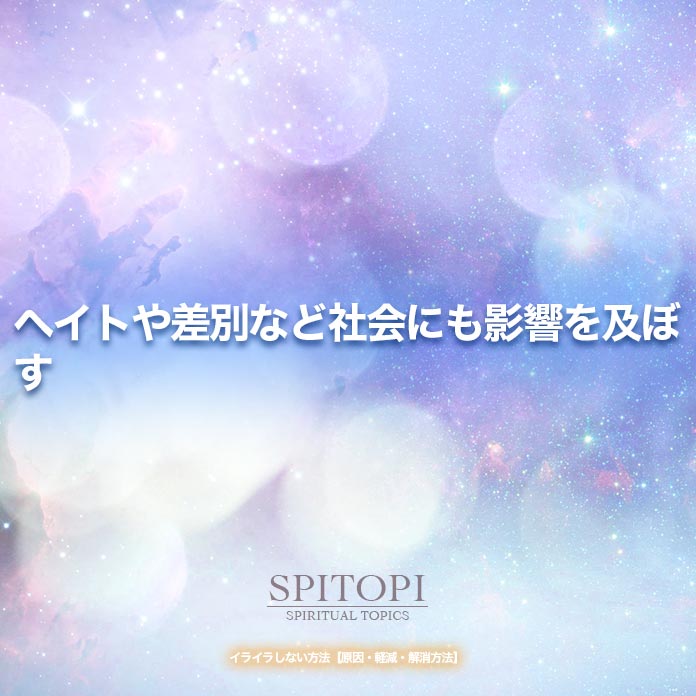
イライラは個人、また複数人の問題だけではありません。
そのイライラが溜まり、噴出したものの最たるものが差別です。
人と人の個性を尊重しあい、労わりあうことができれば、差別は生まれません。
しかし、ささいなイライラから、普段は許せることが鼻につくことがあります。
そんな時人間は、自分がイライラしているから許せないのではなく、なにか許せない理由を探します。
その時導き出されるのが、人種であったり宗教であったりするのです。
イライラからもたらされるヘイトの特徴は、言われなき差別をすることです。
理由があっての弾劾は、イライラからは発生しません。
いちゃもんのような差別が増幅し、最終的には社会問題にまで発展するのです。
4. イライラするメリットはない

イライラすることに、メリットはないと断言できます。
イライラとは、自分の考えを相手にうまく伝えられず、コミュニケーションの断絶が起こることから始まります。
コミュニケーションがうまくいっていないのですから、それ以後の事柄がうまくいくこともほぼありません。
ただただいたずらに怒りを振りまくばかりで、イライラすることに得なことは全くないと言えるでしょう。
5. イライラするのは仕方がない

">
イライラを軽減するには
イライラする気持ちは、仕事や、子育てに一生懸命だからこそ起こります。
仕上げたいプロジェクトがある時、良かれと思ったしつけをする時。
そんな時に相手の行動でそれが阻害されると、どうしてもイライラを感じてしまいます。
しかし、そんなイライラは計画の遂行にむしろ悪影響です。
イライラを軽減し、合理的に物事を進めましょう。
5-1. 他人に期待しない

イライラするのは、他人に期待をかけすぎるから。
そのため、イライラを感じたらまず、自分が他人に過度の期待をかけていたことを思いなおしましょう。
自分でできることは自分でやるという認識を持ち直し、他人がミスをすることなどに寛容になりましょう。
本来、適切な期待は人間関係に不可欠ですが、それでイライラするならそれは期待しすぎだったということ。
しかし期待の度合いは、その瞬間だけでは決まりません。
時間が経過すれば、相手がそのレベルの要望に応えてくれる時も来るかもしれません。
現在の期待が過度だったということはしっかりと認識し、未来にはそれにこたえてくれるかもしれない、と考えなおしましょう。
5-2. 自分の思い通りになると思わない

自分と他人が違うことをしっかりと認識しましょう。
仕事で長く付き合っていたり、こどもと密に接していると、ともすれば相手が別人格であることを忘れてしまうことがあります。
そういった時、相手が自分の想像通り動かなかった場合にイライラを感じてしまうのです。
これは時間の流れでよくあることですし、ある意味で自然な流れであるとも言えます。
そのため、イライラを感じた時はチャンスと考え、自分と相手の線引きをしっかり考えなおしましょう。
この作業は一度やればいいというものではなく、イライラを感じたら都度行うべきです。
その作業によって、相手との関係が修正され、長く付き合えるようになるでしょう。
6. イライラを解消するコツ

イライラは、大変不合理なものではありますが、逆に言えば自分に対するアラームとも言えます。
疲れや気持ちの落ち込み、焦りなど、イライラした時には相手より、自分に原因があることも多いものです。
自分をしっかりと癒すチャンスだと思いなおし、自分を休ませてあげるようにしましょう。
イライラを解消するコツを2つご紹介します。
6-1. 自分の時間を大切にする

ゆっくりと自分の時間はとれていますか?
休憩には、仕事や今思い悩んでいることを頭から離す必要があります。
ふだんいかない場所へ旅行へ出かけたり、いつも食べないような料理にチャレンジするなど、通常状態から切り替えられるようなことをするのが効果的です。
その時、できるだけスマホやPCは家に置いていくようにしましょう。
持っていくときも、起動は時間を決めるなど、だらだらしないことを心がけます。
スマホなどは大変便利なガジェットですが、それにより仕事とプライベートの切り替えが難しくなったのも事実。
せっかくの休暇ですから、仕事のにおいを感じさせるものは一切見ないようにしたいですね。
6-2. 疲労に種類は無いと認識する

仕事疲れ、育児疲れ、また季節的に気温のため疲れていたり、体調不良によって内臓が披露していたり…。
疲労には様々な種類は存在します。
しかし、それらを別々に考えるのはやめましょう。
どんな理由であれ、疲労は疲労です。
仕事も育児もうまくいっている、それなのになにかイライラする…という場合、単に夏の暑さに参っているだけかもしれません。
気候も良く健康でも楽しく過ごせないという時は、全く違う疲労をため込んでいるのかもしれません。
本来人間の感情とはシンプルなものです。
疲れているからイライラするんだ、それを忘れないだけでも、仕事や育児の不要なイライラが減るでしょう。
まとめ

イライラするということは、人間の持つ自然な感情のひとつです。
そればかりに支配されてしまうと自分も疲れてしまいますが、イライラを封じようとするのは不自然です。
イライラした自分を嫌わず、自然なものと受け止めることも必要なことです。
逆にそうすることにより、なぜかイライラが消えてしまうことすらありますよ。
ふと気が付けば体を支配している言われなき怒り、それがイライラです。
嫌なものですが、現代日本においてイライラを感じないことはできないと言えるでしょう。
今回は、イライラしてしまう状況やデメリットの解説、解消方法についてご紹介します。
1. イライラとは?

イライラとは、辞書上では「思い通りにならなかったり不快なことがあったりして神経が昂るさま」とあります。
そんなイライラを軽減する解決策について公開は書いていきます。
2. イライラする時に多い状況

イライラする状況は、たいていが自分が一生懸命に行っていることに対して起こります。
それだけまじめに取り組んでいるからなのですが、悲しいかな頑張れば頑張るほどイライラを感じるシーンは増えてきてしまいます。
代表的な状況3つについて解説します。
2-1. 仕事

仕事をしている時は、イライラを感じやすいと言えます。
イライラとは、自分の思うようにならなかったり、自分の考える進行が妨げられそうなときに感じる感情です。
仕事において、そのようなことは日常茶飯事。
むしろ、イライラを感じないで済むことの方が少ないでしょう。
しかし、仕事の中でも比較的、営業、営業アシスタントなどの仕事がイライラを感じやすく、部署で言うなら営業、人事などがそれに相当します。
逆にマイペースでできる事務やシステムエンジニアなど、自分の裁量が最大限活かせる仕事だと、イライラを感じることも少ないと言えます。
2-2. 子育て

子育てはイライラを感じる最たるものです。
それは、こどもが全く思い通りにならないから。
生まれたばかり〜幼年期は、ミルクや睡眠の状況に振り回され、小学校〜青年期は精神的な要因で疲弊します。
子育てとは、一時的とは言え別人格であるこどもの全責任を肩代わりし、また将来的な面からしつけも行わなければいけないという大変ストレスフルなものです。
自分のしたことに責任を負うのは簡単ですが、別人格であるこどもは思ってもみないことをしでかします。
しかし、責任の所在はすべて親にあります。
また、身の安全さえ守っていればいいというわけではなく、適切な指導・しつけをする必要もあります。
ただ、これを甘んじて受けるこどもはいません。
良かれと思って叱ったことに反発をくらうことは日常的に起こります。
子育てとは、自分の思うとおりにならないこと。
それはイライラの最大の原因です。
2-3. 彼氏や彼女

自分の思うとおりにならないことがイライラの発生源です。
彼氏・彼女の関係性においては、相手に期待を持ちすぎることによってイライラを感じてしまうことがあります。
本当であれば大人同士の付き合いですから、相手に過度の期待はするべきではありません。
しかし、恋とはやっかいなもの。
自分の望むような愛情をかけてもらいたいと願うあまり、その度合いが自分の想像するものと違った場合にイライラしてしまうのです。
スポンサーリンク