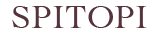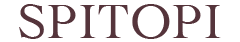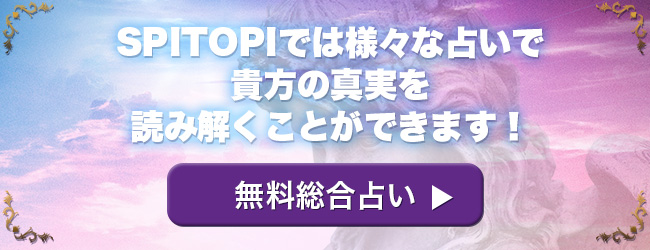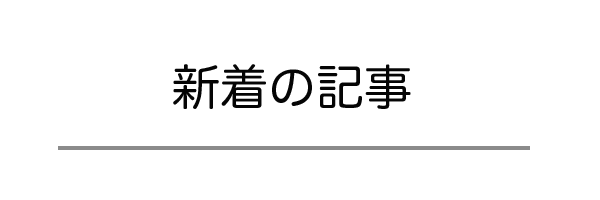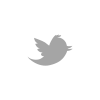アザミの花は独特の形をしています。実は多数の筒状の花が集まって1つの花を形成しており、その中心にめしべとおしべがあります。
太い茎に付いた葉は深い切れ込みがあり、縁にトゲがあるので、触れる時は気を付けましょう。
色は一般的には綺麗な赤紫色を思い浮かべますが、他にも紫や白のアザミもあります。
夏から秋に掛けて花を咲かせるアザミですが、古来から私たちの身近な所に咲いていました。
また、ヨーロッパでは2000年以上も前からアザミの種子を肝臓や消化器官の民間薬として使っていました。
そして、現在ではハーブの1種として楽しまれています。
- アザミとはどんな花?
- アザミの花言葉
- アザミの色は何色?
- アザミの名前の由来
- アザミの開花時期
- アザミを育てる時のポイント
- 種類(原種・園芸品種)
- まとめ
1. アザミとはどんな花?

実はアザミは、キク科アザミ属とそれに類する植物の総称です。
その為、和名でアザミと1種だけ特定出来る花はありません。
原産は北半球全般で、世界中に300種類以上のアザミの種が確認されています。
そのうち日本原産は50種類とも100種類とも言われますが、世界中のアザミの1/3が日本固有のものです。
また自然の中では種同士が自然交配して雑種が出来ることも多く、分類が難しい植物です。
草丈は30cm~120cmと、種に依ってこれだけの差があります。
1-1. アザミは強くて丈夫

昔から自生していた花なので、耐暑性も耐寒性も強くて丈夫です。
茎は太くて固く、葉にはトゲ状の縁を持つアザミですが、花は面白い形をしています。
頭状花序(とうじょうかじょ)という形態で、主にキク科の花に見られるもので、多数の花が集まって1つの花を形成しています。
それぞれの花からおしべとめしべが棒状に付き出すので、あの針山の様な形を作っているのです。
花の後の種子は白く、タンポポの様に長い冠毛があります。
兎に角種類の多いアザミですが、日本で最も一般的にアザミと呼ばれ、栽培されているのは「ノアザミ」で、本州から沖縄まで広く分布しています。
1-2. アザミの伝説

ヨーロッパでも古くからあったことは先述しましたが、スコットランドではアザミは国花に制定されています。
これは、アザミのトゲが敵であったノルウェー軍から国土を守ったという由来から来ています。
ノルウェー軍が夜襲を仕掛けた時、足音を立てない様に裸足で進軍していました。
ところが、そこにはアザミが一面に生えていたのです。
暗闇の中でアザミのトゲを踏んでしまったノルウェー軍は思わず叫び声を上げてしまい、その声でスコットランド軍は敵襲に気づき、勝利を収めたということです。
1-3. アザミのおいしい食べ物

天ぷら

アザミの葉を天ぷらにします。
食べるとき、稀にトゲが刺さることがあるのでよく噛んで頂きましょう。
アザミのお味噌汁

アザミの葉は山菜の中ではクセが無いのですが、苦みがあるので、苦手な方は葉を茹でてから水に10分程浸すと苦みが和らぎます。
アザミの葉を食べやすい大きさに切ります。
鍋にだし汁を入れ、豚肉とうち豆、アザミの葉を入れて火が通ったらお味噌を溶いて出来上がりです。
アザミのお浸し

アザミを良く洗います。
たっぷりのお湯に塩を大さじ1杯位入れて茹でます。
しんなりしてきたら出来上がりです。
冷水に浸けると綺麗な緑色がもちます。
海苔を振り掛けて醤油で頂くのが美味しいです。
アザミの根は「ヤマゴボウ」とも呼ばれて販売されています。
アクを抜いた上できんぴらや味噌漬けにすると美味しいです。
2. アザミの花言葉

アザミは3月19日、4月19日(アザミ)、6月19日(ノアザミ)9月18日、10月21日の誕生花です。
2-1. 「独立」

トゲや、花のすぐ下のがくのトゲなどが他を寄せ付けない印象を与えるアザミならではの花言葉ですね。
自分の身は自分で守って生きていく、という意味となるのでしょう。
2-2. 「報復」

ちょっと怖い花言葉ですが、これはスコットランドで付けられたのが由来です。
攻め込んできた敵を、そのトゲで見事に追い返したアザミでしたから、「独立」と共に敵に勝った(=報復した)ことからアザミを讃える意味で付けた花言葉の様です。
2-3. 「厳格」

これもはアザミのトゲと関係があるのでしょう。
花や茎は食べたりお茶として飲んだり出来ますが、そう簡単に摘ませてくれないアザミをこの花言葉で例えたのでしょうか。
また、スコットランドに敵軍を寄せ付けなかった花だけに、その姿勢が「厳格」というイメージを持たせたのかもしれません。
2-4. 「触れないで」

もうこれはどう考えてもアザミのトゲからきた花言葉ですね。
でも、この花言葉にはとても優しさを感じます。
アザミは「私にはトゲや痛い葉があるの。
触れたら怪我をするわ。
触れるなら気を付けて」と、見る人に注意してくれているように思えませんか。
アザミのトゲもバラのトゲも、花にとっては好きで付いているものではないでしょうから。
3. アザミの色は何色?

アザミは赤紫色が一般的ですが、他にも紫、白、ピンク、赤の花があります。
白は割と珍しいので、見られたらラッキーですね。
赤もショッキングピンクに近い感じの色合いで華やかで可愛い色です。
ピンクはピンクそのものの色です。
紫は薄めの色でおとなしく上品な感じを受けます。
4. アザミの名前の由来

アザミの名前の由来は、「驚かせる」「興ざめする」という意味の「あざむ」から名づけられたと言われます。
鮮やかな色の花につい手を伸ばすと、アザミのトゲに驚き、興ざめすることから付いたというのが通説です。
また、沖縄地方ではトゲのことを「アザ」と言うことから、トゲの多い草という意味の「アザギ」がアザミに変化していったのではないかとも言われています。
やはり、アザミの最大の特徴はそのトゲなのですね。
5. アザミの開花時期

一番一般的なノアザミの開花時期は4月~10月までです。
他に、フジアザミは8月~9月の夏の終わりから秋にかけて、ナンブアザミは8月~10月の間、キセルアザミは9月~10月とどちらかと言うと夏から秋に咲く花です。
6. アザミを育てる時のポイント

6-1. 植え付けの時期

植え付けは2月~3月が適切です。
種蒔きは春蒔きと秋蒔きが出来ます。
春蒔きは2月~3月に種を蒔き、夏に花を咲かせます。
秋蒔きは9月~10月頃種を蒔き、翌年の春に花を見ることが出来ます。
6-2. 苗と種蒔き

苗

アザミは大きくなる物だと120cm位に成長します。
ですから、苗は30cm以上間隔を開けて地植えしましょう。
鉢植えの場合は直径18cmの鉢に1株が目安です。
この植木鉢のサイズは大体5~6号サイズになります。
種蒔き

アザミの種蒔きは地方で異なります。
温かい地方では秋蒔きが適しています。
少し寒冷な地方や高地では春蒔きにしましょう。
どちらも種子が古くなっていると発芽しないので、新しい種を蒔きましょう。
アザミは風通しの良い、日向を好みます。
また、湿地に生えるので地植えするなら、乾燥しすぎる場所は避けて下さい。
6-3. 水やり

地植えの場合はひどく乾燥しなければ、水やりは必要ありません。
雨で充分育ちます。
鉢植えの場合は、土の表面が乾燥し出したら水をやりましょう。
アザミは湿地で育つので、乾燥には気を付けましょう。
また、春から秋にかけて生育するので、その間は水分を充分に与えましょう。
冬は水やりは控えて、土は乾かしがちの状態にしておくのが良いです。
6-4. 肥料

芽が出て茎が伸びてくるまでは、鉢植えは窒素・リン酸・カリウムの3大要素を含む緩効性肥料を与えて下さい。
また、月に2回程液体肥料を1000倍に薄めて追肥してやると元気に育ちます。
地植えは特に肥料をやらなくても大丈夫です。
6-5. 摘芯

アザミの花を多く咲かせる為には、摘芯を行いましょう。
摘芯で生長した芽を切り落とすことで、脇芽を増やしたり、株自体を大きく成長させることが出来ます。
この脇芽が増えると、アザミの花が沢山咲いてくれるようになります。
6-6. 害虫・病害

アザミは病気に罹りにくく、また害虫の被害もあまり受けません。
しかし、時にアブラムシが付くことがあります。
また、時にうどんこ病になることがあります。
うどんこ病は自然に治ることも多いですが、見つけたら酢や重曹を吹きかけます。
1週間に1回ずつ、治るまで吹きかけてやりましょう。
6-7. 生長途中の作業

支柱立て

品種によっては茎が倒れやすい場合があるので、そういう品種の場合は支柱を立ててやります。
花がら摘み

種を取らない場合は、交雑しない様に、花が終わったら花がらを取り除きましょう。
7. 種類(原種・園芸品種)

7-1. ノアザミ(園芸品種)

日本で最も多く栽培されている品種です。
ドイツアザミはノアザミの改良種です。
ノアザミは日本列島の日当りの良い草原や道端に生えています。
花の時期がとても長く、春から秋まで咲いています。
花の直径は3cm程で茎の先端に1~3輪付きます。
花が咲くと、根元の葉は枯れているのがノアザミの特徴となっています。
7-2. フジアザミ

日本で一番大きな花を咲かせるアザミです。
本州中部地方の山地で日当りの良い荒地などに咲いています。
草丈は50~150cm、花の直径は5cm~10cmにもなって花が咲くと垂れ下がります。
花が咲いても根元の葉が残っていて、直径1m程の範囲まで広がります。
この花は白い色もあり、シロバナフジアザミとして販売されています。
7-3. キセルアザミ(マアザミ、サワアザミ)

本州・四国・九州の山地の中の明るい湿地や川の流れのそばに生えています。
草丈は50cm~100cm。
秋に直径3cm程の花を茎の先に通常は1~2輪、下向きから横向きに咲かせます。
フジアザミやこのキセルアザミはノアザミとは違った花の咲き方をします。
こちらも花が咲いても根元の葉は枯れずに残っています。
茎に葉は殆どないか、少な目です。
トゲも小さい方です。
7-4. ナンブアザミ

東北地方から近畿地方や四国に亘って低地から高い山の草原まで生えています。
草丈は1~2mにもなり、秋に直径2cm強の花が沢山咲きます。
花は横向きに咲きます。
花が咲くと、根元の葉は枯れてしまい、新たには出てきません。
変種が非常に多い品種で、関東地方では変種の”トネアザミ(タイアザミ)”がよく見られます。
7-5. タムラソウ

本州から九州、朝鮮半島の低地から明るい高原に生えています。
アザミによく似ていますがトゲがなく、葉は羽状に裂ける特性を持っています。
草丈は50cm~120cm。
花は夏の終わりから秋に掛けて咲き、直径3cm程の花が枝分かれする細めの茎の先に付きます。
7-6. ヒゴダイ

日本列島西部(愛知県以西)、中国東部、朝鮮半島南部の丘や草原に生えています。
現在日本ではあまり見られなくなり、各地で保護活動が行われています。
夏の終わり頃に瑠璃色の花を茎の先端に付けます。
花はノアザミの様に上に向かって広がる形ではなく、ポンポンの様に丸い形です。
花の直径は5cm程あります。
7-7. オヤマボクチ

北海道西部、本州、四国に掛けて分布しています。
日当りが良く、やや乾燥気味の草原に生えています。
秋に茎の先端に直径4cm位の花を付けます。
若葉を山菜としてお餅に入れたり、そばのつなぎにする地方もあります。
7-8. ハバヤマボクチ

本州(福島県以南)、四国、九州に分布しています。
山地の日当りの良い、やや乾燥気味の草原に生えています。
秋に茎の先端に直径4cm前後の花を付けます。
葉の形が三角形に近く、葉の縁に浅く切れ込みが入っているのが特徴です。
7-9. セッラツラ・セオアネイ

フランス南西部からポルトガル北部に掛けての地域が原産です。
秋に直径2cm位の花を咲かせます。
日本では済州島タムラソウ、丹那タムラソウ、細葉タムラソウの名前で販売されています。
7-10. キルシウム・アコーレ(チャボアザミ、クキナシアザミ)

ヨーロッパから西アジアの石灰岩地の草原に生えています。
学名は「茎が無い」という意味ですが、実際キルシウム・アコーレは草丈が5~15cmととても低く、パッと見にはタンポポの様な感じです。
花は直径3cm位でノアザミと同様上を向いて咲きます。
7-11. マリアアザミ(オオアザミ)

葉に白いまだら模様がある特徴を持つアザミです。
このs広い模様がミルクがこぼれた様に見え、ミルクを聖母マリアに例える風習から「マリアアザミ」の名が付いたという説があります。
種子は4種類のフラボノリグナン類が多く含有されているので、肝細胞の修復に役立つとされています。
実際ヨーロッパでは2000年以上も前から肝臓疾患にはこのマリアアザミの種子が使われてきました。
アメリカでは、安全に摂ることが出来るハーブとして扱われています。
7-12. エキノプス・リトロ(ルリタマアザミ、ウラジロヒゴタイ)

ヨーロッパから中央アジアの草原に多く見られます。
夏に開花し、切り花としてよく用いられます。
花の色は藍青色で濃淡があるのが珍しいです。
全体的に毛が多く付いています。
セイタカヒコダイがエキノプス・リトロに似ていますが、セイタカヒコダイは花の色が白いのがセイタカヒコダイの特徴です。
まとめ

アザミは1つの品種を差すのではなく、アザミ属に属する花の総称だったのですね。
また、野生で種が混ざり合い、今では数えきれない程の品種が確認されています。
トゲが玉に瑕ですが、その花の素朴ながら凛とした美しさ、色の可愛さにはやはり惹かれます。
食用にする場合はアザミかどうかを十分確認する必要がありますが、見て楽しむ分には、細かい品種については置いておき、花の姿を愛でたいものですね。
2000年以上も前から地球に存在し、今でもアザミの全種類の1/3は日本にあるのですから、人間のすぐ横で一緒に歴史を刻んできた花だと思えば、親近感も一層増しますね。
アザミの花は独特の形をしています。実は多数の筒状の花が集まって1つの花を形成しており、その中心にめしべとおしべがあります。
太い茎に付いた葉は深い切れ込みがあり、縁にトゲがあるので、触れる時は気を付けましょう。
色は一般的には綺麗な赤紫色を思い浮かべますが、他にも紫や白のアザミもあります。
夏から秋に掛けて花を咲かせるアザミですが、古来から私たちの身近な所に咲いていました。
また、ヨーロッパでは2000年以上も前からアザミの種子を肝臓や消化器官の民間薬として使っていました。
そして、現在ではハーブの1種として楽しまれています。
1. アザミとはどんな花?

実はアザミは、キク科アザミ属とそれに類する植物の総称です。
その為、和名でアザミと1種だけ特定出来る花はありません。
原産は北半球全般で、世界中に300種類以上のアザミの種が確認されています。
そのうち日本原産は50種類とも100種類とも言われますが、世界中のアザミの1/3が日本固有のものです。
また自然の中では種同士が自然交配して雑種が出来ることも多く、分類が難しい植物です。
草丈は30cm~120cmと、種に依ってこれだけの差があります。
1-1. アザミは強くて丈夫

昔から自生していた花なので、耐暑性も耐寒性も強くて丈夫です。
茎は太くて固く、葉にはトゲ状の縁を持つアザミですが、花は面白い形をしています。
頭状花序(とうじょうかじょ)という形態で、主にキク科の花に見られるもので、多数の花が集まって1つの花を形成しています。
それぞれの花からおしべとめしべが棒状に付き出すので、あの針山の様な形を作っているのです。
花の後の種子は白く、タンポポの様に長い冠毛があります。
兎に角種類の多いアザミですが、日本で最も一般的にアザミと呼ばれ、栽培されているのは「ノアザミ」で、本州から沖縄まで広く分布しています。
1-2. アザミの伝説

ヨーロッパでも古くからあったことは先述しましたが、スコットランドではアザミは国花に制定されています。
これは、アザミのトゲが敵であったノルウェー軍から国土を守ったという由来から来ています。
ノルウェー軍が夜襲を仕掛けた時、足音を立てない様に裸足で進軍していました。
ところが、そこにはアザミが一面に生えていたのです。
暗闇の中でアザミのトゲを踏んでしまったノルウェー軍は思わず叫び声を上げてしまい、その声でスコットランド軍は敵襲に気づき、勝利を収めたということです。
1-3. アザミのおいしい食べ物

天ぷら

アザミの葉を天ぷらにします。
食べるとき、稀にトゲが刺さることがあるのでよく噛んで頂きましょう。
アザミのお味噌汁

アザミの葉は山菜の中ではクセが無いのですが、苦みがあるので、苦手な方は葉を茹でてから水に10分程浸すと苦みが和らぎます。
アザミの葉を食べやすい大きさに切ります。
鍋にだし汁を入れ、豚肉とうち豆、アザミの葉を入れて火が通ったらお味噌を溶いて出来上がりです。
アザミのお浸し

アザミを良く洗います。
たっぷりのお湯に塩を大さじ1杯位入れて茹でます。
しんなりしてきたら出来上がりです。
冷水に浸けると綺麗な緑色がもちます。
海苔を振り掛けて醤油で頂くのが美味しいです。
アザミの根は「ヤマゴボウ」とも呼ばれて販売されています。
アクを抜いた上できんぴらや味噌漬けにすると美味しいです。
2. アザミの花言葉

アザミは3月19日、4月19日(アザミ)、6月19日(ノアザミ)9月18日、10月21日の誕生花です。
2-1. 「独立」

トゲや、花のすぐ下のがくのトゲなどが他を寄せ付けない印象を与えるアザミならではの花言葉ですね。
自分の身は自分で守って生きていく、という意味となるのでしょう。
2-2. 「報復」

ちょっと怖い花言葉ですが、これはスコットランドで付けられたのが由来です。
攻め込んできた敵を、そのトゲで見事に追い返したアザミでしたから、「独立」と共に敵に勝った(=報復した)ことからアザミを讃える意味で付けた花言葉の様です。
2-3. 「厳格」

これもはアザミのトゲと関係があるのでしょう。
花や茎は食べたりお茶として飲んだり出来ますが、そう簡単に摘ませてくれないアザミをこの花言葉で例えたのでしょうか。
また、スコットランドに敵軍を寄せ付けなかった花だけに、その姿勢が「厳格」というイメージを持たせたのかもしれません。
2-4. 「触れないで」

もうこれはどう考えてもアザミのトゲからきた花言葉ですね。
でも、この花言葉にはとても優しさを感じます。
アザミは「私にはトゲや痛い葉があるの。
触れたら怪我をするわ。
触れるなら気を付けて」と、見る人に注意してくれているように思えませんか。
アザミのトゲもバラのトゲも、花にとっては好きで付いているものではないでしょうから。
スポンサーリンク