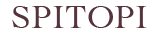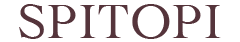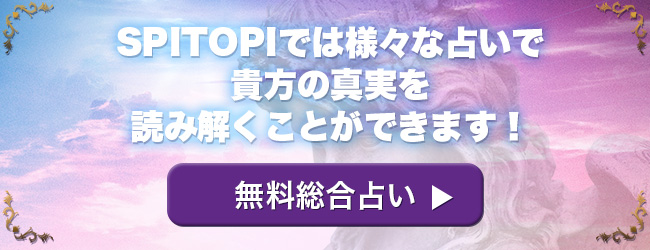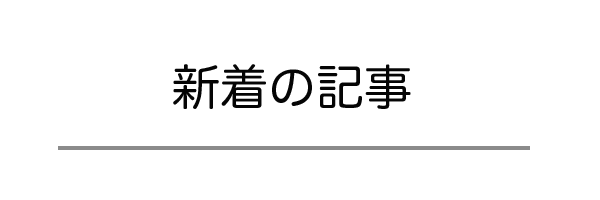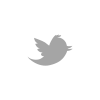藍と聞けば、藍染めを思い出しますね。
日本で古来から行われてきた染色で、美しい藍色に染まります。
また、濃い藍色と薄い藍色があるので、上手に組み合わせると面白い作品が出来上がります。
藍染めはなかなか奥深い物がありますが、今は通販で藍染めのセットが買えますから、自宅でも気軽に藍染が楽しめます。
そんな藍染めに使われる海について書いていきたいと思います
- 藍とはどんな花?
- 藍の花言葉
- 藍染めの原料になる?
- 藍の名前の由来
- 藍の開花時期
- 藍の育て方や注意点
- 種類(原種・園芸品種)など
- まとめ
1. 藍とはどんな花?

日本で言う藍とはタデアイのことで、タデ科・イヌタデ属に分類される1年草です。
紀元前から世界の各地で青い染料として利用されていました。
日本では、奈良時代から藍染めが始まり、それ以来どんどん全国に広まっていったようです。
「阿波藍」と呼ばれる徳島県産の物が最高級として江戸時代には最も好んで使われていました。
現在の徳島県である阿波藩は、藍に依って栄えていたそうです。
その後、明治時代にはラフカディオ・ハーンが「この国日本は神秘的なブルーに満ちた国」と日本の藍染めを絶賛した話が残っています。
2. 藍の花言葉

2-1. 「美しい装い」

日本人の衣服を美しく彩ってきた藍。
遠く奈良時代から現代まで続く藍染は、今では”ジャパン・ブブー”として外国でも人気があります。
やはり日本人の繊細な色への研究が、どんな人をも引きつける美しい藍色を染め出すのでしょうね。
江戸時代には戦も無くなり、木綿の生産量も増えたので民衆の間で衣裳への関心も高くなりました。
特に元禄の頃(1688年~1704年)には、藍染めの美しさが庶民を魅了し、大ブームとなりました。
そんなことから、この花言葉は付いたものでしょう。
2-2. 「あなた次第」

これは、藍染めと一口に言っても色の濃淡は本当に様々であることから付いた花言葉でしょう。
特に平安時代の宮中では女房装束(所謂”十二単”)の色の襲(かさね)には、女性達は皆夢中になって拘りました。
ですから、藍染めも、紺色から浅葱色と呼ばれる薄い青まで、何色もの青色が作られました。
あなたが好む濃さの藍色に染まりますよ、という意味がkの花言葉には込められているのではないでしょうか。
3. 藍染めの原料になる?

藍は、その葉を使って藍染めを行います。
藍の生葉染めは、刈り取ったばかりの新鮮な藍の葉に含まれている藍の色素の元となる物質(インジカン)を繊維に染みこませ、繊維の中でインジゴ(藍の色素)を発生させる染色法です。
葉の中の酵素がインジコを作り出します。
最初に生葉液に浸けたら緑色になりますが、大丈夫です。
空気に触れることに依って染料が藍色へと変化していきます。
Tシャツやコットンシャツ、ハンカチ等ただ染めるだけでなく、絞り模様を入れたりすると、よりオリジナリティが出て世界に1つの自分だけの作品になりますね。
染色する時は藍の茎は使いません。
4. 藍の名前の由来

藍の属名の学名は「Persicaria(ペルシカリア)」と言います。
これは、ラテン語の「persica(ペルシカ:桃)」を語源としており、この属の葉が桃の葉に似ていることから付いた名前です。
一方和名の藍については、その名前の由来は諸説あります。
が、一番一般的な説は、「あおいろ」を略した「あお」が音便化しものではないかというものです。
5. 藍の開花時期

藍の花芽は8月の半ばのお盆を過ぎて、涼しい風が吹き出した頃に立ち上がります。
そして8月下旬から10月いっぱい花は咲いています。
花が咲き終わるまで藍染めが出来るので、それまでは葉を刈り取ることが出来ます。
しかし、花が咲き始めると葉の色が少し変わってきます。
そして、葉の形も先端がとがってくるようになります。
それでも藍の式度が無くなったわけではありませんが、9月初旬頃は花を咲かせるのを遅らせるように、どんどん葉を刈り取ると、色素がしっかりした葉が収穫できます。
藍の花は満開を迎えると、既に花の下の方から種が出来ています。
翌年も楽しみたければ種を見つけ次第取っておきましょう。
6. 藍の育て方や注意点

6-1. 種まき

藍は広い土地が無くても、マンションのベランダでプランターで育てることも可能です。
ただ、エアコンの室外機の排気が当たるような場所は避けて下さい。
土は市販の培養土で大丈夫です。
庭に植える場合は、土をよく耕して腐葉土や元肥を混ぜておき、種は3月上旬から遅くとも彼岸の頃までに撒きます。
土に種を撒き、上から軽く土を被せ、芽が出るまでは土の表面が乾くことが無いように水やりをします。
ただ、関東以北では3月はまだ寒い日があるので、4月に入ってからの種まきにして下さい。
6-2. 移植

5月の初め頃本葉が5~6枚出たら、今迄より大きなプランターに植え替えたり、庭植えなら間引きをします。
日当りが好きなので、日当たりの良い場所に置いて下さい。
お天気が続くと藍はどんどん成長して枝分かれもしてきます。
その為枝が茂るので風通しが良い状態を保ち、土の表面が乾いたらたっぷりの水をやって下さい。
6月になると、草丈は50~60cm程にもなります。
この段階で、藍の葉を取って生葉染めを行うことが出来ます。
早く、そして沢山枝分かれをさせることが出来るので、茎を節の部分から刈り取ると良いです。
そうすると、驚く程葉が大きく成長します。
6-3. 一番刈り

7月の晴天続きの日に葉の一番刈りをします。
刈り取った後はお礼肥えとして有機肥料化固形油粕を与えると、その後の成長も順調になります。
水もたっぷりやって下さい。
また、葉が育って茎が50cm以上伸びたら二番刈りをします。
そして、同じようにお礼肥えを施します。
葉がどんどん茂るので、時々茎を切って風通しの良い状態を保ってあげて下さい。
6-4. 花芽が立ってくる

8月の下旬、涼しくなってくると花芽が立ってきます。
葉を刈り取っている間は花芽の成長は抑制されますので、染め物をしたい人は9月に入っても葉を摘み、花を楽しみたい方はこの頃からは葉を摘むのは止めましょう。
尤も、花が咲き終わった後の葉も染められます。
ただ、葉の形が変わってきますが、色素はまだ残っています。
花の時期は8月~10月頃です。
6-5. 虫害・病気

アブラムシ

特に梅雨のジメジメした時期には大量発生することがあるので注意が必要です。
アブラムシを見つけたら、テントウムシを見つけてアブラムシがいる葉に乗せるのが手っ取り早いです。
テントウムシが見当たらない場合は、牛乳を薄めて霧吹き器でアブラムシが付いている葉全部に掛けて下さい。
これでアブラムシは窒息死します。
ヨトウムシ

夜の間に藍の葉を食べてしまう厄介な虫です。
葉が筋だけになっていたらヨトウムシかもしれません。
そのような場合は、藍の葉の下に米ぬかを撒いておきます。
ヨトウムシは米ぬかを食べると下痢を起こし、脱水症状で死んでしまいます。
根切り虫

大きく育っていた藍が急に萎れたり倒れたりした場合は、株の根元に根切り虫がいるかもしれません。
根元を少し掘って、目きり虫を退治しましょう。
そうしないと他の株もやられてしまいます。
7. 種類(原種・園芸品種)など

藍(原種)
7-1. 山藍

日本最古の染料植物です。
藍と名が付いていますが、インディカンという成分が含まれていないので、青色に染めることは出来ません。
東アジア各地で自生しています。
7-2. ナンバンコマツナギ(インド藍)

木藍(きあい)として、化学合成染料が発明されるまでは主要な染料植物でした。
アメリカ南部、メキシコ辺りが原産。
7-3. ハマタイセイ

藍の種類の中でも寒さに強かったので、日本ではアイヌ民族が使っていました。
また、ヨーロッパでは中世まではよく栽培され、染料として使われていました。
7-4. リュウキュウアイ

沖縄で栽培されてきた藍。
花が本土の藍とは違い、房状ではなく葉の間に小さな花が1輪ずつ咲きます。
7-5. ソメモノカズラ

沖縄、タイ、東南アジアを中心に生息しています。
やはり染料としても使われています。
まとめ

皆さんは「藍」よりも「インディゴ・ブルー」と言った方がわかりやすいかもしれませんね。
でも、藍染めはとても奥が深いものです。
藍染めに興味の無い方でも、最近は園芸店で花の観賞用に藍が売られるようになったので、ピンク、赤、白、好きな花の色を咲かせてみませんか。
藍と聞けば、藍染めを思い出しますね。
日本で古来から行われてきた染色で、美しい藍色に染まります。
また、濃い藍色と薄い藍色があるので、上手に組み合わせると面白い作品が出来上がります。
藍染めはなかなか奥深い物がありますが、今は通販で藍染めのセットが買えますから、自宅でも気軽に藍染が楽しめます。
そんな藍染めに使われる海について書いていきたいと思います
1. 藍とはどんな花?

日本で言う藍とはタデアイのことで、タデ科・イヌタデ属に分類される1年草です。
紀元前から世界の各地で青い染料として利用されていました。
日本では、奈良時代から藍染めが始まり、それ以来どんどん全国に広まっていったようです。
「阿波藍」と呼ばれる徳島県産の物が最高級として江戸時代には最も好んで使われていました。
現在の徳島県である阿波藩は、藍に依って栄えていたそうです。
その後、明治時代にはラフカディオ・ハーンが「この国日本は神秘的なブルーに満ちた国」と日本の藍染めを絶賛した話が残っています。
2. 藍の花言葉

2-1. 「美しい装い」

日本人の衣服を美しく彩ってきた藍。
遠く奈良時代から現代まで続く藍染は、今では”ジャパン・ブブー”として外国でも人気があります。
やはり日本人の繊細な色への研究が、どんな人をも引きつける美しい藍色を染め出すのでしょうね。
江戸時代には戦も無くなり、木綿の生産量も増えたので民衆の間で衣裳への関心も高くなりました。
特に元禄の頃(1688年~1704年)には、藍染めの美しさが庶民を魅了し、大ブームとなりました。
そんなことから、この花言葉は付いたものでしょう。
2-2. 「あなた次第」

これは、藍染めと一口に言っても色の濃淡は本当に様々であることから付いた花言葉でしょう。
特に平安時代の宮中では女房装束(所謂”十二単”)の色の襲(かさね)には、女性達は皆夢中になって拘りました。
ですから、藍染めも、紺色から浅葱色と呼ばれる薄い青まで、何色もの青色が作られました。
あなたが好む濃さの藍色に染まりますよ、という意味がkの花言葉には込められているのではないでしょうか。
スポンサーリンク