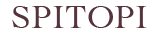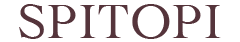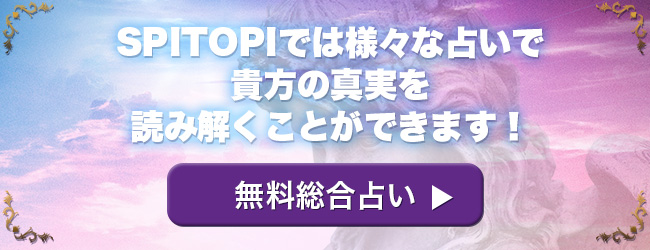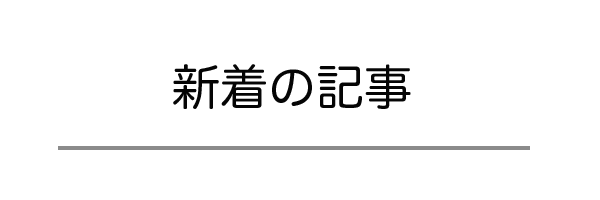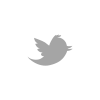春の食卓を彩る美味しいグリーン、アスパラガス。
実はアスパラガスはユリ科に属し、黄色い可憐な花を咲かせるんです。
しかし、アスパラガスの花はちょっと寂しい花言葉を持っています。
お庭に咲いたかわいらしい花を花束にするときは、少し注意が必要です。
また、あまり普段見ることの無い葉(正確には仮葉)はボリュームがあって美しく、観賞用のアスパラガスの品種もあります。
今回は、アスパラガスについてご紹介します。
- アスパラガスの花とはどんな花?
- アスパラガスの花言葉
- アスパラガスの育て方や注意点
- アスパラガスの名前の由来
- アスパラガスの開花時期
- 種類(原種、園芸品種)
- まとめ
1. アスパラガスの花とはどんな花?

アスパラガスとはそもそも、ユリ科クサスギカズラ属の植物です。
学術上はキジカクシ科アスパラガス属と分類されることもあります。
原産国は地中海東部といわれる多年草で、観賞用と食用に分けられます。
食用にされるアスパラガスは明治時代ごろに日本に伝わりましたが、その頃はよく欧米で食べられていたホワイトアスパラガスが主流でした。
なお、緑のアスパラガスと白いアスパラガスは育成方法が違うだけで同じ種類です。
高さは80センチから高くて200センチにも及び、花枝の先に釣り鐘状のかわいらしい花を咲かせます。
色は黄緑色やクリーム色などの優しい色合いです。
葉は退化しており、食用のアスパラガスの上に重なっている小さな重なりが葉です。
食用にするのはこの偽葉および茎で、実は大変小さい赤いものがなります。
なお、雌株と雄株があり、花が咲くのは雌株です。
2. アスパラガスの花言葉

アスパラガスの花言葉はあまり華々しいものではありません。
花が小さいこともあり、もし花束にするならほかの花と合わせて楽しみたい花です。
2-1. 「何も変わらない」「普遍」

アスパラガスは多年草で10年ほど収穫が可能です。
いつも青々と生い茂っている様から、変化に富まないイメージの花言葉が生まれたのでしょう。
しかし、普遍性のあることは決して悪いことではありません。
いつも変わらないことは信頼感や安心感につながります。
2-2. 「無変化」

この花言葉はマイナスイメージが強く、花束を作るときには意識したくない言葉ですね。
アスパラガスの歴史は古く、古代ギリシャ時代から栽培されていたとのこと。
そんな時代から安定して同じ姿をしているので、このような花言葉が付けられたのかもしれませんね。
2-3. 「耐える恋」

めくるめくような変化がなく、ただひたすらに同じ状況をキープしているアスパラガス。
そんなアスパラガスの姿から、我慢が必要な恋を連想したのかもしれません。
ひたむきでけなげな印象ですが、これだけの花束ですとちょっと悲しいですね。
2-4. 「敵を除く」「私が勝つ」

アスパラガスの槍のような葉茎からのイメージです。
やや攻撃的で、これも花束に向いているとは言えませんね。
3. アスパラガスの育て方や注意点

アスパラガスの花は、特に小さく観賞用に向いているとは言えません。
しかし、観賞用として青々とした葉(正確には仮葉)を楽しむ品種があります。
このアスパラガスは育て方も簡単で、見栄えもするためガーデニング初心者向けと言えます。
今回は食用としてではなく、観賞用アスパラガスの育て方をご紹介します。
3-1. 好む土や環境

観賞用のアスパラガスは、繊細な緑が蔓のように伸び、繊細なグリーンを楽しむことができます。
寄せ植えやハンギングバスケットなどでも育てやすい半面、冬の寒さにやや弱いため、鉢に植えて室内で育てることをお勧めします。
植え付けは5月から9月に行います。
元からあるアスパラガスから株分けするのでも、ポットなどで種から発芽させて植え替えるのも特に難しくはありません。
日差しを好むため日光が当たりやすい場所を選んで置きましょう。
寒さにはやや弱い傾向があるため、冬場は日当たりの良い場所を選んで室内に置くようにします。
土は用土をブレンドして水はけのよい環境を作ってあげましょう。
3-2. 水やり、肥料

鉢の土が乾いてきたら水をあげるくらいの気持ちで大丈夫です。
春と秋、年に2回緩効性の化学肥料を与えるのでもいいですし、即効性の肥料を月1~2回与えるパターンも可能です。
3-3. つきやすい虫、かかりやすい病気

青々としていつも元気なアスパラガスですが、炭そ病やさび病にかかりやすかったりカイガラムシやハダニ、アブラムシなどの害虫もつきます。
病気の場合は殺菌剤を塗布し、痛みの大きい葉枝は切り取ってしまいましょう。
虫は目視で取り除いた後、殺虫剤を散布します。
4. アスパラガスの名前の由来

アスパラガスとはギリシャ語、ラテン語で「新芽」や「若芽」を意味する言葉だと言われています。
更にさかのぼるとペルシャ語までたどり着くのが、アスパラガスの歴史の古さを物語っています。
和名はオランダキジカクシ、オランダウド、マツバウドなどと言い、当時ヨーロッパの窓口であったオランダの名前が入っているのが特徴です。
なお、キジカクシとはアスパラガスの背丈が高く、雉がいても隠れてしまうことから付けられたと言われます。
またヨーロッパで食用にされている主な品種は「ワイルドアスパラガス」といい、和名はアスパラソバージュです。
5. アスパラガスの開花時期

アスパラガスの花は5月~7月にその花を咲かせます。
そのかわいらしく小さな花は初夏から夏にかけて目を和ませてくれるでしょう。
観賞用に楽しむアスパラガスは常緑のため、地上部が枯れる寒い時期以外はグリーンを楽しむことができます。
6. 種類(原種、園芸品種)

観賞用アスパラガスはどれも緑が美しく、また季節になると咲く小さな花、その後に実る赤い実もかわいらしく人気があります。
種類は少ないのですが、育て方も簡単で元気なアスパラガスは室内で育てるのに最適です。
また、食用種と違ってトゲの無い品種もあるので、お子さんやペットがいる環境でも安心して楽しむことができます。
6-1. スプレンゲリー

よく流通しているのがスプレンゲリー。
枝分かれが細かく広がり、大きくなると茎が垂れてきます。
そのため、ハンギングで育てると大変見栄えのする品種です。
茎にとげがあるので、吊り下げて高い場所で育てるのがお勧めです。
6-2. ナナス

こちらもよく園芸店で見かける観賞用アスパラガスです。
花は小さく白いものが咲きます。
0度以上なら育てられますが、葉が落ちてしまうためできるだけ5度以上をキープしましょう。
大変繊細な葉が特徴で、髪の毛のように細い葉が楽しめるアスパラガスです。
6-3. メイリー

スプレンゲリーと大変よく似た品種です。
地面に直立し、葉の集合体がモコモコと緑の雲のように立ち上ります。
観賞用アスパラガスの中では寒さに強い方で、暖かな地方であれば庭に植えても数年楽しむことのできる丈夫な品種です。
6-4. スライマックス

蔓性の丸い葉を持つスライマックス。
他の観賞用アスパラガスの葉が細かく繊細なのに対し、スライマックスだけは大振りで豪華です。
そのため、ブーケやアレンジメントにもよく使われるアスパラガスです。
またトゲがないためお手入れも比較的楽な種類です。
まとめ

どうしても食用を思い浮かべてしまうアスパラガスですが、その花やグリーンもなかなかオツなもの。
ロマンティックな花言葉ではないので愛の告白には向きませんが、友人や気の置けない関係であればそのかわいらしい花を贈るのも悪くはないですね。
観賞用のアスパラガスは花の後に実をつけ、その様子も大変かわいらしいです。
ぜひ食べるためだけではないアスパラガスを楽しんでみてくださいね。
春の食卓を彩る美味しいグリーン、アスパラガス。
実はアスパラガスはユリ科に属し、黄色い可憐な花を咲かせるんです。
しかし、アスパラガスの花はちょっと寂しい花言葉を持っています。
お庭に咲いたかわいらしい花を花束にするときは、少し注意が必要です。
また、あまり普段見ることの無い葉(正確には仮葉)はボリュームがあって美しく、観賞用のアスパラガスの品種もあります。
今回は、アスパラガスについてご紹介します。
1. アスパラガスの花とはどんな花?

アスパラガスとはそもそも、ユリ科クサスギカズラ属の植物です。
学術上はキジカクシ科アスパラガス属と分類されることもあります。
原産国は地中海東部といわれる多年草で、観賞用と食用に分けられます。
食用にされるアスパラガスは明治時代ごろに日本に伝わりましたが、その頃はよく欧米で食べられていたホワイトアスパラガスが主流でした。
なお、緑のアスパラガスと白いアスパラガスは育成方法が違うだけで同じ種類です。
高さは80センチから高くて200センチにも及び、花枝の先に釣り鐘状のかわいらしい花を咲かせます。
色は黄緑色やクリーム色などの優しい色合いです。
葉は退化しており、食用のアスパラガスの上に重なっている小さな重なりが葉です。
食用にするのはこの偽葉および茎で、実は大変小さい赤いものがなります。
なお、雌株と雄株があり、花が咲くのは雌株です。
2. アスパラガスの花言葉

アスパラガスの花言葉はあまり華々しいものではありません。
花が小さいこともあり、もし花束にするならほかの花と合わせて楽しみたい花です。
2-1. 「何も変わらない」「普遍」

アスパラガスは多年草で10年ほど収穫が可能です。
いつも青々と生い茂っている様から、変化に富まないイメージの花言葉が生まれたのでしょう。
しかし、普遍性のあることは決して悪いことではありません。
いつも変わらないことは信頼感や安心感につながります。
2-2. 「無変化」

この花言葉はマイナスイメージが強く、花束を作るときには意識したくない言葉ですね。
アスパラガスの歴史は古く、古代ギリシャ時代から栽培されていたとのこと。
そんな時代から安定して同じ姿をしているので、このような花言葉が付けられたのかもしれませんね。
2-3. 「耐える恋」

めくるめくような変化がなく、ただひたすらに同じ状況をキープしているアスパラガス。
そんなアスパラガスの姿から、我慢が必要な恋を連想したのかもしれません。
ひたむきでけなげな印象ですが、これだけの花束ですとちょっと悲しいですね。
2-4. 「敵を除く」「私が勝つ」

アスパラガスの槍のような葉茎からのイメージです。
やや攻撃的で、これも花束に向いているとは言えませんね。
スポンサーリンク