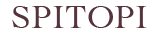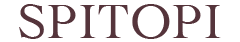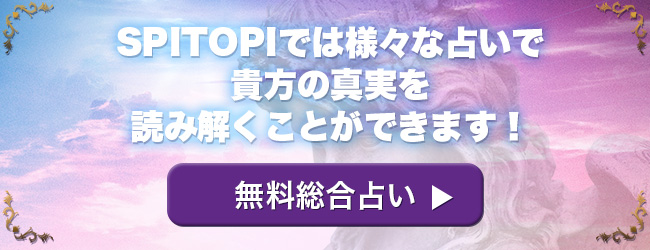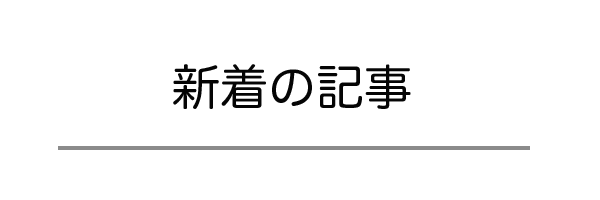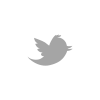「圧巻のパフォーマンスは、その一挙手一投足から目が離せなかった」
雑誌などでこんな見出しを目にした人は多いと思います。
でも、この「一挙手一投足」ってどういう意味か知っていますか?
挙手という文字や、足という字を見て、おぼろげに意味はわかるような気はするけれど…という人も、この機会にこの言葉の正確な意味、語源や由来、また、よく似た言葉である「一挙一動」とどうちがうのかも知っておきましょう。
- 「一挙手一投足とは?
- 「一挙手一投足」という言葉はこんな風に使う
- 「一挙手一投足」と「一挙一動」はどう違う?
- 昔は違った?「一挙手一投足」の語源
- 一挙手一投足に気を配る
- まとめ
1. 「一挙手一投足とは?

「一挙手一投足」とは「いっきょしゅいっとうそく」と読みます。
「挙手」とは手を挙げること、「投足」の「投」という言葉は「足を投げ出す」という言葉にもあるように、「前へ出したり付き出したりすること」という意味です。
つまり「一挙手一投足」とは、手を挙げたり、足を前に動かしたりするような、「細かな一つ一つの動作」という意味に当たります。
2. 「一挙手一投足」という言葉はこんな風に使う

「一挙手一投足」という言葉は、相手の手や足の細かな動きを言い表すときに、非常に便利な表現です。
2-1. 〈例文1〉

「踊りの師範は、弟子の一挙手一投足に厳しい目を配っていた」
細かな動作一つ一つを厳しく見守っている師範の様子がよく伝わってきますね。
また、この言葉は、文字通りの手や足の動きではなく、細かな行動のたとえとしても使うことができます。
2-2. 〈例文2〉

「生活指導の先生は、生徒たちの一挙手一投足をチェックしていた」
この場合は、手を挙げたり、足を出したり、という動作ではなく、日常の行動(授業中にちゃんと前を向いて授業を聞いているか、とか、廊下を走ったり、掃除をさぼったりしていないか、細々としたことにまで目を光らせている様子を、比喩的に表現したものです。
さらに、この比喩から転じて、注目度が高い場合に使われることもあります。
2-3. 〈例文3〉

「歴史的会談に際し、世界中が両国首脳の一挙手一投足に注目していた」
この場合は、非常に重要な会議だけに、両国首脳が握手はするか、するとしたらどちらから手を差し出すか、途中で席を立つことはないか、とどんな小さな動作も見逃すまいと、世界中の人々が固唾を飲んで見守っている様子を表す比喩表現となっています。
3. 「一挙手一投足」と「一挙一動」はどう違う?

「一挙一動」(いっきょいちどう)と「一挙手一投足」はよく似た意味の言葉です。
辞書を見ると「一挙一動」のところに「一挙手一投足のこと」と書いてあるものが多いようです。
そもそも「挙動」という言葉が、「挙動不審」という言葉にも明らかなように、「ちょっとした行動や動作」のことを指す言葉で、それに「一」を一つずつ加えた「一挙一動」も、細かな動作の一つ一つを強調する、という意味を持ちます。
つまり「一挙手一投足」と「一挙一動」は、ほぼ同様の意味と考えても大丈夫なのですが、先に挙げた例文3で見ると「歴史的会談に際し、世界中が両国首脳の一挙一動に注目していた」となった場合、声のトーンやしゃべり方、どんな表情を浮かべるか、笑顔を見せるか、とふるまい全般を指すニュアンスを帯びると受け止められるようです。
4. 昔は違った?「一挙手一投足」の語源

今の私たちは、あまりこのような使い方はしないのですが、「一挙手一投足」には「わずかな労力」という意味もあります。
4-1. 〈例文4〉

「一挙手一投足の労を惜しむ」
わずかな手間をかけるのを面倒くさがる、という意味です。
語源から考えると「一挙手一投足」の意味はこちらなのです。
4-2. 概要

話は中国の唐の時代。
韓愈(かんゆ)という人物がいました。
大変優秀な人で、3000倍ともいわれる倍率の科挙試験を勝ち残ったのですが、貧しい家の出であったために、推薦してくれる人がいませんでした。
そこで韓愈は試験官に手紙を書いたのです。
「自分は水を自由に操ることのできるほどの力を持っています、だから一挙手一投足の労(一度手を挙げ、足を出すほどの労力)を取ってくださったら、私は自分の持つ能力を発揮できます」と訴えたのです。
そこから「一挙手一投足」という言葉が、今日まで使われるようになりました。
5. 一挙手一投足に気を配る

今日では、能を見たことのある人の方が少ないでしょうが、能では能面と呼ばれるお面をかぶったまま、演技をします。
また、動きも所作が決まっていて、非常に限られた動作しかできません。
顔も見えない、動きも限られている、それでいて、非常に豊かで深い感情を表現するのが能という芸術です。
日本画家の巨匠である内村松園は、能を題材にした日本画を数多く描きました。
その松園は、能のことをこのように言っています。
「表情の移らない無表情の人の顔を能面のようなと言いますが、しかし、その無表情の能面といえども、一度名人の師がそれをつけて舞台へ出ますと、無表情どころか実に生き生きとした芸術的な表情をその一挙手一投足の間に示すものであります」
https://www.aozora.gr.jp/cards/000355/files/47312_30888.html
引用 (上村松園「謡曲と画題」)
底本:「青眉抄・青眉抄拾遺」講談社
一挙手一投足にその人の表情が現れる、というのは、私たちにも深くうなずけるものではないでしょうか。
5-1 私たちのコミュニケーションの大きな要素となっている非言語的コミュニケーション
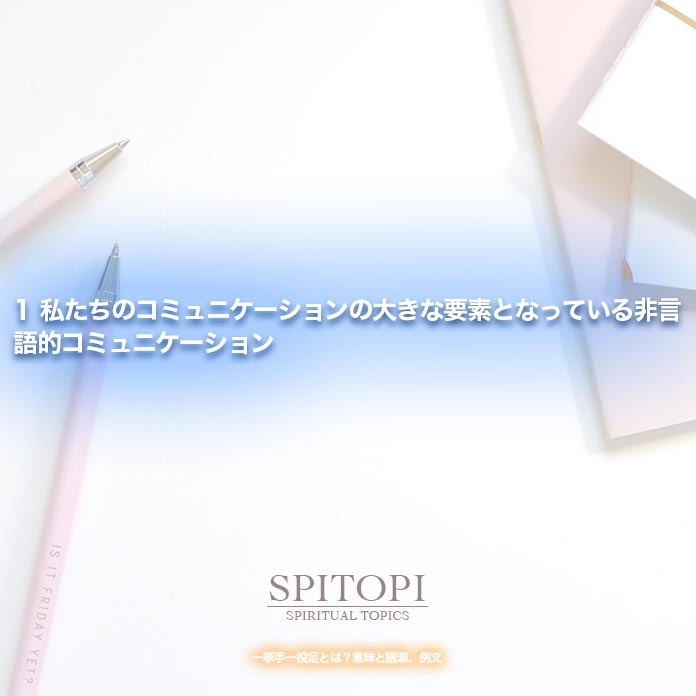
一挙手一投足に表情を見て取るのは、何も松園のような芸術家ばかりではありません。
私たちは日常、言葉を使ってコミュニケーションをしていると思っています。
ところが、実際には、対面でのコミュニケーションの場合、言葉以外の表情や動作、ちょっとした声のトーンやイントネーション、視線や身振り手振りの方が、大きな意味を持つというのです。
言語によるコミュニケーションと非言語的コミュニケーションの割合は3:7である、という研究もあります。
ラインやショートメッセージ、メールなど、言葉だけのコミュニケーションで誤解が生じやすい、という経験は誰にでもあることでしょう。
なので、言葉以外のメッセージを送るために、絵文字や顔文字、ラインスタンプなどの代替手段もつぎつぎに生まれてきました。
コミュニケーションというと、ともすれば私たちは言葉の内容に意識が向きがちですが、相手はむしろその中身より、しゃべり方や表情、声のトーンや身振り手振りから多くの意味を引き出しています。
それを考えると、改めて一挙手一投足が重要であることがわかってきます。
5-2 日常生活の一挙手一投足

日本人の作法の根幹には、禅宗の教えがあります。
禅宗では、日常生活そのものが修行である、という考え方から、食べ方や掃除の仕方、立ち居振る舞いすべてに厳格な決まりがあります。
もし機会があれば、禅宗の僧侶の方の所作を一度見てみると良いと思います。
修行をされた僧侶の方の立ち居振る舞いの美しさに驚くことでしょう。
道元禅師は、最初の心掛けがどうであれ、まず行いを改めれば、いずれ精神も備わってくる、として、食事の仕方から作り方、朝起きてからの洗面の仕方などを徹底的に教えました。
このことは、現代に生きる私たちも、参考になるのではないでしょうか。
まとめ

立派な生き方というのが、どういうものかわからなくても、まず、きちんと立つ。
歩くときはつま先まで意識を向けて、猫背でだらだらと歩かない。
話をするときにも、相手の時間を使って聞いてもらっているのだ、という意識を忘れず、きちんと相対して、自分といることで価値のあるひと時を過ごしてもらう。
そうやって、日常生活において一挙手一投足を丁寧に、意味のあるものにしていくことによって、おそらく私たちのコミュニケーションは、より豊かなものになっていくはずです。
もちろんそれが、外から見た私たちの印象を引き上げてくれることは、言うまでもありません。
「圧巻のパフォーマンスは、その一挙手一投足から目が離せなかった」
雑誌などでこんな見出しを目にした人は多いと思います。
でも、この「一挙手一投足」ってどういう意味か知っていますか?
挙手という文字や、足という字を見て、おぼろげに意味はわかるような気はするけれど…という人も、この機会にこの言葉の正確な意味、語源や由来、また、よく似た言葉である「一挙一動」とどうちがうのかも知っておきましょう。
1. 「一挙手一投足とは?

「一挙手一投足」とは「いっきょしゅいっとうそく」と読みます。
「挙手」とは手を挙げること、「投足」の「投」という言葉は「足を投げ出す」という言葉にもあるように、「前へ出したり付き出したりすること」という意味です。
つまり「一挙手一投足」とは、手を挙げたり、足を前に動かしたりするような、「細かな一つ一つの動作」という意味に当たります。
2. 「一挙手一投足」という言葉はこんな風に使う

「一挙手一投足」という言葉は、相手の手や足の細かな動きを言い表すときに、非常に便利な表現です。
2-1. 〈例文1〉

「踊りの師範は、弟子の一挙手一投足に厳しい目を配っていた」
細かな動作一つ一つを厳しく見守っている師範の様子がよく伝わってきますね。
また、この言葉は、文字通りの手や足の動きではなく、細かな行動のたとえとしても使うことができます。
2-2. 〈例文2〉

「生活指導の先生は、生徒たちの一挙手一投足をチェックしていた」
この場合は、手を挙げたり、足を出したり、という動作ではなく、日常の行動(授業中にちゃんと前を向いて授業を聞いているか、とか、廊下を走ったり、掃除をさぼったりしていないか、細々としたことにまで目を光らせている様子を、比喩的に表現したものです。
さらに、この比喩から転じて、注目度が高い場合に使われることもあります。
2-3. 〈例文3〉

「歴史的会談に際し、世界中が両国首脳の一挙手一投足に注目していた」
この場合は、非常に重要な会議だけに、両国首脳が握手はするか、するとしたらどちらから手を差し出すか、途中で席を立つことはないか、とどんな小さな動作も見逃すまいと、世界中の人々が固唾を飲んで見守っている様子を表す比喩表現となっています。
スポンサーリンク